(2005.12〜)
@Collegium Doupelle
![]() バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV
バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV
(2005.12〜)
@Collegium Doupelle
この曲は高校1年生の学園祭のときに高校のオーケストラで2ndのソロを担当した曲で、30年ぶりに同じ2ndソロ担当でCollegium
Dopupelleという社会人ユニットで練習を開始したところ。
2006年中に全楽章を演奏するチャンスを模索している曲。
| アルバム | 演奏者 | 演奏 | 録音 | 寸評 | |
| 01 | 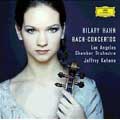 |
ヒラリー・ハーン, マーガレット・バーチャー ジェフリー・カヘイン指揮 ロサンゼルス室内管弦楽団 DG 2002.10 ロサンゼルス |
4.0 | 4.5 | 【全体】 目下現役最高のヴァイオリニストのひとりであるハーンのバッハ。 15年後くらいの円熟期にもう一度聴きたい。 【第1楽章】 快速運転だがブレない。 ここまで正確無比だとスポーツ感覚になってくる。 【第2楽章】 この楽章は普通のテンポ、ゆえに表現力に余裕を感じ、ソリスト同士のパトスの交感を感じ取れる。 【第3楽章】 これも第1楽章と同じくとても速い。 それでいて技術点・芸術点ともに高い。 若さのエネryギーがなせるワザであろう。 【録音】 メリハリのきいたスッキリとした録音。 この演奏にはこうしたシャープな音が合う。 (2006.2.9 記) |
| 02 | 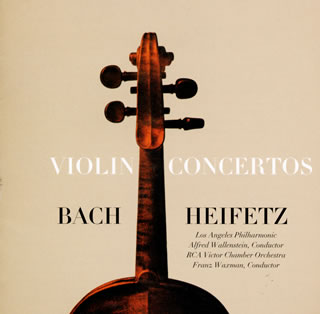 |
ヤッシャ・ハイフェッツ(1st&2nd), フランツ・ワックスマン指揮 RCAビクター室内管弦楽団 RCA 1946 ロサンゼルス、ハリウッド・スタジオ |
4.0 | 2.0 | 【全体】 ハイフェッツの一人二重録音。 やはり20世紀最大のヴァイオリニストと云われるだけあって絶妙の演奏を展開する。 全盛期の貴重な記録でもある。 【第1楽章】 端正なテンポと確実なボーイングとフィンガリング、古い録音の中から立ち昇る気品。 【第2楽章】 二人のハイフェッツの間で最初テンポ感の齟齬があるのがほほえましい。 しかし、すぐに天才的な語り口で音楽は進行する。 【第3楽章】 出だしのアインザッツの乱れ、16分音符のスピッカートの多用が気になるが、あとはスリリングな展開を見せる。 【録音】 SP盤復刻のようで針音が多い。 しかし、気になるのは最初だけで、あとはハイフェッツの妙技に引き込まれる。 (2006.2.8 記) |
| 03 | 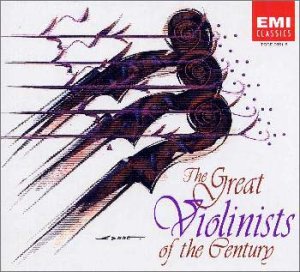 |
ヨゼフ・シゲティ(1st), カール・フレッシュ(2nd), ワルター・ゲール指揮 管弦楽団 EMI 1937 |
3.5 | 2.0 | 【全体】 この時代を考えるととてもモダンな演奏。 メニューイン盤の懐かしさとは対極にある極北ともいえる対照をなしている。 【第1楽章】 よく言われるシゲティのテクニックについて、多少のボーイングのブレはあるにせよ、いわゆる飾り気のないスッキリとしたものである。 フレッシュのほうが甘い音色。 【第2楽章】 ここも感傷に溺れることなく、精巧なバッハの世界を捉えている。 【第3楽章】 古い録音なのに整然としているのは、ソロ・バック共に自らの役割を果たしているからであろう。 【録音】 芯があり、鑑賞にはさほどの障害にはならない。 SP盤起こし。 (2006.2.9 記) |
| 04 | 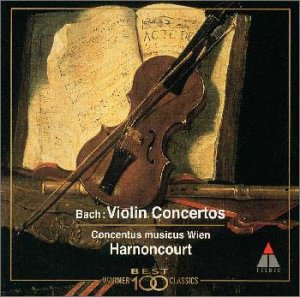 |
アリス・アーノンクール、ヴァルター・プファイファー ニコラウス・アーノンクール指揮 ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス WARNER CLASSICS 1966-1976頃 ウィーン |
4.5 | 4.0 | 【全体】 アーノンクール面目躍如の一品。 やはり随所に非凡なものを感じさせる。 【第1楽章】 いくつかの古楽器演奏と比べて、出だしから説得力が違う。 軽くなくむしろ重量感がある。 ソロも明快で、時折入るトウゥッティのアクセント、突如現れるソロのリタルダンドなど聴きどころ満載。 【第2楽章】 第1楽章から連続性のあるテンポ設定。 ソロとバックのバランスがおそろしくよい。 【第3楽章】 アーノンクール一流のアクセントの付け方、テンポの伸び縮み、いやみでなく個性として現れるところがすごい。 【録音】 1960-70年代にかけての録音としてはとても明瞭で、バランスがよい。 迫力も十分伝わってくる。 (2006.2.9 記) |
| 05 | 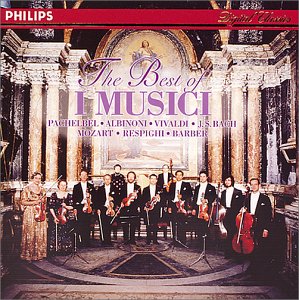 |
フェリックス・アーヨ, ロベルト・ミケルッチ イ・ムジチ合奏団 PHILIPS 1958 |
4.0 | 2.5 | 【全体】 歴代名コンマス、アーヨとミケルッチの共演。 いぶし銀のアーヨ、輝かしさのミケルッチの構図。 【第1楽章】 堂々たる横綱相撲の趣。 重厚な中にも予定調和の美しさ、醍醐味十分。 【第2楽章】 なめらかで美しい。 2人の対話が永遠に続くかに思われる。 こんなに遅くても、やはりイタリアはバタ臭くなく爽やかだ。 【第3楽章】 ゆったりとしたテンポで泰然自若としている。 うーん、さすがと唸ってしまう。 【録音】 録音は古めかしさを感じる。 特に第1楽章の始まりは時代がかって聞こえる。 (2006.2.9 記) |
| 06 |  |
ギドン・クレーメル(1st&2nd) ギドン・クレーメル指揮 アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ PHILIPS 1980.6.14-16 オランダ |
5.0 | 4.5 | 【全体】 クレーメルのソロによる二重録音。 これを聴くとやはりクレーメルは次元が違うと思う。 【第1楽章】 速めの快調なテンポ。 音はシャカシャカとなる一歩手前の例のクレーメル独特の音。 さすがにテクニックは一流で、流麗である。 【第2楽章】 なめらかな天上の音楽。 クレーメルが二人いるようで、この統一性がいい方向に作用している。 【第3楽章】 全く妥当なテンポ設定。 余分な力が入っていないので、聴き手の心に素直に入ってくる。 それでいてパッションを感じる。 言うことなし。 【録音】 聴き難さが全くなく、これ以上もこれ以下もない絶妙のバランスで録られている。 (2006.2.8 記) |
| 07 | 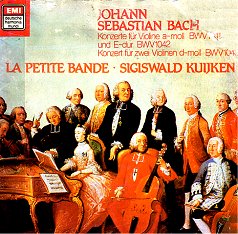 |
シギスヴァルト・クイケン(1st)、ルシー・ファン・ダール(2nd) ラ・プティット・バンド EMI 1982.6.22-26 Honrath ev. Kirche |
4.5 | 4.5 | 【全体】 メリハリの効いた演奏。 端正だがパッションを感じる。 ソリストの力関係はクイケンが一歩リードする感じ。お勧めの一品。 【第1楽章】 細部が明瞭で気持ちが良い。 テンポも妥当で、新鮮な息吹きを感じる。 【第2楽章】 モダン演奏と比べるとぶっきら棒な印象だが、なれるとその簡素さが逆にすがすがしい。 【第3楽章】 両者が主張しあいながらもまとまっていくという多少スリリングなところが絶妙な味付けとなっている。 【録音】 シャープな音像を捕らえておりソリストを浮き立たせた爽快な録音。 (2006.2.7 記) |
| 08 | 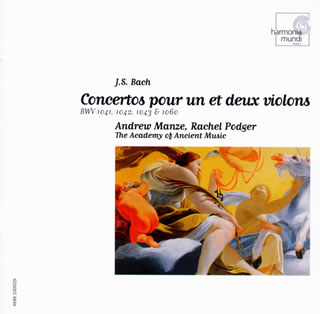 |
レイチェル・ポッジャー, アンドルー・マンゼ アンドルー・マンゼ指揮 エンシェント室内管弦楽団 harmodia mundi 1997 |
4.5 | 4.5 | 【全体】 全体を速めのテンポで爽快感がある。 装飾音も各所に施しているが、ヒラヒラと葉々が舞うようで趣がある。 【第1楽章】 キビキビとしたテンポで古楽器のよい響きが生かされている。 【第2楽章】 ほどよいテンポ設定で、ソロが交互に浮き立つ。 中間の厚みと、ちょっとはぐらかすような装飾音の対比がよい。 【第3楽章】 非常に見通しのいい進行の仕方である。 躍動感に溢れ、アクセントの置き方が特徴的。 【録音】 音の分離がよく、バランスもよい。 多少軽めなところが好き嫌い分かれるところか。 (2006.2.14 記) |
| 09 | 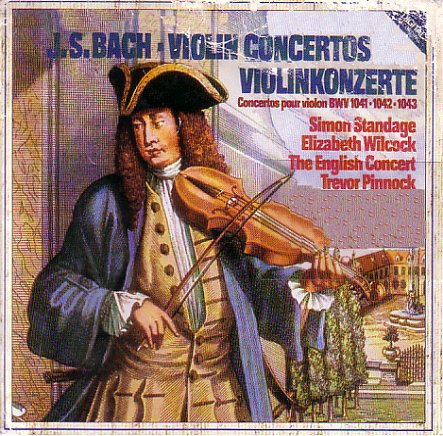 |
サイモン・スタンデイジ, エリザベス・ウィルコック トレバー・ピノック指揮 イングリッシュ・コンサート ARCHIV 1983.3.7-10 ロンドン、ヘンリーウッド・ホール |
3.0 | 3.0 | 【全体】 古楽器計の中ではまろやか派。 しかし、豊潤さに欠けるのはどれも一致している。 全体的にまとまってはいる。 ソリストは並。 【第1楽章】 ホグウッドと似た傾向だが、こちらはレガートを多用し、弓圧を加えている。 拍の頭に強いアクセントがつくので、拍のウラからのフレージングが生きてこない。 【第2楽章】 舟をこぐ感覚に襲われる。 しかし、これはこれで気持ちがよい。 中間部は独特のアクセントが印象的。 【第3楽章】 ちょっと窮屈な出だしだが、低弦が効いており次第にリズムが安定してくる。 後半のノリはなかなかのもの。 【録音】 オンマイク気味で各楽器の音は明瞭だが、広がりに欠ける。 (2006.2.8 記) |
| 10 | 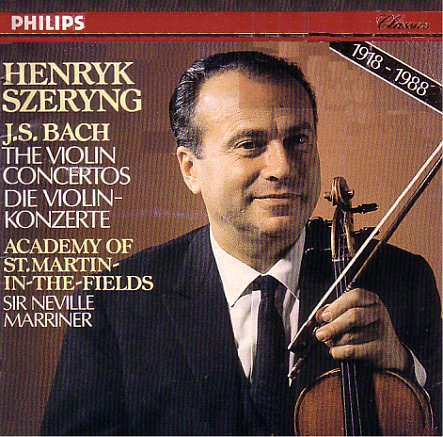 |
ヘンリック・シェリング, モーリス・アッソン ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団 PHILIPS 1976.6.23,25 ロンドン、ウェンブリー |
5.0 | 3.5 | 【全体】 やはり一番落ち着く演奏。 自分が最も参考にしたというのも大きい。 シェリングはやはりバッハの規範となる演奏家である。 【第1楽章】 妥当なテンポ、妥当なバランス、ソロ部分を我を通すことなく全体の調和を優先する。 秀逸な表現である。 ソロ両者共にいい出来である。 【第2楽章】 晴朗な表現で、吸い込まれていくようである。 この曲の第2楽章の、自分にとってのベスト・テンポ。 【第3楽章】 ニョキニョキと竹などが突き出してくるような生命力を感じる。 むやみな速さを避け、音楽あってのテンポ設定には脱帽。 【録音】 やや古くなった。 しかし髄は保っており、十分に第一線で通用するものだ。 (2006.2.14 記) |
| 11 |  |
諏訪内晶子, フォルクハルト・シュトイデ 諏訪内晶子 指揮 ヨーロッパ室内管弦楽団 PHILIPS 20058.8-10 ロンドン、ヘンリーウッド・ホール |
3.5 | 4.0 | 【全体】 とても優しいバッハ。 皮肉ではなく、お上手です。 【第1楽章】 上品で繊細な演奏である。 決して力まず、楽器そのものの響きを重視している。 ただ、なんかサワサワと撫でられているような感触がないでもない。 【第2楽章】 いやみのない素直な表現である。 この緩徐楽章においてはとても効果的だ。 もう少し潤いがあれば、と思うのは欲だろうか? 【第3楽章】 今ひとつヴェールがかかっていてもどかしさを感じる。 カデンツァを入れたのは斬新で、ハっとさせられる。 【録音】 まろやかな楽器の響きを大切にした録音。 やや芯のようなものがほしいような気もするが・・・ (2006.2.9 記) |
| 12 | 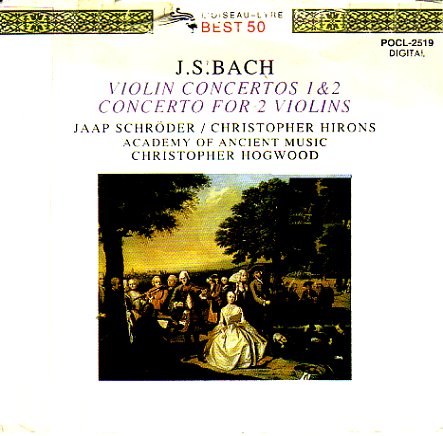 |
ヤープ・シュレーダー,クリストファー・ハイロンズ (vn) クリストファー・ホグウッド指揮 エンシェント室内管弦楽団 POCL-2159 1981年録音 |
2.5 | 2.0 | 【全体】 全体的に軽く、遅い楽章は揺れてあまり好きになれない。 【第1楽章】 これがシャカシャカしている古学器奏法というものか? ならば、モダンの方がよい。 小手先で弾いているみたい。 【第2楽章】 音符の振幅が大きすぎて酔いそう。 しかし、このサウンドにもいつしか慣れてくる。 【第3楽章】 またシャカシャカ音が耳につく。 ブッキラボー!名まで聴いたらどう聞こえるのかには興味がある。 【録音】 ややオフで低域が浅いので上澄みだけをすくって聴いているようだ。 (2006.2.8 記) |
| 13 | 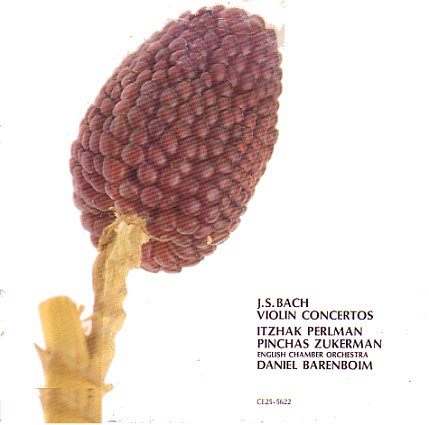 |
ピンカス・ズーカーマン,イツァーク・ パールマン ダニエル・バレンボイム指揮 イギリス室内管弦楽団 EMI 1071.6.15&16 |
4.0 | 4.0 | 【全体】 変な表情をつけず正統的なバッハ演奏を展開。 ソロの立場は対等に聞こえ、競うのではなく協調する方向で音楽を進めている。 【第1楽章】 両者とも丁寧に弾いている。 多少大上段に構え、そこが多少の煩わしさを覚えなくもない。 【第2楽章】 この楽章は両者の特質が現れ、ビロードのようななめらかさがあり好演。 【第3楽章】 丁寧に弾き込み、次第に高潮していく部分とのコントラストをうまく描いている。 【録音】 ソロの音質、オケの分離もよく捉えられている。立体感もあり比較的聴きやすい。 (2006.2.8 記) |
| 14 | 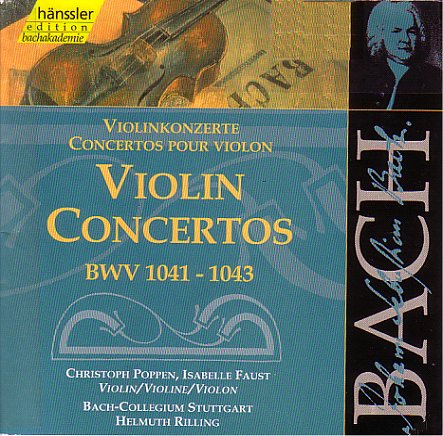 |
クリストフ・ポッペン, イザベル・ファウスト ヘルムート・リリング指揮 バッハ・コレギウム・シュトゥットガルト hanssler 1999.5 レオンブルク市民ホール |
4.0 | 3.0 | 【全体】 ソリストは二人とも切れ味がよい。 キビキビとした展開で緊張感を保つ。 好演! 【第1楽章】 活き活きとして活発なソロのやり取りが聞ける。 最後までテンションが切れることなく堂々とした終結。 【第2楽章】 速めのテンポで前楽章の流れに乗っている。 しかし、多少速すぎる感も否めない。 だんだんと情感の乏しさを覚えてくる。 【第3楽章】 適切なテンポで開始される。 ソロのフレージングが独特な部分が散見され、耳をそばだてさせる。 いろいろと考えるものだなと感心。 【録音】 やや音がやかましいが、その分輝かしさもある。 (2006.2.8 記) |
| 15 |  |
五嶋みどり、ピンカス・ズーカーマン ピンカス・ズーカーマン指揮 セント・ポール室内管弦楽団 PHILPS 1986.3 ミネソタ |
3.5 | 2.5 | 【全体】 落ち着いた演奏でガシャガシャしたところがなく安定した演奏。 後の楽章になるほどさらに安定感が増してくる。 【第1楽章】 五嶋みどりよりズーカーマンに一日の長あり。 終始ズーカーマンの妙技がリードする感じ。 【第2楽章】 これは美しい演奏。テンポ感がよく、両者が交互に現れては消える。 【第3楽章】 両者が溶け合い優麗な響きが心地よい。16分音符の速いパッセージの中にも歌を感じる。 【録音】 やや低域が重いので、今ひとつスッキリ感に欠ける。全体にボワンボワンしている。第1楽章のチェンバロが大きすぎる。 (2006.2.7 記) |
| 16 | 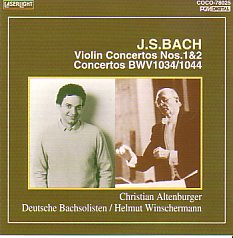 |
クリスティアン・アンテンブルガー ヘルムート・ヴィンシャーマン指揮 ドイツ・バッハ・ゾリステン Prominent 1993? |
2.5 | 1.5 | 【全体】 ソリストは線が細い。 中間楽章はいいが、両端楽章が不満。 【第1楽章】 響きが浅い。 出だしの2nd走り気味。 全体的にオブラートに包まれた感じ。 なんとも中途半端な印象。 【第2楽章】 ソリストは丹念に音を大切に弾いていてたいへんよい。 バックが何かざわついた感じで邪魔をしているのが惜しい。 【第3楽章】 対向配置の効果がよく出ている。 1stのソロがシャリシャリしていて違和感あり。 【録音】 奥に引っ込んだ感じの音で、音楽が遠い。 残響が多すぎて、輪郭がはっきりしない。 (2006.2.8 記) |
| 17 |  |
エドワルド・メルクス、 カペラ・アカデミア・ウィーン AECHIV 1977 |
4.0 | 3.5 | 【全体】 速い楽章は遅く、遅い楽章は速いといった形で描き分けている。 むしろ中間楽章の速さが全般的に重くなることを救っている。 【第1楽章】 荘厳な開始。 遅めのテンポで音楽を掘り下げる。 途中止まるのではないかとハっとさせられる瞬間あり。 【第2楽章】 意外と速いテンポ。 チェンバロのトントンという低音が耳新しい。 音楽はよどみなく流れ、なかなかよい。 【第3楽章】 テンポはゆったりめ。 一つ一つの音をソリストはしっかりと弾き分けており、説得力がある。 バックとのバランスもよい。 【録音】 全体的にバランスよく、ヴァイオリン協奏曲ということが認識できる録音。 (2006.2.8 記) |
| 18 | 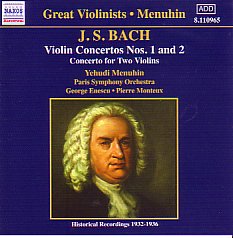 |
ユーディ・メニューイン、ジョルジュ・エネスコ ピエール・モントゥー指揮 パリ交響楽団 NAXOS 1932.6.4 Paris |
2.0 | 1.5 | 【全体】 全編レトロ!いい時代だったなぁ、という感慨が押し寄せてくる。 もちろん自分がこの時代に生きていたわけではないが、そんなことを感じさせる。 1930年代という遠い昔の揺れ具合、こういうの嫌いじゃない。 心情的には演奏には4.0ポイント付けたい。 【第1楽章】 開始から懐かしいいわゆるばいおりんの音色が響く。 拙く聞こえるところが帰って情緒をかもし出す。 【第2楽章】 連綿たる演奏が続く。 本来こういうのは時代遅れとバッサリ斬り捨てられそうだが、なぜか哀しく嬉しい気持ちにさせられる。 【第3楽章】 これもゆるーい演奏。 ポルタメントの雨嵐、否定したいが出来ないもどかしい気分。 【録音】 さすがに古いが、モノクロ映画を観て想像力がたくましくなると同じ感じ。 (2006.2.9 記) |
| 19 | 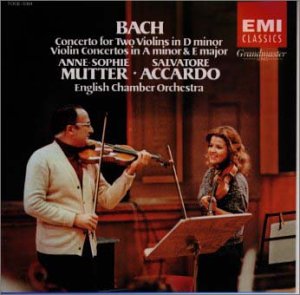 |
アンネ=ゾフィー・ムター、サルヴァトーレ・アッカルド サルヴァトーレ・アッカルド指揮 イギリス室内管弦楽団 EMI 1982.11 |
4.0 | 3.5 | 【全体】 シンフォニックで構成力のしっかりした演奏。 モダン演奏の中では1,2を争う出来。 ただし、好き嫌いは分かれそう。 【第1楽章】 非常にしっかりした造りで安定感抜群。 ソロのふたりが圧倒的で、バックの存在感が希薄なのも確か。 【第2楽章】 硬軟自在に使い分け、一転して広がりのある世界が展開する。 無限に花が開いていく光景が浮かんでくる。 【第3楽章】 劇的な展開でバロックというカテゴリーからは大きくはみ出した感のある立派なもの。 【録音】 やや大味な間もあるが、全体の音圧は強く、大きな作品を聴いた気になる。 (2006.2.9 記) |
| 20 | 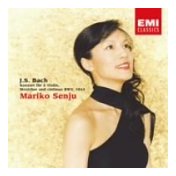 |
千住真理子, アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ 東芝EMI - September 7, 2005 |
4.0 | 4.5 | 【全体】 非常にオーソドックスなスタイルの演奏。 破綻がなく、模範的な演奏のひとつ。 二重録音でのソロの同質性はいたしかたないところであろう。 【第1楽章】 中庸のテンポ設定、合奏に重みがあり、どういうわけか2ndの法が音が厚いがボッテリしている。1stは涼やかで悪くない。 【第2楽章】 こちらは速めのテンポ。 モタモタやられるよりこの方が音楽が流れていく。 スムースにことは運び自然な印象。 【第3楽章】 縦割りを強調したバックに流線型のソロが乗る。 多少の違和感はあるが、次第に歩み寄る。 【録音】 潤いのある音で録られている。 勢いも捉えており、そのバランスが聴きやすい。 (2006.2.14 記) |
| 21 | 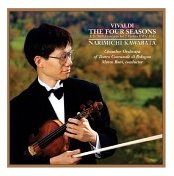 |
指揮: ボーニ(マルコ) 演奏: 川畠成道, ボローニャ歌劇場室内合奏団 ビクターエンタテインメント - 2005/12/16 |
3.0 | 2.5 | 【全体】 やや期待はずれというのが結論。 器は立派だが、どこがメイン・テーマかが見えない。 【第1楽章】 新しい要素はなく、伝統的な演奏スタイル。 もう少し奏者の訴え方が強いほうがいいような気がする。 【第2楽章】 これも美音ではあるが、淡々としている。 音が飽和状態になる感が無きにしも非ず。 【第3楽章】 これも一丸となるが、ワーン、という感じで拡散してしまう。 録り方に問題あり。 【録音】 大浴場のような音場間。 次第に落ち着いてくるが、全体に残響音が多すぎる。 (2006.2.14 記) |
| 22 | 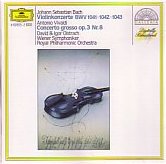 |
イーゴル・オイストラフ, ダヴィド・オイストラフ ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団, サー・ユージン・グーセンス指揮 |
4.0 | 3.5 | 【全体】 いかにも巨匠オイストラフの悠然とした足取りのバッハ。 オイストラフのバッハの無伴奏ソナタ&パルティータはソナタ1番しか残っていないので、この協奏曲は貴重。 【第1楽章】 時代を感じさせるスタイルだが、ダヴィド(父)の輝かしさ、イーゴリ(子)の渋さ、器の大きさの違いがわかる。 【第2楽章】 この楽章もデヴィドの存在感が光る。 彼の音色を聞いているだけで至福のときを得られる。 【第3楽章】 これは妥当なテンポ設定である。 ムラなく丁寧な仕上げ。 【録音】 目だって悪いところはない。 この時代の録音としてはいい方の部類に属する。 (2006.2.17 記) |
| 23 | 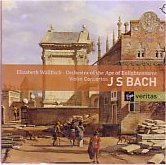 |
1999/03/12 レーベル: Virgin Classics Veritas |
4.5 | 4.5 | 【全体】 これは無伴奏ソナタ&パルティータも録音しているウォールフィッシュの協奏曲集だが、躍動感に溢れ、クリアな音色がいい方向に向かっている。 【第1楽章】 いわゆる古楽器の特徴をふんだんに入れた演奏。 重からず軽からずなかなかのもの。 【第2楽章】 最近はこの楽章はこのくらいの速めのテンポで流れていくのが好きになってきた。 ややバックがうるさい気がするが、全体的にはよい。 【第3楽章】 編成規模もちょうどぴったりと思える統一感で、この曲の最後が見事に締めくくられている。 【録音】 変な強調が全くなく、やや硬質だがむしろ透明性を高めるのに一役買っている。 (2006.2.17 記) |