
楽器購入以来お世話になっている川崎の島村楽器のアンサンブル・サークルでの活動および自主コンサート企画グループ「VPO]をまとめてあります。
練習レポート
(上に行くほど新しい内容です)
| ■2007/02/25 (日) 久々のアルジェンティーノ |
アルジェンティーノのデュオ・アンサンブルがピアノ三重奏に拡大し、2時間練習。
ハイドンのピアノ三重奏曲HV.2。
ほのぼのとした曲で、第3楽章はジプシー風に盛上がり、なかなか楽しい。
しかし、初練習でテンポが極めて遅く、まだこれからである。
といっても参加ユニットが多すぎるので時間が取れないのが実情。
| ■2006/11/04 (土) バロック・オーソリティー宅訪問 |
午前中は次男のレッスン&定演の曲目の練習。
なかなか両方ともタフで、でもみっちりやったから成果が出ることを期待したい。
午後からアンサンブル倶楽部で知り合った同年輩Kさんのお宅に7878おじさん、高校の後輩ピアノのKさんと一緒にお邪魔してチェンバロを見学に行った。
Kさんの邸宅の2Fはまさに音楽空間という感じで、天井が高く防音された部屋の中にはグランド・ピアノ、スピネット(チェンバロの小型形)、サンプリング・パイプ・オルガンなどが置かれており、音楽書の類、楽譜もたくさんあった。
まさに圧倒されるというのはこのことで、来年VPOでの貴重な戦力として期待できる人だった。
帰りは川崎のアンサンブル倶楽部の練習に出るということで駅までご一緒し、そこで別れた。
自分もアンサンブル倶楽部にはよく行ったが、今は忙しくなかなか参加できない。
そのあと7878おじさん、ピアノのKさんと軽くのつもりが、まあ、普通に4時間ほど飲んだ。
来年の方針と、役割分担などを話し合い、来年は多少楽に運営できそうだが、低弦がまだ決まらないのが最大の悩み。
これからも手分けして知り合いを手繰って探していくことにした。
あと、お二人は医薬品メーカー勤務、薬剤師なので今飲んでいる薬についていろいろ説明・指導を受けられたのも収穫。
多すぎる薬を少しずつ試しながら減らしていきたい。
| ■2006/10/20 (金) VPO幹事打ち上げ会 |
会社帰りに新橋で7878おじさん、NさんのVPO幹事で反省会&来年のプランニングと称した幹事打ち上げ会。
職場の違う人間で企画から運営、演奏までマネージしたVPOの演奏会はやはり3人にとってはかなりの達成感だったのだろう。
3人ともよく飲みました。
次回も企画書を持って行って、おおよそのところ内容的には合意。
あとは人選、場所などを具体化していく。
また自分たちの手で演奏会をやってみたい、という意志が相互確認できたのでよかった。
| ■2006/10/19 (木) VPO2006 演奏会録音 |
9/30のVPO@原宿「モーツァルトと先人作曲家たち」の演奏会録音を以下にアップした。
http://homepage1.nifty.com/relaxin-jazz/vpo/promotion_hp/promotion.html
ページの下の方にある音符の絵をクリックするとそのページにたどり着く。
クラッシックの演奏は巧拙が歴然としてしまうため、なかなか公開する勇気がなかったが、これを通過点としてもっといい演奏を目指せるよう確認の意味で公開してみた。
本番では練習の半分以下の力しか出ないというのはよく言われることだが、
昨日のルツェルンではないが、ミスも演奏のうちと開き直るのも時には必要かな、と思った次第。
| ■2006/09/30 (土) VPOの本番-1 |
VPOの本番の日。
朝8:40に原宿アコスタジオ前に集合し、事前確認を行う。
9時からホールで準備、9:10過ぎには音だし可能となりディヴェルティメントでバランスをみる。
9:30から12:00まではゲネプロで通して演奏する。
ここまできたらもうやるしかない。
昼食休憩後に皆でホールで記念撮影。
13:30開場。
思ったよりお客さんの出足はよく開演10分前にはほとんど席が埋まる。
1曲目は弦楽合奏でモーツァルトの「ディヴェルティメント
K.136」
チューニングのあと、7878おじさんが巨匠然と登場すると拍手が起こる。
第1楽章、ちょっと遅めかな、というテンポ。
2,3楽章は尻上がりに速くなり、やや荒っぽく終ったが、大きな破綻はなかった。
2曲目は高校の後輩Kさんの「キラキラ星変奏曲」。よく指が回ると感心。
演奏を終えて戻ってくると「たくさん間違えちゃった!」とのこと。
次は自分と7878おじさんとのデュオでモーツァルトの「ヴァイオリン・ソナタK.304」。
冒頭の入りで一瞬呼吸がずれる。
ヤバ!と思ったがその後は持ち直し、練習より快速調で終る。
第2楽章は出来としてはまあまあ。
哀愁も漂っていたのではないかな?
前半の最後はバッハの「2つのヴァイオリンのための協奏曲」
第1楽章は気負いもあってか、練習時よりだいぶ速いテンポだったが、推進力はあった。
聞かせどころの第2楽章はちょっと連綿たる感じで平板。
終楽章は後半半拍ずれるアクシデントがあったが、無事戻り終了。
バッハは難しい。
| ■2006/09/30 (土) VPOの本番-2 |
第2部はNさんのヴィターリの「シャコンヌ」から開始する。
7878おじさんとずっと練習を続けていただけあって聞かせられる音楽となっていたのには拍手。
2組目は会社の後輩のソプラノの女性Tさんが、先の高校の後輩の女性の伴奏でオペラ・アリア集。
楽器演奏の中にあって、やはり人間の声は人をひきつけるものがある。
あでやかな歌声とピアノに盛り上がる。
最後は1曲目と同じ弦楽合奏で「アイネ・クライネ・ナハトムジークK.525」
個人的には第2部はこの曲だけの出演なのでやや気楽に弾くことが出来た。
課題はアンサンブルの練習時間の少なさ。
個人個人はそこそこに弾けても、細かい解釈、アーティクレーションが指揮者の意図どおりに伝わらずに本番になってしまった感がある。
今後の課題となりそうだ。
アンコールはモーツァルトの晩年のモテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」を歌・ピアノを入れて全員11名で演奏。
クライネバックで一緒のMちゃんが今回は司会に専念してくれて、絶妙のトークで全体をつないで行ってくれた事も感謝である。
終演後、渋谷に移動しほぼ出演者全員での打ち上げ。
ほっとしたからかとてもにぎやかに話題が飛び交う。
今回は1回目の試みとしてやってみたが、いろいろ反省を踏まえて継続できればと思った。
| ■2006/09/18 (月) VPO本番前最後の練習 |
VPO本番前最後の練習。
午前中ドッペル、午後モーツァルト。
結局ヴィオラ、チェロがひとり欠け、完全フル・メンバーでの練習は1回も出来ずじまい。
今後はアンサンブルに出来るだけ参加できる人選が必要と感じた次第。
ドッペルはだいぶまとまってきた。
本番で集中していけばそこそこのものにはなりそう。
午前中の最後でソプラノとピアノが加わり、Ave
Verum Corups
を通す。
ヴィオラが不在なのでピアノとの合わせに不安が残るが、歌とヴァイオリンの相性はいいようだ。
午後はモーツァルトの2曲を練習。
中・低弦部の音程の合わせがもうひとつ合わないのが気になる。
しかし、もう当日のゲネプロに賭けるしかないのだろうな。
泣いても笑ってもあとは本番まで各自の個人練習に期待するのみである。
| ■2006/08/26 (土) VPO練習;ドッペル&ラーセン |
本日はミューザで9-12時ドッペル、13-16時半ラーセンとハードな一日。
午前中のドッペルは1stのTuttiのヴァイオリンとチェロの1名が欠席だが、おおむね編成どおりの音は出た。
まず各楽章ごとに練習。最初に通しを行い、細部のアンサンブルを調整していく。
次第に細かい表現まで入っていったので、各人のイメージは固まってきたのではないか?
個々の楽章のリハのあと、全曲の通し演奏を2回行う。
これはソリストにとってはかなりの負担で、自分も1stソロのNさんもだいぶヘバる。
というところで皆でランチ。
今日も蕎麦屋で定職やらそばを食べながら、午後に備える。
午後のモーツァルト・タイムはヴァイオリンとヴィオラが各1名増員されるが、1stの人が午前のみで帰ったため、1stは自分ひとりで弾く羽目に陥る。
やはり午前中の疲労は回復せず、指が思うように回らない。
ディヴェルティメントK.136は第1楽章以外は大体まとまったが、最初の雰囲気を作るのが難しい。
アイネクライネは鬼門の第2,4楽章が初めて通り、一安心だが接続部分などに不安要素が残る。
あと1回の練習でどこまで改善されるか。
「夜の女王のアリア」はとりあえず通ってはいるが、細かいところはまだまだ。
「アヴェ・ヴェルム・コルプス」は譜面自体が難しくないので、あとはどのように天上の音楽を奏でられるかであろう。
夜は長男の誕生日のため早々に帰宅。
| ■2006/08/20 (日) VPO;ラーセン |
9-12時の午前練習@ミューザ。
フルメンバーに一人欠けただけなので前回と違い、非常に充実した響を得た気がする。
やはり、合奏の力というものはたいしたものである。
ディヴェルティメントK.136、アイネクライネともに人数増加の相乗効果が表れる。
しかし、出欠を確認したり運営は一苦労である。
| ■2006/07/17 (月) VPO練習日 |
今日は雨の中、朝10時半からミューザでVPOの練習。
昨日夜中帰りだったので4時間ほどの睡眠、体が重い。
その重い体にヴァイオリンとヴィオラ(今日のヴィオラの人が初参加のため一応予備として)の2つが入るちょっと大きめなコンビ・ケースを背負って出かける。
午前中がドッペル、午後がモーツァルト。
今日はは欠席者が多く、ドッペルはソロ・ヴァイオリン2人、チェロ1人、ピアノという最初のころの編成だった。
午後のモーツァルトは完全な弦楽四重奏(1st&2ndヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)を指揮者が指揮をするという普通ならありえない練習。
午前中のドッペルは4人だったこともあり、どこが明確でないか、こうしたほうがいいのではないか、といったことがいろいろと試行錯誤の末いくつも改善され、一応方向性は定まった。
しかし、気を抜くととたんに音に表れるバッハの曲は怖いものがある。
午後はモーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」、「ディヴェルティメントK.136」、「アヴェ・ヴェルム・コルプス」を7878おじさんの指揮で練習。
「夜の女王のアリア」は次回となった。
アイネクは第2,4楽章が難しい。
特に第4楽章はよほど気合を入れてかからないとコンサートまでにちゃんと仕上がるかどうか不安。
K136もやればやるほど難しくなっていく。
去年から一緒にやっている2ndのNさんも同じことを言っていた。
バッハとはまた違う簡潔さのなかの奥深さを痛切に感じる。
これまた真剣に取り組まないとヤバいな。
今回弦楽四重奏用にアレンジした「アヴェ・ヴェルム・コルプス」は初めてあわせたが、中声部がよく聞こえず、ひょっとしたら歌とオーボエとピアノの全員参加のほうがいいかなと思い始めた。
しかし、スコア直すの面倒だし、どうしようかな。
そして疲れ切って帰途についたのであった。
| ■2006/07/07 (金) VPO 9月コンサートのホームページ |
原宿のアコスタディオ・ホールで行うVPOコンサートの公開HPを作成してアップした。
VPOの略もそこでわかる。
VPO
第1回演奏会
モーツァルトと先人作曲家たち
2006年9月30日(土)
14:00 開演(13:30 開場)
原宿アコスタディオ・ホール
http://homepage1.nifty.com/relaxin-jazz/vpo/promotion_hp/promotion.html
| ■2006/07/01 (土) VPO;ドッペル練習 |
今日の午前中はミューザ川崎でコレギウム・ドッペルの練習があった。
ソリスト2人、弦楽四重奏(チェロは2本)、ピアノのフル・メンバーでの初めての練習だった。
ひとまずどんな音になるのかがわかったのは収穫。
自分が弾き振りのような形となり、アンサンブルだけでやらせたり、ソロとのからみ、トゥッティの練習など細かく各楽章を改めて見直すことができた。
この曲は簡単なように言う人が多いが、とんでもない!
簡単な音楽など存在しないし、やればやるほどいろいろな?が出てきてそこをどう自分たちは表現するのかを考えていくこと、これが創造行為であり、これができたときの達成感を味わうときが音楽を演奏していることの一番の醍醐味なのではないかと思う。
ドッペルのメンバーもこの意識を全員が共有するとき、さらにいいものとなっていくと信じている。
| ■2006/06/24 (土) デュオ練習 |
今日はお昼から7878おじさんとデュオの練習。
共通の友人であった高校の同級生のお通夜で先週も会ったが、二人とも友人の死が尾を引いていてなんか沈みがち。
モーツアルトのホ短調のソナタなどを練習しているとその哀愁のあるメロディーについ思いが重なってしまう気がした。
それでも、このデュオは確実によくなっているのではないかと思う。
9月には彼と同窓会で30年ぶりのスプリング・ソナタ、タイスの瞑想曲などを、そして9/30は自主室内楽コンサートでモーツァルト特集を演奏する。
音楽があって救われている。
| ■2006/06/10 (土) VPOラーセン・リハーサル@ミューザ |
午前中はミューザでVPO企画の室内楽コンサートの練習。
巨匠7878おじさん指揮ラーセン弦楽合奏団の「ディヴェルティメントK.136」と「アイネク」の全楽章。
7878おじさんは精力的な指揮で全体を引っ張り、時間内に全部ひととおり終了させたのは見事。
参加団体の中では人数が多いので、この初練習はどうなるかと思っていたが杞憂に終わりほっとしている。
1stにHさんという強力な戦力が加わったことも特筆しておきたい。
また、忙しい中高校時代のチェロの先輩Iさんが駆けつけてくれたことも嬉しかった。
ところでVPOとはなにか?
私にもわからない。
名付け親のS先輩が今度練習にきたら聞いてみよう。
| ■2006/05/27 (土) 試験外出 |
入院した日、初めていかに心身ともに疲労しているかがわかった。
鉛のように重たい体。
いかんともしがたい。
しかし、徐々に体が楽になる。
今日はあえて無茶し、病院にはちょっと外出します、と言ってミューザ川崎のコレギウム・ドッペルの練習に参加。
疲れたが、楽器を弾くのはいい。
久しぶりのヴァイオリンの音色に、そしてみんなでやるアンサンブルに心なごむ。
はやくまた復活したい。
夕方病院に戻った。
| ■2006/04/23 (日) ドッペル練習 |
午前中ミューザでドッペルの練習があり、妻が出かけるため次男を練習に連れて行く。
一応学習本などを持参していったので、練習には支障はなかった。
Nさんと7878氏でとりあえず完成させて、これに弦楽四重奏を加えようというのが9月のコンサートまでの構想だが、いかんせんまだまだ曲が通ることが精一杯で、そこから先にいけない。
何がいけないかと考えたとき、3人のリズム感が違うことではないかと思い当たる。
それとNさんは合奏経験が少ないのでどうしても伴奏つきソロ・モードになってしまうのではないか?
バッハは特に音符の伸び縮みは禁句である。
そこのところを改善し、3者がバッハの音楽を同じベクトルで演奏するのが次なる課題である。
3者とも日々の練習を絶やさず、音符を覚えこんでしまうまでやらねばならない。
| ■2006/04/16 (日) デュオ・シュプリームの練習 |
7878氏と結成したデュオで、ユニット名を書くたびに恥ずかしいが、演奏のほうは2回目の練習だが、モーツァルトのヴァイオリン・ソナタ第28番は外面的には大体完成した。
あとはほんとに細かいニュアンス、モーツァルトらしさをいかに出していくかが課題である。
しかし、自画自賛だが2回でここまでいくのは、お互いが音楽を弾くのではなく表現することに興味がある証拠であろう。
内面というものを表現することは、外面的なものはもう体の一部になっていなくてはできないことだ。
| ■2006/04/09 (日) ラーセン・カルテットの練習 |
前夜の興奮も冷めぬまま、午前中は9時から12時までラーセン・カルテットの練習。
ミューザ川崎の練習室で、今回は2ndのNさんが欠席のため、会社オケのIさんにトラを頼む。
モーツァルトのディヴェルティメントK.136を各楽章40分ずつくらいかけて、細かいところ、表現の仕方などを練習し、最後に通し練習をした。
Iさんはほとんど初見だが、正確な演奏でなかなかうまくいったように思う。
9月のコンサートにも出てくれることになり、本格的にプログラムを考えなければならないな。
| ■2006/03/19 (日) ドッペル練習@ミューザ |
午後はミューザ川崎に練習に出かける。
Nさん、7878おじさん、Kさんとのドッペル・ユニット練習。
その前にヨドバシでオーディオテクニカの録音用マイクを購入。
15年間に買ってずっと使ってきたSONYのマイクが断線しそうなので同クラスのものを買ってみた。
ミューザにいくとNさん、7878氏が最後の部分の練習中。
その間に録音のセッティングを行う。
K氏もやってきたので、第1楽章からはじめる。
前回ほどのまとまりにかける気がする。
細かく区切り伴奏部分、伴奏と片方のソロだけなどいろいろ試してみる。
Kさんは別練習もあるとのことで中途退出。
3人で3楽章をやるが今日はどうしてもどこかでひっかかり最後まで通らない。
各自引っかかる部分を再点検し次回までに自主練ということとする。
第2楽章はとりあえず出来てきているが第1楽章ほどの理解度は低い。
やや消化不良なまま練習は終る。
終了後3人で会話し、コンサートの日を決めて目標を作ろうという事になった。
次回の練習日を決め予約し帰途に着く。
| ■2006/03/12 (日) アルジェンティーノ&デュオ・シュープリーム |
今日は午後からミューザ川崎でピアノとのデュオ練習がふたつ続けてあった。
ひとつめはMちゃんとのアルジェンティーノ。
曲は「望郷のバラード」と「ハンガリー舞曲第5番」。
両方とも譜面はだいたいこなせてきたのでこれからは曲の表現段階。
ここからが音楽の奥の深いところなので、細かく気が付いたところを伝え、チェックし、何度か練習して少しずつ自分たちの音楽にしていく。
今日もそれが少しずつできていた気がする。
次回の課題は「バラード」の速いパッセージの安定感と全体の物語性。
「ハンガリー」はヴァイオリン・パートをアレンジし、よりカラフルな舞踊性を加味したい。
次は7878おじさんとのデュオ・シュープリーム(たいそうなネーミングだがコルトレーンの「Love
Supreme」から取った)。
今回が初練習だが、昔も一緒にやっていたし、ジャズでも共演したことがあるので、リズム・フィーリングは非常に合う。
モーツァルトの28番のソナタと「アダージョ」K.261の2曲。
ソナタはやはり骨格がしっかりした曲なので、まずきちんと弾くこと。
それから細かいニュアンスを加えていくこと。
第1楽章は2-3回の合わせでだいぶつかめてきたが、第2楽章が難しい。
今回は譜面の細かな確認にとどまった。
「アダージョ」はレッスンでやっていたのでピアノがオーケストラのイメージをつかめば仕上がっていくだろう。
終了後は例によりお疲れのビール。
| ■2006/02/12 (日) ドッペル練習-今年2回目 |
日曜なのにまた7時前には起きだし、ヴァイオリンの練習。
毛替えをした弓に松脂を塗る。
弾き始めると、カスカスだった音が、キュッキュッという感じで太い音が戻ってきた。
まだ引っ掛かりがあるがそのうちピタリと馴染んでくるであろう。
今回は半年振りの毛替え。
やっぱり3ヶ月にいっぺんは変えないとだめだなぁ。
今日はレッスンとドッペルの練習があるのでその辺りを中心に練習。
ドッペルは曖昧だった細かいフレーズもほぼ高い精度で弾けるようになった。
やはり毎日の練習にかなうものはない。
原宿のアコスタディオに向かいドッペル今年2回目の練習。
前回と違い自分なりに、ソロ部分、スコアを見直して練習も積んできたのでなんとなく楽しみ。
始めてみるとやはり周りがよく聞こえる。
これはその成果であろう。
チェロの人が途中退出したので、前半細部を取り上げて何回か練習して、全楽章を通す。
後半もピアノ伴奏で、全楽章通した。
録音もしたので、じっくり聴いて具体的なところを次回は指摘・改善したい。
帰りは7878おじさんと軽く飲んで帰る。
レッスンで取り組むモーツァルトのソナタのピアノを彼に頼むことにする。
やはり長年共に築いてきた音楽の嗜好、深さを考えるとそうそう一緒に組める相手はいないものだ。
ちゃんと音楽をするということにお互い同意識を持っているので、30年ぶりに本格的にできそうである。
| ■2006/02/09 (木) カルテット新年会 |
今日は夜カルテットの新年会+ミーティングで久々に飲み会があるので、朝連を行う。
断酒の効果は大きく、結構時間が有効に使えて、やるべきことをやり、やりたいこともできる。
このところ録音をしているのでそのうち聞きながら、CD-Rに落としておこうと思う。
聞いていく過程で少しでも進歩が見られれば嬉しいではないか。
約10分遅刻で川崎に到着。
カルテットのミーティング会場は大抵「鳥良」。
今日もそこで行う。
個室スペースなので、会話がしやすい。
久しぶりのビールを飲むとやはりうまいなぁ!
しばらく歓談の後、あらかじめ用意してきた検討項目のプリントを配る。
一番のポイントはパートの組み換えだったが、すんなり今年は私が1stになり、Nさんが2ndに換わることになった。
曲は今まで手がけてきたモーツァルトの「ディヴェルティメント
K.136」を全楽章というのが最初の目標となった。
プラス「音楽的に仕上げる」というのが、これまでのとにかく弾くというのとは違うことで、これが達成できれば、このカルテットもグレードが上がると信じている。
いろいろあるだろうが、女性3人束ねながらやっていきたい。
| ■2006/01/14 (土) 室内楽&ドッペルのダブル練習 |
今日は夕方から会社の室内楽コンサートのための最後の合奏練習とS楽器のコレギウム・ドッペルのユニットの練習が続けてあり、箱崎→川崎への移動を含め5時に出て10時終了とハードなスケジュールだった。
室内楽のコレルリの「クリスマス協奏曲」は前回の練習が出られなかったが、ボーイングを決めておいてくれたので一安心。
しかし、伴奏部分は数えてないと落ちるので気が抜けない。
川崎へ移動のため1時間ほどで退席。
移動は雨・強風の中を楽器を抱えているのでなかなかきびしい。
なんとかたどり着くがへとへとになる。
すでにNさんと7878おじさんは先行してデュオの練習が終了していた。
チェロのKさんが遅れて到着し、練習開始。
第1楽章は通るので、中身を議論しながら進める。
Nさんの1stと私の2ndで各々の表現が食い違うので難航する。
部分と全体にわけイメージを言葉として伝えるが、なかなかぴったりとはいかない。
音符を弾くことと音楽を造っていくことの違いを痛感する。
第2楽章も同様で、私は決して一昔前の重厚なスタイルを否定するものではないが、この楽章は澄んだイメージを持っているのでガリガリとやるのには同意できない。
・・・とまあ、こんな議論をしているうちに時間はあっという間になくなり、3楽章を少しだけあわせるが、途中で合わなくなり終了。
曲へのコンセンサスというものを取らないといけないな。
次回はそれを踏まえてやっていきたい。
そういえば、ドッペル練習の時、松脂を落っことしてバラバラになり使えなくなった。
なんとなくツイてない一日。
| ■2005/12/10 (土) ドッペル&アルジェンティーノ@アコスタジオ |
今日は午後から原宿のアコスタジオというところでホール見学兼ねてのコレギウム・ドッペルの練習。
昔通った代々木ゼミナールの近くのマンションの地下が5-60名ほどのキャパの木製のホールで、2回が調整室、3回が練習室となっている。
基本的にクラシックだが、ジャズや寄席などのプロのラウブも行われているとのこと。
http://nttbj.itp.ne.jp/0334084541/index.html
とりあえず2時間の練習で第3楽章まで通すことが出来た。
ピアノとチェロが2つのヴァイオリンを下から支えてくれるので非常にバロックらしい雰囲気での演奏ができた。
今後、細かいところをつめてこのホールでリサイタル形式でやってみようという方向に進みそうだ。
そのあとはアルジェンティーノのピアノのMちゃんがきて新曲「望郷のバラード」の初練習。
歌いまわしのタイミングでの呼吸が難しく、最初はなかなか合わない。
しかし1回通したあとはお互いの呼吸が計れるようになり、だいぶよくなった。
速いパッセージ部分の精度を上げていけば意外と早く仕上がりそうな雰囲気である。
なんとなく満足感を得て、ふたりでドッペルのメンバーの待つ忘年会会場に向かう。
竹下通りの人ごみの中を掻き分け会場に着く。
もうひとりオーボエのMちゃんの到着を待ち、形だけは男女3人ずつの合コンモード。
お父さんと娘くらい年は違うけど・・・
いろいろな話で盛り上がり、9時頃に終了。
2次会の話もあったが明朝も早いので切り上げる。
今年のシマムラ・アンサンブル・サークルの打ち上げとしての一区切りといったところ。
| ■2005/11/13 (日) シマムラ第2回定演 |
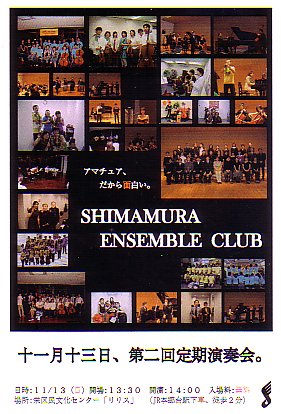 (島村楽器が作成した案内チラシ))
(島村楽器が作成した案内チラシ))
あさ9:50にJR本郷台(大船のとなり)の栄市文化センターリリスに集合。
第2回シマムラ楽器定期演奏会である。
昨年は10数ユニット参加で5ユニットに出演、今年はなんと32ユニット参加で同じく5ユニットに出演。
しかし、自分の参加するユニットの曲の難易度は昨年より相当高くなっているので練習不足感も否めず何となく不安。
ステージでのサウンドチェックが進み、ステージにたってヴァイオリンを鳴らすと結構遠くまで自分の音が響くのがわかる。
ピアノの方もスタインウェイのフルコンで昨年同様とても弾きやすい。
サウンドチェックも終了し、いよいよ14時開演を迎える。
ラーセン弦楽四重奏団
演奏曲目:
モーツァルト作曲 ディヴェルティメント第1番 K.136〜第1楽章
ハイドン作曲 セレナーデ
 (4人の楽器)
(4人の楽器)
まず最初の出演は最初から2番目のラーセン弦楽四重奏団で出演。
ハイドンの「セレナーデ」、モーツァルトの「ディヴェルティメントK.136」の2曲。
5回の練習で臨んだが、致命的なミスはなく、多少テンポ感の違うところはあったがデビューとしてはまずまずの出来。
弦四はたゆまぬ練習を続けて4人がひとつの楽器のようにならなければならないので、これを契機に今後とも続けていきたい、ということになった。
コレギウム・ドッペル(ヴァイオリン2台のデュオ・ユニット)
演奏曲目:エックレス作曲 ヴァイオリン・ソナタ(ヴァイオリン・デュオ版)全曲
 (事前の練習風景)
(事前の練習風景)
2つ目はヴァイオリンニ重奏でのエックレスのソナタ。
昨日ピアノとの合わせを行い自分的なリハは出来ていたと思うが、共演のNさんが不安だということで練習室で出演前に練習をする。
本番は事前に4楽章あります、とMCで伝えてもらったが、第2楽章がエネルギシュな終結のため期せずしてここで拍手が起こる。
そのあと第3楽章は思ったように表現できたと思う。
最終楽章は入りがミスり、やり直し。
演奏自体は2度目の頂点を迎えた中で終わり、また拍手をいただいた。
ただこうしたミスをなくしていくことがいかにアマとはいえ大切なことだと思った。
自分の音はホールで響かせることが出来たと満足。
リラクシン・デュオ(ピアノとベースのジャズ・デュオ・ユニット)
演奏曲目:
シューマン作曲 「子供の情景」から
「ムーン・アンド・サンド」
 (事前の練習風景)
(事前の練習風景)
3ユニット目はリラクシン・デュオ。
シューマンの「異国より」と「ムーン・アンド・サンド」。
最近ピアノはほとんど練習できなかったので、出演前に練習室で30分ほど練習。
昨年のような緊迫感よりリラックス感を基調に弾きはじめる。
しかし、サビの入りを間違えたり、コーラスの1部を飛ばしたり、最低限決めたことがステージ上でできるかどうかがプロとアマの違いなのだな、と改めて反省。
客席で聞いてももらった7878おじさんは「悪くなかった」と言ってくれたので、明確な破綻は少なくとも客席にはわからなかったようだ。
アルジェンティーノ(ピアノとのデュオ・ユニット)
演奏曲目:コレルリ作曲「ラ・フォリア」
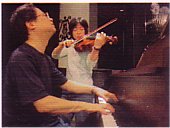 (プログラムの紹介用写真なのでお互い弾いている楽器が逆です))
(プログラムの紹介用写真なのでお互い弾いている楽器が逆です))
4ユニット目は自分の中で一番プレッシャーを持って臨んだ「ラフォリア」。
昨年同様アルジェンティーノのMちゃんとのユニットである。
総合点としては60点。
弾ききれないかもしれないと思ったところはやはり弾けなかったし、カデンツァ後半はかなりの精神力が要求され、そこから確実にいかなければいけない部分が粗くなる。
自分でカデンツァの後半は納得が行かなかった。
しかし、最後まで持ちこたえられホール全体に音を響かせることは出来たと思う。
精神的・肉体的ダメージ大だがこの曲を人前で演奏できたことへの達成感も併せて持った。
クライネバック(オーボエ、ヴァイオリン、チェロ、ピアノのカルテット)
演奏曲目:J.S.バッハ作曲 オーボエとヴァイオリンのための協奏曲〜第1楽章
 (プログラムの紹介写真)
(プログラムの紹介写真)
最後5ユニット目はクライネバックで「オーボエとヴァイオリンの協奏曲」。
ラフォリアでかなり疲れたので集中力を持ち直すのが大変だった。
オーボエのMちゃんは本番に強く、今回も練習よりいいソロを取っていたが、そのあと落とし穴があり、一瞬のずれが生じ(多分自分が1拍遅くなってしまったのだと思う)、しばらく全体がズレたまま進行。
止まるかなと思ったところでオーボエのフレーズが出て、位置を認識しあわてて修正。
危なかった。
終ってから皆、自分がずれたと思い「すいませーん」ということだったが、いずれにせよバッハは難しい。
危うい状況が予想されるうちは人前ではやってはいけないな、というのが教訓であった。
これにて出演プログラムは終了し、第4部は客席から聴く。
いろいろなユニットがいて楽しめる。
去年ぜんぜん弾けなかった初心者が成長し、1stヴァイオリンを弾いている姿にも感動を覚える。
こういう機会を企画してくれたスタッフの地道な努力に頭が下がる。
19時半頃5時間半に渡るコンサートが終了した。
自分としてはここで知り合った人たちとのユニットは大切に継続させていきたいと思っている。
アルジェンティーノ、ラーセン弦楽四重奏団、コレギウム・ドッペルは新たなる目標を終了後に確認したので楽しみながら音楽の質を上げていきたい。
帰りに7878おじさんと軽く飲んで帰る。
彼も今回の出演は刺激になったらしく、今後ヴァイオリンのNさんとのデュオもやることになりそうだ、と嬉しそうだった。
とりあえず3連チャンの一つ目がクリアされ、次はヴァイオリン教室発表会。
今週はやや仕事的に楽なので、できれば毎日練習の時間を作りたい。
さあ、明日から頑張ろう。
| ■2005/11/05 (土) 4ユニット+1の練習 |
今日は島村楽器の練習の日。
まず9時から弦楽四重奏を2時間練習。
大分形になってきたが、やはりハーモニーが難しい。
時々素晴らしく響くところもあるが、まだまだ弦楽四重奏としての響きにはなっていない。
今後定演後にどう進めていくかがこのあたりの向上の鍵になりそうだ。
続いて11時からバッハのオーボエ&ヴァイオリン協奏曲の練習が2時間。
オーボエ・パートがかなりのテクニックを要するため、四重奏の1stのNさんに補助的に入ってもらい、5人でのユニットに変える。
こちらもやはりバッハ、一筋縄では行かず、細かい部分を調整しつつ全体のテイクを5つほど重ね、最後にやっとなんとか、というところまできた。
しかし本番は集中していかないととても怖い。
時間を作って細部と全体をさらい直しておこう。
次はヴァイオリンニ重奏でのエックレスのソナタ。
基本的には弾けている。
1stと2ndのバランスが難しい。
Nさんにはピアノ伴奏のような部分、コンチェルトのような部分を多面的に要求しているが、よく応えてくれているもののもう少し時間があればさらに音程とか音量とかいろいろ打ち合わせるのができるのに、とやや勿体無い気がしている。
しかし、現状で最高のものを出せれば今回はよしとしよう。
最後はピアノとの二重奏でコレルリのラフォリア。
これはピアノのMちゃんとは相性がよく、一番弾きやすい。
重音、カデンツァも前々会より前回、前回より今回と我ながら安定してきたし、ピアノとの息もぴったりとあってきた。
一番難しい曲だが、一番仕上がっているのでそれが精神的な支えとなりそうだ。
ということで4ユニットの練習を終了し帰宅。
帰宅後は次男の発表会の曲のレッスンと二重奏の合わせを行う。
少しずつこちらも息が合ってきた気がする。
今日も練習三昧でした。
| ■2005/10/30 (日) アルジェンティーノ&ラーセンSQの練習 |
今日はまず10:30からアルジェンティーノでMちゃんとラフォリアの練習。
最初のテイクで問題点をチェック。
各変奏ごとのタイミング、ニュアンスといったものを確認。
これで1時間近くかかった。
最後の30分でカデンツァなしのテイクとありのテイクを通しで演奏。
最初のテイクより相互認識が高まり演奏自体はスムーズになる。
高度な技術を要する箇所が何箇所かあるので、その部分の繰り返し練習と、音一つ一つに込められた音楽性といったものを本番までにさらに高めていきたい。
12時から13時まではブレイク。
マイスターの無料点検でヴァイオリンの調整をお願いする。
目立った問題点はないが、ペグのゆがみ・駒の反りの調整をしていただいた。
あとネックの部分は汚れるので弾いた後は丹念にふき取ってくださいとのことであった。
13時からはラーセン弦楽四重奏団の練習。
モーツァルトのディヴェルティメントから。
1stのNさんもガット弦に昨日変えたそうで、ピッチの変動に悩んでいる様子だった。
今回は各人のリズムのニュアンスの合わせ、同じ音形で相手を聞いて合わせること、モーツァルトらしい柔らかさを出すこと・・・など
力を抜いて気張らずに演奏しないとベートーヴェンのようになってこの音楽には不似合いだ。
あと安定しないトリルのカット、低弦の不安定な動きをオクターブ下に置き換えることによる解消など、今の技術レヴェルでよく聞こえる方向に手を加えた。
ハイドンのセレナードの方は1stにミュートをつけるかつけないかで議論が分かれ、録音して聴いたとところ、譜面の指示どおり付けることに決定。
伴奏のピッチカートも2ndとヴィオラは統一した弾き方をすることを確認。
最終的にどこまで仕上がるかというところである。
| ■2005/10/23 (日) ドッペル&クライネバックの練習 |
今日の午前中はコレギウム・ドッペルで、エックレスのソナタのヴァイオリンニ重奏版。
お相手のNさんは経験者なので音符的にはあまり問題はなく、意識合わせの部分・表現記号の取扱いなどが練習の対象。
第1楽章はテンポをやや速めに取り2ndはピアノ伴奏のような淡々としたテンポ感をお願いする。
その上で1stもあまり弾き崩さないで端正な佇まいを維持する。
第2楽章は一転して躍動感が出る部分。
出だしの和音の処理を何回か試してみて、3拍目のウラの意識を共有する。
第3楽章はこれも2ndは淡々と進み、1stの強弱に合わせ、ピアノ伴奏であったり弦楽伴奏であったりする表情を出してもらうようにお願いする。
そのニュアンスは大分出てきたように思う。
第4楽章はやはり躍動感溢れる楽章だが、2ndは刻みの部分が多いので、弦楽の刻み、転調部分はあたかも木管楽器のスタッカートみたいに、と難しい要求をする。
全体は多少のほころびはあるものの大体完成したので、あと1回の練習で仕上げたい。
第4楽章はもっとテンポをあげて繰り返しもしようかどうしようかというのが最後の悩みである。
午後はクライネバックでバッハの「オーボエとヴァイオリンのための協奏曲」だったが、オーボエのMちゃんが仕事でこれず、ドッペルのNさんがまだ時間があるということで無理を行って初見でオーボエ・パートで参加してもらった。
主役との合わせがあと1回しか練習がないので不安がないわけでもないが、いつもなんとかするのがMちゃんなのでなんとかなるでしょう。
時間が余ったのでせっかくNさんがいるので、懸案のバッハのドッペル・コンチェルトを7878おじさんとK氏に初見で付き合ってもらい、とりあえず全楽章通してみた。
定演後はこのユニットで文字通りコレギウム・ドッペルで全曲を練習していこうということになったのが収穫だった。
| ■2005/10/22 (土) 10/22 午前中 カルテット練習 |
午前中はS楽器店で弦楽四重奏の練習。
今回もモーツァルトのディヴェルティメントに終始したが、ピッチの点をまず確認。
弦楽器はピアノやチューナーの平均律で1本ずつ合わせるとやはりあまりきれいではない。
Aの音から純正5度を取っていくように合わせたいが、とりあえず今日は各楽器同士で一応純正に合わせた私のヴァイオリンから1本ずつ確認してみた。
曲の方は各人のテンポ感が朝一番目覚めてないのかすっきりしない。
2nd以下の刻みの部分も弾き方がまちまちなのでまず、スタッカートでの弾きかたの統一を行う。
1stと2nd、ヴィオラとチェロ、2ndとチェロ、1st、ヴィオラ、チェロなど様々な組み合わせで試しているうちに最大公約数のようなものが見えてくる。
次に音量バランスの問題。
ヴィオラが音域的に微妙で音程はいいのだが音量が不足気味なので、そこをメンバーが指摘。
これはボーイングの問題とも絡めて今後の課題。
最後はメトロノームで108のテンポを最終とすることにして、全体をメトロノームに合わせてみる。
難関のトリルもテンポ的には大丈夫なので、あとは音程を含めた楽器感の流れが次の課題。
あと2回の練習でなんとかなるかなといったところ。
もう1曲のハイドンのセレナーデは最近手がけていないが、1stのNさんに依存する部分が大きいので次回は取り上げて気がついいた部分を全員でシェアしていい方向に持っていきたい。
| ■2005/10/17 (月) 練習録音の反省 |
弦楽四重奏はピッチの問題で、次回はチューニングを徹底して和音でメロディーが動く部分、トゥッティで全体が響く和音の和声感覚をきれいなものとしたい。
それとモーツァルトなのにベートーヴェンのような感じがするのも、力みすぎの部分があるかもしれないので、こちらもモーツァルトのイメージを共通認識としたい。
バッハの方は意外と全体のサウンドは悪くない。
ピアノという確固たる音程楽器が入っているので拠りどころとなっているのかもしれない。
ソロのパートが結構難しいので、細かい音をしっかりと峻別して曖昧さのない音程、リズム感を保つことが肝要である。
基本を確実に実践できた上での曲想の自在感、これを限られた練習の中でどこまで近づけるかが課題である。
| ■2005/10/16 (日) バッハ練習(クライネバック) |
今日は7時頃起床。
次男は野球の練習、長男は朝寝、妻は買い物?なので、パン+紅茶で朝食を取る。
そして1時間ほど練習や譜面の整理などをする。
そうこうしているうちに11時になったので、S楽器店に練習に出かける。
12時から14時までバッハの「オーボエとヴァイオリンのための協奏曲」第1楽章の練習。
ピアノの7878おじさんが全体の構成を考えてきてくれたので、それを元にして練習番号ごとにこなしていく。
彼との見解の一致は、いかにもバロック風でガチガチやるより、モダン路線でレガートを効果的に入れていく方がいいというで、実際やってみるとスケール感が広がり正解だった。
正直なところソロのバランスがよくない。
あと2回の練習でどこまでいけるか、各人の頑張りにかかっているというところ。
| ■2005/10/15 (土) カルテット練習(ラーセン弦楽四重奏団) |
夜は21-22時に弦楽四重奏の練習。
モーツァルトだけで手一杯になったが、細かく部分をピックアップして組み立てていく。
ひとまずある種のまとまりが出てきて、全体を通して終了。
1時間はあっという間に過ぎてしまい、ぜひ来週も練習を入れたいと言うことになり、土曜のオケ練の前の午前中に2時間追加練習が決定。
来週もハードな土日になりそうだ。
| ■2005/10/09 (日) 今日も2ユニット練習(コレギウム・ドッペル&クライネバック) |
今日は10時半-12時でコレギウム・ドッペル、ヴァイオリン・デュオでのエックレスの練習。
2ndをお願いしているNさんは弦楽四重奏の1stでもあるわけだが、難しい和音をよく練習してきてくれ、今回2度目の練習では音符の確認から表情記号の確認に重点を置いて行った。
特に遅い第1&3楽章はどう感じ、表現するかがポイントなので特に細かいところまで気を配った。
あと2回の練習でなんとかまとめられるでしょう。
しかし、練習あとのプログラム用の写真撮影で弾いていたら1週間前に変えたばかりのOliveのE線が切れた。
駒にチューブなしで張っていたのでちょっとヤバい気はしていたけど、最短記録だな。
少し音はこもるがチューブはつけて張ることにしよう。
12-14時はクライネバックでバッハの「オーボエとヴァイオリンのための協奏曲」〜第1楽章。
前回オーモエのMちゃんが風邪で欠席だったため、初めての4人(オーボエ、ヴァイオリン、チェロ、ピアオ)での練習だった。
やはりバッハは難曲で、遅いテンポから始めるが途中で落っこってしまい、なんどかやり直し。
効率が悪いので、かたまりごとに練習番号を振り部分的にやっていくことにする。
ピアノの7878おじさんが全体をよく聴いており、練習のポイントを指示してくれるので助かる。
最後はなんとか通るようになり、テンポアップも多少出来た。
あとは個人個人の細部の練習と全体での曲想の共通認識である。
曲が難しいので、あと3回の練習でどこまでいけるかというところかな。
| ■2005/10/08 (土) 2ユニット練習(ラーセン弦楽四重奏団&リラクシン・デュオ) |
13-15時でラーセン弦楽四重奏の練習。
女性3人に男1人という編成で、最初にモーツァルトのディヴェルティメントを合わせてみる。
ヴィオラの方も練習をちゃんとしてきてくれて一発で通る。
なんとかなりそうと皆一安心。
しかし、このアンサンブルクラブに入って1年経ってみて、皆上手くなり意見もきちんと言うようになったのは頼もしい。
今回目標のモーツァルトとハイドンのセレナーデの2曲、モーツァルトは細部のテクニックとテンポアップが当面の課題、ハイドンは1stを譜面の指示どおりにミュート付にしたところ、まろやかな雰囲気が出てきた。
次回からは中身の表現検討に入っていきたい。
15-17時は引き続きリラクシン・デュオでへらまたさんと練習。
シューマンの「子供の情景」から3曲メドレーにしようと思ったが、最初の「異国から」はジャズ・ワルツの軽やかさが出ていいが、「トロイメライ」はアレンジの練り上げが必要、「炉端にて」はちょっとこのままでは安易過ぎるかな、ということで「Moon&Sand」に変更。
やはりやり慣れているだけあって、表現の深みが違う気がする。
ということで今回は「異国から」「Moon&Sand」の2曲に決定。
| ■2005/10/02 (日) ラ・フォリア(アルジェンティーノ) |
午前中は前日の疲れも回復し、S楽器に出かける。
今日はピアノのMちゃんとのユニット・アルジェンティーノの半年振りの練習。
11/13のアンサンブル定演に出ることになったので、今年初めにやっていたコレルリの「ラ・フォリア」をやることになった。
1回通して、各変奏の移り目、テンポの確認等を行い、通しを2回やって終了。
自分的には3度音程のところ、カデンツァの四重和音などまだわかっていない部分があり、これはセンシティブな音程が要求されるので集中的に練習要。
アンサンブル的には、比較的相性がいいのか、楽に合わせられる。
昨年集中的に二人で練習したのが活きている感じだ。
あと1回練練習を持って本番に臨むが、個々の細かい課題点をクリアできればまずまずといったところかな。
| ■2005/09/25 (日) 室内楽練習日(クライネバック&コレギウム・ドッペル) |
朝起きたら11時!
12時から川崎で練習である。
飛び起きシャワーを浴び、おにぎりをほおばり、脱兎のごとく家を出る。
9時間も寝たので体力は十分。
12時5分にS楽器に着き、まずバッハの「オーボエとヴァイオリンのための協奏曲」の練習。
しかし、オーボエのMちゃんが風邪でダウン。
旧知のピアノの7878おじさん(高校時代コンビを組んでいたS氏)と初顔のチェロのK氏ととりあえず始める。
ふたりともちゃんと弾くので、あまり予習をしてこなかった私はやばかった。
しかし数回合わせるうちに細かいところも弾けるようになり、なんとかなった。
オーボエが入るとよりらしくなるであろう。
しかし7878おじさんも結構うまい。
彼のピアノで弾くとリズム的に安定してて弾きやすい。
さて、バッハの練習が終るとNさんとのヴァイオリン・デュオで次のユニットの練習。
曲はレッスンで習っているエックレスのソナタのヴァイオリン・デュオ版の楽譜を使用。
難しい2ndの方をNさんにお願いする。
最初はテンポとか難しくなかなか会わなかったが、一回メトロノームを使って全曲を通すとなんとか見えてきた。
それからは第1-4楽章までピックアップして細かい部分の確認をし、最後に全曲通して終了。
こちらはあと数回で表現を含めて完成できるのではないかという感触を持った。
| ■2005/09/20 (火) もうひとつの定演 |
オケ練に出られたからか、気持ちが楽になり、体も楽になった気がする。
やはり精神と肉体の連関はあるのだなぁ。
S楽器店の定演に出演するユニットがだんだん増えてきて4つになった。
1.去年ピアノの伴奏をしていただいたMさんと「ラ・フォリア」。
2.やはり去年オーボエとデュオで演奏したOさんとバッハの「オーボエとヴァイオリンのための協奏曲」第1楽章、チェロとピアノ(高校時代からの友人7878おじさん!)が加わったカルテットに拡大。
3.今年5月にドッペルで共演したNさんとのヴァイオリン・デュオ版のエックレスのソナタ。
4.そして一時中断していた弦楽四重奏、ヴィオラが交代して若い女性3人に私という顔合わせになり、ハイドン、モーツァルト。
それぞれに編成が違うので面白そうだ。
オケの定演の2週間前が本番なので、効率よく練習計画を立てなければ。
| ■2005/08/21 (日) Romance in-Tea@ミニコンサート |
ピアノのTさんとのユニット、Romance
in-Teaでミニコンサートに出演。
昼過ぎに2回ほど通しリハを行い、6番目中5番目の出番。
純クラシックでの参加は我々だけ。
一応アコースティック・ライブという名目の催しだったのでシンガーソングライターなどの人も参加。
場違いかなとも思ったが、結構な数のギャラリーが聴いてくれていてちょっと緊張。
1曲目の「トロイメライ」はややラフな部分も出てしまったが、全体としては陰影がつけられたように思う。
2曲目の「ロマンス ヘ長調」は普通はオーケストラ伴奏だが、今回はピアノ伴奏なのでTさんに結構負荷がかかる。
とても入念に準備してきてくれたので安心して乗っかれることが出来た。
細かいところはやはりミスもあったが、こうしたところを引っかからないようにするにはやはり不断の練習あるのみと改めて感じた。
この年になると、受ける音楽より聴かせる音楽をやりたい欲求が強くなる。
| 2005/08/10 (水) 自宅でのデュオ練習 |
今日の午後はピアノのTさんが我が家にいらっしゃって、レッスン・ルームで練習した。
たまたま家族が出かけていたのでインターラプションも入らず、2時間ほどみっちりできた。
始める前に5月のシンデレラステップでのドッペルのDVDを観る。
2階からの収録なので雑音が多く構図も遠い。
1回観ればいいね、という話になる。
練習の方は、トロイメライとロマンスin
Fで、トロイメライの休みの感覚が微妙に違うのでそこを確認し合わせる。
旋律を繰り返していく部分では表情をどのように変えていくかがまた難しい。
この曲はやればやるほど深みにはまっていくようだ。
ロマンスは大体テンポ感は合ってきたので、あとは細かい部分でどちらかが相手を待ってしまって音楽が止まってしまう箇所の点検と相互の理解をする。
まだスムーズに行かない部分もあるが、あとは本番までにイメトレで解消するということになる。
今回はスタジオ等にいかなくても簡単な練習ならこの方がお互い家も近く効率がいいかな問い言うことがわかったのが収穫だった。
| ■2005/07/17 (日) デュオ練習 |
長男に付き添ってもらい川崎に出かける。
まずヨドバシに行き、彼の誕生祝ということでMP3プレーヤー(S社のスティック)を買う。
ついでに自分のも買う。(S社のスクエア)
S楽器店でTさんとヴァイオリン・ピアノのデュオ。
長男は外をフラフラしてくるというので、2時間の練習を行う。
8月のミニコンサートに出ることになり、曲目もベトーヴェンの「ロマンス ヘ長調」とシューマンの「トロイメライ」に決定。
無難なところであろう。
練習はいつもどおりだったが、今後はより音楽的なところを合わせていきたい。
| ■2005/06/11 (土) デュオ練習 |
シマムラでTさんと久々のデュオ練習。
トロイメライから始める。
3回ほど合わせたが、難しい。
音程もリズムも簡単そうに聞こえる曲だけにちょっとした狂いが歴然とわかってしまう。
こういう曲を聴かせられるようになれば満足だ・・・が、まだ程遠い。
次はスプリング・ソナタの第1楽章。
ゆっくり目のテンポでいろいろなことを確認しながら合わせてみる。
これも奥が深い。
でも考えてやればそれだけ音楽がよくなるというのはよくわかる。
3曲目はカンタービレ。
まだちゃんと譜面を読み下していないので、Tさんに迷惑をかけてしまう。
ちゃんと弾けるようにしたい。
最後はロマンス へ長調。
これが一番弾けているかもしれない。
ピアノはオーケストラのトランスクリプションなので大変そう。
ということで、やはりデュオはいろいろと勉強になり、楽しい。
また1ヵ月後合わせの予定。
| ■2005/05/15 (日) シンデレラ・ステップ・ライブ |
今日はS楽器店主催の屋外コンサートにリラクシンとバッハのユニットで2回ずつ出演。
ミューザ川崎の練習室を9:00借りたので1人で2時間近く個人練習。
といってもグランド・ピアノがあったので半分以上は久々にピアノを弾きまくったのだが・・・
バッハの共演二人がきて数回合わせて終了。
昼になり全員集合し、サウンド・チェックを順次行う。
バッハはコレギウム・ドッペルという名前で「2つのヴァイオリンのための協奏曲」から第1楽章。
リラクシンはチックの「アルマンド・ルンバ」。
マイクでヴァイオリンを拡声するのでハウリングが気になる。
でも、仕方ないでしょという感じで本番が始まる。
そこに高校の同級生の7878おじさんがこの日記を見て聴きにきたといって突如現れ一同驚く。
例によって高級カメラをぶらさげているので写真撮影をお願いする。
バッハの1回目は入りの呼吸をピアノのTさんがうまく合わせてくれて上々の滑り出し。
Nさんとの2台のヴァイオリンの絡みも上手く行き無事終了。
次は別のユニットがひとつ演奏してからリラクシンと思っていたら、それは第2部だということで続けてリラクシンで演奏。
こちらは開始前に再三いったんからテンポを速くし過ぎないようにと釘をさされる。
やはりカウントなしで入る。
自分的には練習どおりにまとめられたかなという感じ。
休憩中になると妻と次男が現れ2Fで聴いていたとのこと。
ピアノのTさんを紹介。
帰ってから次男に聞くとピアノのおねえさん上手かった・・・たしかにTさん若い。
パパは張り切りすぎ、もっと力を抜いてだと・・・6歳が。
ほどなく年末来ほぼ毎月1回はお会いしているやはり高校の同級生Aさんが聴きに来てくれて嬉しくなる。
ということで2回目が始まる。
バッハは油断大敵とはこのことで、楽譜のクリップ止めを怠ったら、始まって3段目くらいで突風で楽譜が飛んでしまった。
途中で入るのもなんなのでソロから入り直し中断することなく終了。
1ユニットおいてリラクシン。
2回目なのでちょっとラフかと思ったが迫力優先の弾き方に変える。
ところどころ音符が飛んだが演奏としてはこちらの方が良かったかもしれない。
ドラムのTくんも休憩中に買ってきた特製スティックでさらにドライブ感が増してたし。
最後はシンデレラ・ステップで全員で記念写真を撮り終了。
疲れたけど楽しい一日だった。

| ■2005/04/30 (土) デュオ&ドッペル練習 |
午後はピアノのTさんと2時間デュオ、そのあとヴァイオリンのNさんを加えてドッペルを2時間、合計4時間の練習。
Tさんとは「スプリング・ソナタ」全曲、パガニーニの「カンタービレ」、「トロイメライ」、「ロマンス ヘ長調」を練習。
スプリングは第1、2楽章はまだ手探り部分はあるが、何とかいけそうな雰囲気。第3、4楽章はまだまだこれからだ。
カンタービレは私の方が曲をもっと覚えれば様になりそう。トロイメライ、ロマンスはこれからは表現の領域でどうしていくかというところかな。
しかし、こうした曲を次々にこなしてくれるピアノの方もなかなかいないのでとてもいいパートナーにめぐり合った気がする。
後半はNさんを加えて5/15のイベントで演奏するドッペルの第1楽章を何度も練習する。
最初重い感じだったバッハが7テイク目くらいには、軽やかなバランス感が出てきた。
多分これは大丈夫でしょう。
練習後は懇親会ということで3人で焼き鳥と十割そばのお店に行く。
とりあえず焼き鳥全種類ひとり1本ずつ、本日のお勧め料理などを注文し生ビールで乾杯。
音楽の話、家庭の話などいろいろ盛り上がる。
やはり同じ趣味の人たちとはすぐに仲良くなり話も弾む。
気がつくと10時を過ぎている。
4時間練習して4時間飲んで帰宅した。
| ■2005/04/16 (土) アンサンブル練習 |
夕方5時半からドッペルのパートナーとの練習、引き続きヴィオラ&チェロを入れてカルテットの練習。
ドッペルはレッスンの内容をパートナーに伝えるとさすがに経験者だけあり、すぐに対応してくれた。
合わせの段階から表現の段階に少し入ったかな、という感じ。
カルテットはモーツァルトのディヴェルティメントK.138の第1&2楽章を集中的に練習。
特にリズムの刻みなど1stを支える部分を注意して行った。
チェロの女性はまだ初めて2年目だが耳がよく、リズム感もあるので今後の成長が期待できるかな。
夜10時に終了。
とってもたくさん練習した1日でした。
| ■2005/04/03 (日) カンタービレ |
予定していた墓参りは延期となり、休養の一日。
ピアノのTさんがパガニーニの「カンタービレ」が好きだというので、譜面を買ってきて弾いてみる。
いい曲だ。
ぜひこれはデュオでやってみたい。
まさしくカンタービレ、歌うように、この譜面を弾くとそう弾かざるを得ない、というかそう弾いてしまう。
なかなかいいなぁ、こういうの、と思った。
| ■2005/03/26 (土) カルテット&デュオ練習 |
1ヵ月半ぶりのカルテットの練習。
ミューザ川崎の練習室は広くゆとりがあり、リラックスして練習が出来る。
前回第1楽章の前半にとどまっていたモーツァルトの「ディヴェルティメントK.137」がとりあえず第1楽章全体が通るようになった。
細かい音程、テンポ設定はまだまだこれからだが、室内楽というのはお互いの音を聴くことがとても大切だということが実感できる。
堰を切ったように「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」の第1&3楽章も通してみる。
これもレパートリーに加える事になった。
ハイドンの「セレナーデ」もあとは表情付けをどうするかというところで、一気にアンサンブルとしてのモラルアップが出来たように思う。
次回は「ディヴェルティメントK.137」の第2楽章も加えてやってみることになった。
カルテットのあとはS楽器店でアルジェンティーノ(ユニット名)Mさんと「ラ・フォリア」の練習。
最初のテイクでカデンツァも一気に弾いてみたところ全体で11分強。
そのあと細かい部分を確認して、カデンツァ省略で通してみると8分強。
なかなか長い曲だ。
この曲も大枠は仕上がったので、これからは全体の流れを掴んで1曲としてどう表現するかという段階に入っていく。
さすがに4時間弾きつづけ疲れて帰る。
| ■2005/03/22 (火) どうも今ひとつ・・・ |
帰宅後スプリング・ソナタの練習をする。
第4楽章が結構難しい。
オケの方もブラ4を練習。
第3,4楽章がやはりかなりの難易度。
いろいろと練習する曲が多く、練習スケジュールを立てるのに一苦労。
せめて体調がよければなぁ・・・
| ■2005/03/19 (土) 新しいデュオ・パートナー |
今日はピアノのTさんとの初のデュオ練習。
同窓会で30年ぶりに再開したAさんのお友だちでT音大のピアノ科出身でピアノの先生をやっているというから、かなりの腕前だろうと期待と不安で臨む。(不安は自分の腕前が追いつかないのでは?ということ)
Tさんはにこやかで人当たりの良い方だった。
最初にロマンスを合わせるが、特に破綻もなく完奏。
続くスプリング・ソナタの第1楽章もほぼ通る。
あとはお互いのテンポ感、リズム感がもう少しつかめてくれば意外とはやく仕上がりそうである。
練習後半から紹介者のAさんが見学にきて、候補曲2曲とおまけの「タイスの瞑想曲」を聴いてもらった。
30年ぶりのスプリング・ソナタは懐かしいのと、こういう音楽だったんだという新発見とが混じった印象で、ぜひ全曲を弾きたくなった。
Tさんも一応合格点をくれたようで、次回は全楽章やりましょう、ということになった。
練習のあとはTさんとAさんと3人で軽く飲んでいろいろとおしゃべりをする。
Tさんに「最近毎月同窓会やっている」というと半ば呆れられるが、Aさんが「あなたも今度来なさいよ」と誘う。
他に主婦の旦那さんへの関心はどのようなものか、など話が聞けて面白かった。
一回同窓会に出るといろいろな交流が広がり面白いな、と思った。
| ■2005/02/25 (金) 週末 |
朝練でベートーヴェンを中心に弾く。
スプリング・ソナタは毎日聴いているのでだいぶ自分なりのイメージが出来上がってきた。
やはりこの曲はベートーヴェンである、スフォルツァンドが肝。
この効果がどう出せるかがベートーヴェンらしさに近づく。
| ■2005/02/21 (月) 少し楽 |
今日は朝練と夜練各30分ずつ行う。
スプリング・ソナタの第1楽章、ロマンス
ヘ長調の譜面をよく読むと両方ともロマンティックな曲名とは裏腹にベートーヴェン特有の激しさが随所にちりばめられている。
最近はベートーヴェンという作曲家の情熱と説得力に驚かされることが多い。
| ■2005/02/19 (土) 充実の?休日 |
午後は昼寝をし、夕方次男のレッスンを見る。
課題曲は譜面づらは覚えたので、クレッシェンド、ピアノ、フォルテなど表情記号を中心に行う。
できないとフテくされるが、ともかく最後までやらせる。
曲想全体がつかめてきたようなので終了。
そのあと自分の練習をする。
昨日やらなかった分含め2時間くらい弾いてしまった。
前半はスケール、練習曲、ザイツのコンチェルト、アヴェ・マリアと来週のレッスン用の練習。
ザイツのコンチェルトは3楽章の構成で部分部分は課題があるが全体的なバランスはわかってきた。
アヴェ・マリアは音符そのものは簡単だがなかなか納得のいく表現にはいかない。
さらに練習要。
後半はラフォリア、ロマンス、スプリング・ソナタ。
ラフォリアは重音部分とカデンツァがまだ十分に弾きこなせていない。
テーマ部分の表情はだいぶついてきたように思う。
ロマンスは半音階などの細かい部分があいまい。
スプリング・ソナタはまだまだ音符の把握が不十分で、16部音符の速いパッセージの臨時記号を見落としがち。
ということで課題を分析し、さらに弾き込むしかない。
最後はバッハの無伴奏で、プレリュードは5箇所の難関を少しずつ改善中、アダージョは音符の長さの妥当性を見直し中、プレストは延々と続く八分音符の連なりを落ちないように覚えること、などが課題。
これに今日弾けなかったものとして、アンサンブルでやっているバッハのドッペル・コンチェルト、カルテットのモーツァルト、ハイドンもあるのでやはりちょっと欲張りすぎかな?
夜は少しピアノを弾く。
バッハのインヴェンションと明日のリラクシンの練習のためのおさらい。
そんなことでまたあっという間の休日であった。
| ■2005/02/17 (木) 「ロマンス ヘ長調」と「スプリング・ソナタ」 |
昨日から始めたベートーヴェンの「ロマンス ヘ長調」と「スプリング・ソナタ」を中心に弾く。
新しいピアノのTさんとはまだメールでのやり取りしかしていないが、「聴くのとやるのでは大違いでスプリング・ソナタむつかしい」とのこと。
たしかに細かいところをきちんと弾き、楽譜の表情記号を表現しようとするととても難しい。
しかし高校時代の懐かしさも蘇ってくる。
ぜひとも再演したいものである。
おまけに寝る前にピアノでインヴェンションの2声の1-4番を弾いてみる。
とてもよくできている曲だなぁ。
自分には難しいがやりがいはある。
| ■2005/02/16 (水) 近所に住むピアニストの方 |
年末の高校の同窓会以来懇意にしていただいているAさんから偶然近所に住むピアニストの方を紹介していただいた。
最初の合わせの候補曲であるベートーヴェンの「ロマンス ヘ長調」と「スプリング・ソナタ」をちょっと弾いてみる。
ロマンスは再開後も何回か弾いているのでなんとかなりそうだが、スプリングは高校時代以来なので、少し練習が必要である。
また新しい励みができバランスよく生活のリズムに乗れていきそうなのがうれしい。
夜寝る前にピアノでバッハのインヴェンションを弾く。
弾くというよりポロンポロンと鳴らす程度だが、一日の疲れが取れるようだ。
ピアノは座ってキーを叩けば鳴る。
ヴァイオリンのような表現力うんぬんまでいかないけどやはり慣れた楽器なので変な気負いがなく接することができる。
気が向いた時に2声の15曲の方だけ少しずつやってみようかな。
| ■2005/02/12 (土) アンサンブル |
午後からドッペル・コンチェルトと弦楽四重奏の練習@ミューザ川崎練習室。
初めて利用したが、広いスペースで残響もよく練習場所としては最適である。
おまけに3時間半で\2,000という破格値。
ドッペルはまだまだ細かいところはこれからだが、第1,2楽章は大体お互いの感覚があってきて大丈夫かな。
第3楽章はまだインテンポでやるには研鑽が必要。
しかし次回はピアノ伴奏を入れてやってみようということになった。
カルテットはモーツァルトのディヴェルティメントK.136の第1楽章前半部分を、細かくあいまいさを排除する要領でやっていった。
けっきょくこれで2時間近く使う。
しかし音楽にしていくためにはこれくらいの周到な練習をしていかないと意味がないし、だんだんとこうした練習法が体得され他にも生かせるだろうということでみんな納得してくれた。
きょうの練習の始まりと終わりでは、学芸会レベルから弦楽四重奏としての響き方の追求へと各人の意識が変革され、明るい展望が見えてきたと感じた。
| ■2005/01/22 (土) ドッペル練習 |
Tutunとのドッペルコンチェルトの練習のため出かける。
途中チェロのChlliちゃんからメールが入り、ふぐに当たって七転八倒の苦しみだとのこと。
彼女もとんだ災難だが、若いから早き回復を望みドッペルのあとに予定されていたカルテットの練習はキャンセルとなった。
ドッペルはさすがに経験者のTutunだけあり、1,2楽章は危なげなく通るようになった。
初めての第3楽章はゆっくりしたテンポでやってみる。
お互い3小節あいたあとの相手のソロの途中で入る部分がなかなかできない。
もちろん単純に数えていればできるが、相手のソロを聴いてしまうとあれっ?という感じで見失ってしまう。
全部で5,6回通して、なんとか全体が繋がるようになった。
この曲は高校のとき以来なので、当時よくこの3楽章を間違えないで弾けたな、と思ってしまった。
しかし、何とか形ができてきたのは収穫で、そのうち伴奏ピアノを入れてやってみたいね、という話で次回までにさらにお互い練習しておきましょうということで終了。
| ■2005/01/15 (土) アルジェンティーノ・デュオ初練習 |
アンサンブルクラブに赴きピアノのMさんとのデュオ。
夜のオーケストラも出ませんかといわれたがさすがに体力が持たないのでお断りする。
ラ・フォリアを全パート練習してみる。
この曲はテーマのあと8つの変奏曲のあとヴァイオリンの長いカデンツァがあり、ふたたびピアノとの二重奏のテーマで終わるという12-3分の大曲。
前回はテーマと6つの変奏曲までやったが、まだお互いこなしきれておらず、なかなか難しかった。
今回は曲のイメージがかなり進んでおり、とりあえず最後までいってみた。
しかし、ほんとに最初の一歩を踏み出したという感じで仕上げまでには半年近くかかるだろうな。
| ■2004/12/29 (水) 弦楽カルテットの練習&忘年会 |
朝はしんしんと冷え込むと思ったら初雪。
雪の舞う中、朝整体に行き全体をほぐしてもらう。
無理せず体を適度に動かし睡眠を十分とることが一番というのが、この一年で達した結論である。
といいながら夕方からアンサンブルのTuTun(というニックネームの美人ヴァイオリニスト)とドッペルの練習。
最初のときより予習ができていて第2楽章まで通るようになった。
とりあえず次回3楽章に突入し、それから各細かいところをチェックしていこうと思う。
そのあと彼女にヴィオラの青年と、チェロのChiriちゃんを加えて弦楽四重奏の練習。
ハイドンのセレナーデとモーツァルトのディヴェルティメントが課題。
今回はハイドンは全部、モーツァルトは1ページ目を遅めのテンポで通すことが目的。
最初はなかなか細部は合わなかったが、こうしてやっていこうということで意見をあわせ、少しずつフレーズの繰り返しをやることで段々と形が出来上がってきた。
あと何回か練習方法を考えながらやっていけば、仕上がっていくのではないかと思う。
練習後は予約した鳥良で反省会&忘年会。
いろいろ話しているうちにみなメンタル系の薬のお世話になっていることがわかり、そっち方面で盛り上がる。
でも現代にとって当たり前のもので、あとは自分が何らかの支えにより立ち直っていけるかだろうかが大事なんだということがわかってきた。
この4人にとっては音楽を合奏すること、新しい仲間でたのしくやっていくことがその一助になっていることはいうまでもないだろう。
よいお年をということで、終電の時間まで飲んで別れた。
来年の1Qのスケジュールも月1の練習ということでまとめ、また楽しみが増えた。
| ■2004/12/18 (土) アルジェンティーノの練習 |
午後はアルジェンティーノ(ピアノとのデュオ)の練習。
発表会以来の練習だ。
おさらいということで譜面をみて、美しきロスマリン、ベートーヴェンのメヌエット、タイスの瞑想曲をやってみる。
発表会以来譜面を見ないで練習していたので改めて譜面をみながら弾くと自分の中に出来上がっていたイメージとまた違うということを発見。
暗譜したものもたまにこうした確認が必要だなと思った。
そのあとラ・フォリアに挑戦。
譜面を2種類使っていたので自分的には中途半端。
ピアノもまだバロック曲的な軽さがでないので、テーマそして変奏曲ごとに表現を確認しながら進める。
とりあえずカデンツァ前のあたりまでいった。
思った以上に難曲なので当面この1曲を突き詰めてこのユニットでは練習していきたい。
| ■2004/11/29 (月) カルテット |
会社のあとアンサンブルの四重奏のメンバーと会い、美味しい鳥から揚げの店でDinner on
Meeting。
2ndの女性(ヴァイオリンとピアノとのユニットのピアニスト)がピアノに専念するので、四重奏の存続に関する議題だった。
チェロの女性はこの日素晴らしいチェロを購入したばかりでやる気マンマン。
ヴィオラの男性も続けていきたいとのこと。
私が候補として挙げたメンバーの人に二人とも賛同してくれたので、今後はその人に交渉してみることとなった。
ベクトルを合わせた上で息の長いものにしていければと思う。
| ■2004/11/22 (月) ピアノとのデュオ・ユニット |
ピアノのMさんに演奏会のビデオを渡しがてら今後の活動について話した。
彼女は多才で今回もピアノのほかヴァイオリンやヴィオラも担当した。
しかし、今後はピアノに専念して音楽的レベルを上げたいとの事。
私自身彼女は練習のたびに良くなっていくのでピアノを追求した方がいいのではないかなと思っていた。
演奏会の演奏がよかったと評価され、共演依頼がいくつかきたが中途半端になるとイヤなのでほとんど断ったそうだ。
私とのユニットはぜひ継続して続けたいといってくれたのは嬉しかった。
次回からはコレルリの「ラ・フォリア」をメインに、クライスラーの「ロンディーノ」、ドヴォルザークの「ユーモレスク」という小品だけではなく将来ソナタを見据えた曲目を選びやっていくこととなった。
自分は子供の頃にやっていた曲をきちんとした形でやり直し、音楽として表現を加えていけるのでとても意味のあるユニットだと思っている。
自分もこのアンサンブル・サークルにおいて今後何をどうやりたいのかを整理し、納得のいくものだけを続けていきたい。
| ■2004/11/21 (日) よき休日 |
午前中長男が撮った昨夜の発表会のビデオを家族で鑑賞。
なかなかよく撮れている。
自分のヴァイオリンのステージ上での演奏姿もはじめて見たが、ちゃんと構えてボーイングもまあ出来てるじゃん、と自己満足。
HDDに落として早速パートナーたちに配るDVD、ビデオのダビングを始める。
母にもDVDを渡すと喜んでみてくれた。
| ■2004/11/20 (土) アンサンブル発表会@ミューザ川崎 |
いよいよここ数ヶ月練習してきたアンサンブル・ユニットの発表会の日である。
全20ユニットのうち5ユニットに出演するのでサウンドチェックだけでも大変である。
しかも直前まで親戚の結婚式に出席していたので、自分の出演ユニットのリハーサルは無理を言って4時半過ぎに寄せてもらった。
それでも最初のユニットのリハには間に合わなかった。
終わり頃に滑り込み、そのままベース、オーボエ、ピアノ、全体アンサンブルのリハを終え、開演に備える。
式場で別れた妻は別途一時帰宅し母と子供たちを連れて会場前にはMUSAに到着。
開場し、楽器店側で確保してくれた座席とスペースに陣取り、長男はビデオ撮影のセッティングを開始する。
楽屋と会場を行ったり来たりしているうちに出番となり、まずヴァイオリンでピアノとのデュオを弾く。
各曲ちょっぴりミスはあるがそれを超えたところで思い通りの表現で弾けたように思う。
ピアノのMさんも直前までの緊張状態から打って変わりリズムの乗りもよくいい演奏だった。

3ユニットおいて今度はヴァイオリンとオーボエのデュオ。
弦1本管1本という絶妙な音量・音程バランスが要求される編成だったが、音楽を意識して練習してきた甲斐があり本番としてはいい出来だったと思う。
オーボエのこちらもMさん(ピアノとは別人)の印象がとても好評で、発表会からコンサートという雰囲気に変えてくれた。

休憩後、カノンの弦楽合奏にセカンド・ヴァイオリンで参加。
多少の崩れはあったものの最後まで持ちこたえる。
今回で終わりにするのは勿体無いので今後ともこの曲は弦楽合奏のレパートリーとしてやっていければいいな、と思った。
次の出演はラス前で今回のコンサート唯一のジャズ、そしてピアノ演奏でリラクシンのベーシストへらまたさんとのデュオお互い何回これまでに演奏したかわからない「ステラ」と「グリーンドルフィン」なので阿吽の呼吸で始める。一応最後のキメは3-6-2-5循環と決めておき無事終了。
うーん、スタインウェイのピアノは快感である。
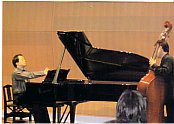
ラストはコンマス役でバッハのコラール「主よ人の望みの喜びよ」。
コンサート最後の曲という事で全員参加で壮観!
出来もリハーサルをここ数ヶ月続けてきただけあって今日の演奏が一番よかった。
終演後はみんなで記念撮影、スタッフへのお礼などがあって解散。
打ち上げには参加せず、家族と一緒に帰る。
母も次男も、よかった!と言ってくれほっとした。
妻と長男の頑張りにも感謝。
ひとつの大きな一日が終った。
| ■2004/11/13 (土) 直前練習の一日 |
練習漬けの一日だった。
ヴァイオリンとピアノのデュオは前回あたりから急速にテンポの自在感が出てきて、お互いの呼吸もかなり合ってきた。1ヶ月前とは雲泥の差である。また、全曲暗譜で弾くのにもなれてきたので音楽も息づき始めたのかもしれない。
オーボエとヴァイオリンのデュオのほうも役割分担、細かなニュアンス、全体構成が決まってきて、こちらもリズム感が出てきた。ザッツのタイミングとボーイングの再確認で本番にはベストに仕上げたい。
カノンはとりあえず最後まで通るというレベルで、じっくりと取り組んだ他のものに比べ時間の足りなさのハンディはなかなか埋められない。音楽を練り上げることに重点を置いているのでホントは今回は見送りたかったが、他の参加者の出演数を考えると仕方がないかなというところ。逆に弾ける人が引っ張っていく形にしないとしょぼくなってしまうであろう。
最後のコラールはヒヤヒヤものだったが、とりあえず管のリーダー的立場の人と事前打ち合わせをして事なきを得た。なんとか和やかな雰囲気で本番を迎えられるであろう。
終了後はカノンの自主練習を行うのを参加せずに傍聴する。とやかく言わずやってみるしかないでしょう。
残った人9人で定番のファミレスに夕食を食べに行く。
管の女の子も3人混じり若いパワーに圧倒されながらも一日の疲れが癒されるいい感じの食事会だった。
定演後はユニットを見直し、ありきたりの管、弦パートでの分奏を再検討し、みんなが楽しく向上できるやり方に変える必要があるなと感じた。
| ■2004/11/09 (火) 弦楽パート練習 |
会社の帰りにオーボエの人とアンサンブル練習に行く。
今日は弦楽のパート練習だが、コラールとチェロの強化練習を中心に行う。
ボーイングの見直しでリズム的には揃ってきた。
初心者の集まりで難しいことばかり言っても仕方がないので、強化ポイントを絞ること、これが最大の効果を生むということがよくわかった。
しかし皆音楽が好きで熱心に練習に参加する気持ちを持っていることが弦楽グループの最大の強みであるとも感じている。
音楽の内容には対立・競争の部分、協調の部分といろいろあるが、練習は全体の調和を考えたポジティブな内容でないとそこに進歩はない。
| ■2004/11/07 (日) まる一日練習 |
今日も一日アンサンブルサークルの練習。
10時からカノンで人数も揃い、形になってきた。
あと2回の練習でうまくいきそうである。
問題は11時からのコラールの練習で発生。
メンバーの和を壊す人が参加し、全体がいやな雰囲気になる。
2時間の練習時間を1時間半で切り上げそのムードを引きずらないようにした。
女性陣とランチ後、オーボエとのデュオ練習。
前回に比べリズム感がお互い出てきてデュオらしくなってきた。
もう1回の練習で細かいところを詰めれば大体OK。
次の練習までの間会社に行き仕事をする。
17:00からピアノとデュオの練習。
前回のレッスンでのサジェスチョンをピアノの人に伝え、全体をテンポアップし軽やかにする。
クライスラーもベートーヴェンもだいぶよい感じに変わった。
タイスも表情のメリハリに気をつけて演奏したところ、大分仕上がった感がある。
ということでクタクタだが収穫のある一日だった。
| ■2004/11/06 (土) ドッペルができるかも |
夕方からアンサンブルの練習に出かける。
人数は少なかったがカノンとコラールの練習を行う。
帰りに新しく入ったヴァイオリン経験者の女性と食事をして帰る。
音大受験のカリキュラムとか、どんな曲をやったのか聞いたりしてなかなか会話が弾んだ。
発表会後はバッハのドッペルを一緒にやりましょうということで意気投合する。
| ■2004/11/03 (水) 練習&レッスン |
今日も午前中はアンサンブル・クラブでの練習。
10時からジャズ・デュオ、11時から弦楽四重奏。
最初狭くてベースが入らないかと思ったがここの練習室でもベースとのデュオ練習が可能なことがわかった。
弦四はアイネクライネの第3楽章と第1楽章前半で、まだまだこれからだがみんなやる気満々なので来年には形になるのではないかな。
ランチ後移動してヴァイオリンのレッスンを受ける。
発表会での3曲をみていただく。
詳細はレッスン再開記で。
と盛りだくさんの一日だった。
| ■2004/10/30 (土) レッスン&アンサンブル |
夕方からアンサンブル・サークルに行き、新曲「パッヘルベルのカノン」を合わせる。
最初は誰がどこを弾いているのかわからなくなるのでスコアをだしてもらい、目印となる箇所を確認する。
それからはメリハリが出てきてなんとか本番に間に合うのではないかな、という気になってきた。
次は大所帯の「コラール」でコンマスのお仕事をする。
こちらは数をこなしているだけあって大分まとまってきたので、不明瞭な部分をピックアップし何度も練習する。
最後の頃はカルテットもコラールも同じ意識で曲に参加できてきていい仕上がりとなった。
そのあとオーボエの人も参加していたので二人でデュオの練習をする。
二人は難しいが、面白い。
ということでまたしても目一杯の一日だった。
| ■2004/10/26 (火) デニーズ |
アンサンブル・サークルの練習に行き、コンマスということになったので全体の練習を見る。
全部ではなくある箇所を抜き出して弦楽パート、コラール・パートのそれぞれ意識のもち方をわかってもらう。
音楽を創ることの意味が伝わればもっとよくなると思う。
帰りは健康的にデニーズで夕食。
酒も飲まないのに盛り上がり、帰りは11時過ぎになってしまった。
| ■2004/10/24 (日) アンサンブル練習日 |
今日はアンサンブルの練習フル稼働。
・11:00からアイクラを弦楽四重奏で1時間。
(初めての合わせだったが3楽章は大体通る。次回は1楽章だ。)
・12:00からコラール全体練習を1時間。
(総勢20名ほどの管弦楽に拡大した。コンマスをやることになった。)
・14:00からピアノとのデュオを2時間。
(タイス、メヌエットはだいぶまとまってきた。ロスマリンのテンポに再考要)
・16:30からオーボエとのデュオを1.5時間。
(初の合わせ、バッハ中心だが音程を作る楽器同士、難しいけど面白い)
| ■2004/10/19 (火) カノン |
今日は夜8時過ぎまでミーティングがあり、それから楽器店を覗くと2ndとviolaのふたりで練習をやっていた。
1stで加わり30分ほど参加。
コラールばかりやっていたので、パッヘルベルのカノンをやろうと店の人が譜面を持ってくる。
初めて弾いたが非常に長い曲だ。
拍数も長く時々見失う、がなんとか最後までいった。
帰りは3人でお好み焼きを食べて帰る。
疲れたが、なんとなくいい感じの一日の終り方だった。
| ■2004/10/16 (土) レッスン&調整&アンサンブル |
今日は久々にヴァイオリンのレッスンに行ってきた。
初めて電車で行ったので回り道をして10分の遅刻、でもその分延長してやってくれた。
だんだん基本テクニックから音楽表現の指導が増えてきている気がする。
詳しくは近日中にレッスン記の方に載せよう。
そのあとヴァイオリンのお店に行き、マイスターの方に定期点検をしてもらう。
気になっていたG、D、A線のペグの調子だが、やはり全体に乾いているのと、弦を入れる穴の位置が適切ではないとのことで調整。
とても調弦がしやすくなった。
今回の仕入れで初めて100万円以上のクラスのヴィオラも仕入れてきたというので弾かせてもらう。
ヴァイオリンの購入時最後までどちらにしようかなぁ、と悩んだクレモナのRocaterriという人の作品。
ヴァイオリンの造りと見た目、音色の傾向が良く似ている。
よく練れたひなびた感じ。
購入したMorenaは華やかだが正反対の印象だが、これも好きだ。
しかし、試奏させてもらうだけでとりあえず満足。
それからアンサンブルの練習で今日は新しいヴィオラの人2名が入り、管も2本来て11名。
コラール部分、四重奏部分お互いがなにをやっているかを突っ込んで練習し、成果があがったように思う。
| ■2004/10/02 (土) 弦+管の合奏練習 |
バッハのカンタータの練習。
本日はヴァイオリン8名プラスお店の人のヴィオラ、チェロ2名に会社の同僚のオーボエが初参加、さらに管のグループからクラが加わり練習室が満杯の状態。
1stのパートが4名なのでバランスが悪いと管の人から指摘される。
たしかにそろそろパートを固定して効率よく練習をしていく時期に入っていると思う。
運営しているお店の人が全てを切り盛りしているのでなかなか首尾よく行かないがここは温かく見守ることにしよう。
終了後は12名で飲み会でまたも盛り上がる。
アイクラを演奏する弦楽四重奏団も結成し、今月中に初練習することになった。
| ■2004/09/28 (火) パート練習 |
今日の夜のアンサンブルはバッハのカンタータの練習。
本日はヴァイオリン4名プラスお店の人のヴィオラ、というちょっとさみしい集まり。
2ndの人と2ndのパートを一緒に練習。
この前はヴィオラのパートも弾いたので四重奏の各パートの動きが少しわかってきた。
最後に低音部なしで四重奏とコラールを合わせて終了。
| ■2004/09/21 (火) BOW試奏&アンサンブル |
19:00のアンサンブル練習の前に楽器店に行くとスタジオの1室にヴァイオリンの弓がたくさん並べておりお店の人が自由に弾いてみてください、というのでいくつか弾いてみる。ARCUSのカーボン弓はとにかく軽い。軽すぎて飛んでいってしまいそう。やはり自分のLucasが最高と納得。
アンサンブルはバッハのカンタータ。
練習はメンバーの友だちのプロの女性チェリストが特別ゲストとして参加。
さすがに低域のリズムが締まり演奏全体に躍動感が出る。
リズムパートの強化ということでヴィオラが手薄なのでヴィオラを借りて弾く。
人前で弾くのは初めてだが、楽器が弾きやすいので面白くなってしまう。
その後ヴァイオリンに戻るとなんと小さく感じられることか。
何回か通していくうちにようやく自分たちそれぞれを聴きあうことができてきたという感じ。
まだまだいろいろとあるが、とりあえず楽しんでやれればいい。
| ■2004/09/14 (火) アンサンブル |
会社の会議が長引き、最後の15分だけ参加。
バッハのカンタータを2度通して弾いただけだが、疲れがスーッと抜ける。
いい音楽だなぁ。
| ■2004/09/11 (土) 個人練習&デュオ&アンサンブル |
19:00からアンサンブルの練習があるのでその前に18:00からスタジオを借りて個人練習、
ベートーヴェンの協奏曲、バッハ無伴奏を練習する。
場所が変わると音の特性も変わるので慣れるのに少しかかるが、どんな場所でも臨機応変に対応できるようにするにはこうした積み重ねが必要であろう。
18:30からピアノのMさんとデュオの練習、
ベートーヴェンのメヌエット、トロイメライをテーマに、楽譜の解釈と表現の志向性の打ち合わせながら進める。
あっという間に30分経ってしまったが、こういう音楽的な意見の交換が楽譜面を弾くことから音楽を表現するために必要なことだと思う。
次回からは練習前にお茶でも飲みながらこのように曲の確認をしてから音出しをすることにした。
19:00-21:00過ぎまでアンサンブル練習。
最初弦楽四重奏のみで練習。
今日が初めてヴァイオリン、ヴィオラ、チェロが揃った記念すべき練習だそうで、自分も前回の管入り全体練習以来2回目の参加。
内声部がモヤモヤするが何回か中断後、最後まで通る。
そのあとコラール組が参加するので弦楽四重奏組と別室でパート練。
私はコラール組の指導を任せられる。
初心者の女性4人にコラール・パートを弾かせるが、最初はテンポ感覚がバラバラで合わないので指揮をしながら音の長さを楽譜どおりのリズムで弾くことをやってみると途端にアンサンブルの精度が上がる。
最後は電子ピアノで低弦部を弾きその上に乗せると大体のところうまくいった。
指揮者が音楽を作っていく断片を味わえたのは面白かった。
そのあとミーティングをかねて飲み会。
若い女性が多く、場違いかと思ったがそんなこともなく、音楽やもろもろの話でおおいに盛り上がる。
これもヴァイオリンを再開したおかげで、新しい人たちと知り合うことができよかった。
| ■2004/09/05 (日) ヴァイオリン&ピアノ 初アンサンブル |
今日は昼過ぎからアンサンブル・サークルのMさんと2時間スタジオでヴァイオリンとピアノのデュオの練習。
結局用意した9曲はとりあえず完奏。細かいところは順次練り上げていくとして、ちゃんと準備をしてきてくれるところがありがたい。
あと2,3回合わせれば音楽的な部分まで踏み込んで仕上げていくことができそうだ。
Mさんはピアノのみならず、ヴァイオリン、ホルンの経験もあるそうで、大学では室内楽研究会に所属していたというキャリアの持ち主。
ベートーヴェンのメヌエット、タイスの瞑想曲、トロイメライ、等々有名どころだが、なかなかピアノと合わせる機会の少なかった曲ができて本当に嬉しい。
次回の練習日も決め、新曲も2曲追加し、このユニットは順調に進みそうな気がする。
| ■2004/09/01 (水) 週末への準備 |
今日は最近のヴァイオリン練習状況でも書いてみよう。
次の土曜はヴァイオリンのレッスン、日曜はピアノとの合わせがあるので、最近の練習はその2つを中心に行っている。
夜は1時間ほどピアノとの合わせの曲を中心に楽譜の確認、いきなり10曲近くやるが、初めての曲は3曲ほどなのでなんとかなりそう。
難しいのは「愛の挨拶」ホ長調の音程、ニ長調版もあるがこちらは簡易バージョンなので大分楽。しかし、やはりホ長調の方がやりがいがある。
あと「タイースの瞑想曲」、「ベートーヴェンのメヌエット」等ピアノの生伴奏で弾けるのはうれしい。
どんな風な演奏になるか、これまた楽しみである。
| ■2004/08/27 (金) ピアノとのアンサンブル打ち合わせ |
会社のとなりの楽器店でピアノのMさんと会い、練習曲目を決める。
ベートーヴェンのメヌエット、トロイメライなど小品を10曲ほどセレクト。
来週合わせることになった。
今は公私ともどもアップアップなのでこのくらいの多少余裕のある選曲だと気が楽である。
とはいっても逆に細心の表現を心がけなければならないのでかえって難しいかも。
| ■2004/08/22 (日) アンサンブル・サークル初参加 |
S楽器店のアンサンブルの練習に初参加。
行ってみるとヴァイオリン4名、チェロ1名、クラリネット2名、フルート3名、アルトサックス1名、トランペット1名、ピアノというメンバー。
曲は「主よ、人の望みの喜びよ」。
私は1stヴァイオリンを受け持つ。このパートはほとんど最初から最後までメロディーを弾く。
チェロの刻みに乗って弾いていき、他のパートはコラール(合唱)部分をハモる。
ヴァイオリンの女性陣は初心者ということでやはりコラール部分を担当。
隣に座った方はうちの会社のお客さんらしく、となりのビルの研修受けに行ったことありますよ、ということでドッキリ。
店の弦楽器担当のおにいさんが2nd、ピアノがヴィオラ部分を弾くという変則的な編成。
自分のパートはほぼ弾けたのでほっとした。
11月に発表会があるので、出だしは「1stに指示を出してもらいましょう」と言われる。
でもその日は親戚の結婚式で出れません、というとみんなから「えーっ!そこまで弾いておいてそんなー!」との声。
そう言ってもらえるだけありがたい。
何十年ぶりかでコンマス的感覚も味わえよかった。
帰りにピアノの女性と一緒になり、最近伴奏してくれる人といろいろセッションしているんだよね、と言うと「私でよかったらちょっと合わせてみませんか」ということになり、その方とも9月に入ったら1回合わせてみることにした。
とにかく時間が限られているので新しい曲をバンバンやるというのは無理なので、小品で弾けるものを中心にやっていくスタイルで行きたいと思っている。
いろいろと収穫の多い日だった。
| ■2004/07/24 (土) サークルのピアニストと初顔合わせ |
夕方からはS楽器アンサンブル・サークルの一環ということで紹介されたピアノの人と初顔合わせ。
音大を出て現在は普通の会社づとめだが、最近ピアノ・コンクールに入賞したりしている方で、もう一度夢に向かっていきたいという30台の男性だった。
初顔合わせでこちらが用意したフメンを初見で弾いてもらっただけなのでコンビとしての呼吸はまだわからない。
逆に「私はヴァイオリンは本当に久しぶりに再開したばかりなので不満ならそのようにはっきり言って下さい」と最初に言っておいた。
数曲弾いたあと「どうでしょう?」と聞くと「ぜひやりましょう」とのこと。
そしてとりあえずモンティの「チャールダーシュ」やショパンの「ノクターン」などを候補にして考えていくことになった。
あとコンクールに入賞したリストの「詩的で宗教的な調べ」を1曲聴かせてもらったが、前半の難解な部分をよく捉えているな、後半のメロディックな部分もよく歌っているな、と感じた。
ただ、自分はこのところ古典・バロックに心を打たれ、ヴァイオリンの愛らしい小品に心を惹かれ、内省的な室内楽に傾倒しつつあるので、アクロバティックな方向性にということであればちょっと待ってください、ということになるであろう。
貴重な時間は納得いくものをやっていきたいと思うから。
![]()
![]() Argentino アルジェンティーノ
Argentino アルジェンティーノ
島村アンサンブル倶楽部で知り合ったピアノのMちゃんと結成したデュオ・ユニット。
2004年11月のシマムラ第1回定期演奏会でデビュー。
レパートリーはヴァイオリン小品が中心。
「美しきロスマリン」、「タイスの瞑想曲」、「愛の挨拶」、「ラ・フォリア」他
2005年11月13日のシマムラ第2回定演に出演し、「ラ・フォリア」を演奏。
2006年はまず「望郷のバラード」に取り組み中。
(2006.2.6 記)
![]()
![]() KleineBach クライネバック
KleineBach クライネバック
会社の同僚のオーボエのMちゃんと結成したユニットで、2004年11月のシマムラ第1回定期演奏会でデビュー。
全くのデュオで「バッハのガヴォット」、「家路」などを演奏。
2005年は規模を拡大し、チェロのK氏、ピアノの7878おじさんを加え、バッハの「オーボエとヴァイオリンのための協奏曲」に挑戦。
2005年11月13日のシマムラ第2回定演に上記第1楽章にコレギウム・ドッペルのNさんも加わり出演。
(2006.2.6 記)
![]() Lasen String Quartet ラーセン弦楽四重奏団
Lasen String Quartet ラーセン弦楽四重奏団
島村アンサンブル倶楽部の弦楽器奏者で2004年末に結成。
2005年明けより練習を開始するが、ヴァイオリン、ヴィオラ奏者の交代などがあり、2005年10月に新メンバーが確定し、2005年11月13日のシマムラ第2回定演に出演予定。
1st♀、2nd♂、Vla♀、Vc♀という編成で、若い女性パワーにおじさんが調整役となる?絶妙の構図。
モーツァルト、ハイドンの古典を中心にレパートリーの拡張を図る予定。
(2006.2.6 記)
![]() Collegium Doppell コレギウム・ドッペル
Collegium Doppell コレギウム・ドッペル
島村アンサンブル倶楽部で知り合ったヴァイオリンのNさんと、バッハの「2つのヴァイオリンのための協奏曲」をやろうということで結成したユニット。
2005年5月15日の川崎ルフロンのシンデレラステップでピアノのTさんを加え、第1楽章を演奏。
2005年11月13日のシマムラ第2回定演ではエックレスの「ヴァイオリン・ソナタ」(ヴァイオリン・デュオ版)を演奏予定。
今後の活動としてはピアノに7878おじさん、チェロにK氏を迎え、バッハの「2つのヴァイオリンのための協奏曲」全楽章完成を目指す。
(2006.2.6 記)
![]()
 Relaxin' Duo リラクシン・デュオ
Relaxin' Duo リラクシン・デュオ
ジャズ・バンド Relaxin' のベースへらまたさんとのデュオ。
昨年は2004年11月のシマムラ第1回定期演奏会に参加し、「星影のステラ」「グリーン・ドルフィン・ストリート」を演奏。
好評?のため2005年11月13日のシマムラ第2回定演にも参加。
今回はより内省的な内容のデュオを目指し、シューマンの「異国より」と「ムーン&サンド」を演奏。
(2006.2.6 記)
![]()
![]() Romance in-Tea ロマンス・イン・ティー
Romance in-Tea ロマンス・イン・ティー
高校時代の同級生に紹介していただいたご近所に住む音大出身のピアノの方とのデュオの練習です。
リサイタルができるようになればいいな、と思って結成。
2005年はコレギウム・ドッペルにも参加していただき5月にシンデレラステップでバッハの「2つのヴァイオリンのための協奏曲」第1楽章、8月にS楽器店店内コンサートで「トロイメライ」、「ロマンス
in F」を演奏。
2006年春から再開?
(2006.2.6 記)
![]()
![]() DUO SUPREME デュオ・シュープリーム
DUO SUPREME デュオ・シュープリーム
音楽性の追求を第一に30年ぶりに再結成した高校時代以来のピアノとのユニット。
第1弾はモーツアルトの28番のソナタを取り上げる。
(2006.2.17)
![]()