その他
個人練習やその他のことをまとめました。
今日は朝練ができ、久しぶりにバッハをきちんと練習した気がする。
アルマンドはまだ足踏み状態。
もうひとつ殻を破れると次の次元に生けそうな気がするのだが。
アダージョは解析が大分まとまり、我ながら近来になく譜面に忠実に、かつ楽器を鳴らしきることが出来た。
プレリュードもカスカスだった3弦にまたがる移弦の箇所が、だいぶ粒が揃ってきた。
いずれもMDに録音しており、アルマンドは1枚目がいっぱいになり、2枚目に入った。
まだCDには落としていないが、時間が出来たらどのように日々変わっていったかを検証したい。
| ■2007/01/18 (木) ちょっと弾かないと・・・ |
昨日はヴァイオリンの練習が出来ず、今朝も起きれなかったので、仕事を昼休み返上で片付けて帰宅し、夕食後にバッハの無伴奏、ベートーヴェン&ハイドンの弦楽四重奏、ヴィヴァルディの「秋」の練習をすることができた。
一日弾かないと、なんか変な感じで、慣れるのにちょっと時間がかかる。
ほんとに微妙なことなのだけど。
本日も昨日と同じように朝練を行う。
亀のような歩みだが少しずつ昇っていこう。
朝練はバッハの3曲。
アルマンドは少しずつではあるが、スピード感と呼吸感がつかめてきた。
でも、まだまだ。
アダージョは一回分解して組み立てなおしているのでもう少しかかりそう。
プレリュードはとにかくゆっくり一つ一つの音を確実に響かせるところからやり直し。
充足された気持ちにはなる。
今日はまったくの休み。
午前中はバッハ、カルテット2曲、四季の練習。
バッハはアルマンドはかなり自信が出てきた。
アダージョはまだ袋小路。
プレリュードは、ゆっくりからさらい直している。
カルテットはハイドンはなんとかなりそう。
ベートーヴェンは1楽章の速いパッセージ、第4楽章のプレスティーシモが危うい。
四季の秋のソロは大雑把にはテンポどおりに弾けそうだが、細かい音程、譜割りはこれから、といったところ。
土曜日だが同じように朝のバッハ練習は続く。
アルマンドは繰り返しをすべて行って弾いてみた。
前半後半では、今のところ前半の方がモノになってきている感じで、後半はまだ消化されていない部分がある。
レッスンではここからが多分出発点となり、細かいアーティクレーションの分析に入っていくのだろう。
とりあえず第1段階の出口が見えてきたところである。
これに対し、アダージョは混乱している。
一度、楽器から離れて譜面と向き合おう。
といいながら、もう1曲パルティータ3番のプレリュードもメニューに入れてみた。
ヴァイオリンを習っていた昔、最後に弾いていた曲なので運指は覚えているが、移弦がうまく動かない。
これもトレーニングが必要だ。
今年は無伴奏はこの3曲を徹底的にやることにして、できれば発表の場で演奏したいものである。
今朝のバッハはアルマンドは快調、アダージョは少し馴染んできたというところ。
アルマンドもアダージョも引っかかるところ、不安な箇所は明確なので、そこの部分練習と前後のつながりをさらに練習することが必要だ。
帰宅後はカルテット(ベートーヴェンの4番)と「四季」の「秋」のソロを練習。
ヴィヴァルディも好きだが、ベートーヴェンの曲は段違いに構造が複雑だ。
音楽と向き合っている自分が自分で好きだ、と思うようになってきたこの頃である。
今日の朝のバッハは、アルマンドをインテンポで挑戦し、多少転ぶところはあったにせよ、曲らしくなってきたのでは?と勝手に自己評価。
アダージョはもう一度譜面を研究してクリアにしてから臨まなければならない。
とりあえず録音はしたが、完成には程遠い。
今朝もアルマンド、そして無伴奏ソナタ1番のアダージョもせっかく音が取れるようになったので、譜割りに注意をして練習に加えることにした。
アルマンドは昨日よりもさらに弾けるようになった気がする。
毎日の積み重ねの大切さを実感。
アダージョはまだぎこちない。
厳格なソナタの形式(ソナタ形式の意味ではなく楽曲としての)を守って弾く事の難しさを感じる。
こちらもMDを替えて毎日録ってみることにした。
朝はバッハのパルティータ2番のアルマンドを練習。
まだまだだが、少しずつ譜面の視野が広がってきた気がする。
録音して聴いてみるとまだ推進力が弱いが、音譜的な破綻はだいぶ解消されてきた。
| ■2007/01/07
(日) ヴァイオリンのお稽古 |
まったくの予定の入っていない休日。
午前中、とても時間がなく通えなくなったスポーツ・クラブに退会届を出し、図書館に寄って帰る。
午後はヴァイオリンの練習。
ベートーヴェンとハイドンの弦楽四重奏曲。
ヴィヴァルディ「四季」の「夏」のソロ。
バッハのパルティータ。
以上を練習。
パルティータは録音して聴いてみて、ダメな点を修正していくという方法にした。
最初はあまりの情けなさに涙が出たが、だんだん何がダメかがわかってきて、結局5テイク録音した頃には多少スピード感が出てきた。
午前中はまずアルマンドを5回弾く。
しかし、一度たりとも間違いなしには弾けない。
少し動きの悪いフィンガリングなどを修正。
先は長い。
次にベートーヴェンの作品18-4に取り組む。
といっても全楽章のフィンガリング、ボーイング入れで2時間くらいかかる。
やはりこれも相当難しい。
初期の作品でこれだから中期、後期はどうなるんだろうか?、と思う。
生涯バッハの無伴奏(6曲)と並んで、全部弾いてみたいのはベートヴェンのソナタ(10曲)とこの弦楽四重奏曲である。(16曲)
午後はヴァイオリンの練習をいっぱいする。
例の弦楽四重奏2曲はまずハイドンを全楽章のフィンガリング、ボーイングを入れ、速いパッセージの反復練習。
ウルヴリヒ弦楽四重奏団のCDと合わせてみるが、まだ細かいところは全然ダメ。
少しずつイン・テンポにしていこう。
VPOは「秋」のソロを担当することになったので、こちらも弾いてみる。
トゥッティーは楽だが、ソロの重音はちょっとクセ者。
こちらもフィンガリング、ボーイングをはやめに確立しよう。
あと、無伴奏パルティータのアルマンドは難しい!
バッハの音楽はヴィヴァルディのようにヴァイオリン弾きの定番のフィンガリングとは予想外の動きを要求する。
とりあえずは音を性格に取ることから始めた。
定演のあとあまり楽器を弾く時間がなく、夜久しぶりに弾いてみると弓と弦が全く噛み合わず、かすれたりキーキーという音が出る。
これは松脂の付け過ぎか、と思い弦の松脂を落とすがあまり変わらず。
仕方がないので年明けに変えようと思っていた「オブリガート」にA、D、Gを張り替える。
Eのオリーブはそのまま。
すると、非常に滑らかでいい音が出た。
前のドミナントは変えてから1ヶ月弱なのにもう寿命?
購入してから1年以上経っていたのがいけなかったのか?
とにかく、弦は取り置きは劣化されることが判明。
最短での弦の張替えとなった。
今日は休みを取って定演の曲目の練習と、来月初参加のAPAの室内楽でのベートーヴェンの弦楽四重奏曲第1番の1stパートの練習。
是非やってみたかったので自分からリクエストしたが、第1楽章、第2楽章、第3楽章のスケルツォ部分まではなんとかスメタナSQのCDに追いつけそうだが、トリオと第4楽章は速くてまだまだ譜読み段階。
他にもシューベルトの第10番のカルテット(こちらは2nd)をやるそうなので、定演が終ったら今度はカルテット練習に専念することになりそう。
クラシックを始めてから次から次へと曲がくるので、楽しくもアップアップなこの頃である。
| ■2006/11/13 (月) ヴァイオリンが心配 |
土曜の練習の帰りにヴァイオリンをケースごと地面に落としてしまい気になっていたが、確認したところ、駒が5mmほどずれていた。
ちょうど弦をエヴァ・ピラッツァからドミナントに張り替えようと思っていたので、一応元の位置に戻したら、なんんとなくくすんだように感じていた音が非常に大きくクリアになった。
ドミナントに張り替えるとさらにいい音になった。
エヴァ・ピラッツァは9月の3つの演奏会を乗り切ったのだから、3ヶ月とはいえとても酷使したのだろう。
金色のE線がブリキ色に変わっていた。
駒の問題はいいとして、なんとなく魂柱が傾いているような気がする。
これは自分では直せないので、近いうちに工房で見てもらおう。
| ■2006/07/19 (水) ヴァイオリンの毛替え@GEM |
ヴァイオリンの毛がバサバサ切れるので、ヴァイオリンの先生の紹介の代官山の工房に初めて行ってみる。
いつもお願いしているところは時間的に制約があるので、今回は試しにこちらに来てみた。
マンションの一室にあって、ピンポンをならすとお姉さんが出てきて楽器を預かる。
別室のマイスターの人のところに持って行き30分ほどで終了。
出来上がったときちらりと姿を現すが、声を交わすこともない。
次から次へ楽器が持ち込まれ、その調整で時間がないのであろう。
出来上がりはなかなかしっかりしていて、落ち着いた感じ。
松脂は何をつけたのか聞くと「ベルナルデル」だというので、しばらくそれに変えてみようかと思う。
| ■2006/06/25 (日) ヴィオラの練習状況 |
ヴィオラの方も実は9/30の弦楽合奏団の曲はヴィオラでも練習している。
コンマスをやる立場上、ヴィオラを弾くことはないと思うが、現在ヴィオラは1名しかいないので、不測の事態に備えての練習である。
新しいヴィオラになってからは弾くのも楽しく、何とか大体弾けるようになったが、ヴァイオリンのような闊達さは全くなく、やはり専門家に任せたいところだ。
ヴィオラを練習しての利点は、実際に弾いてみることで、他のパートの譜面上だけではない本当の役割がよくわかったことである。
これを頭の中で全て行う指揮者というのは本当すごいと思う。
そんなところで、やはり両方の楽器を練習するとへとへとになる。
今だからできるぜいたくかな。
| ■2006/06/23
(金) 「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 |
先月の入院中はモーツァルトに関する本を読み、まだまだ聴いたことのないいろいろな曲があることを知った。
その中にモーツァルト最晩年の小品として教会用のモテット(合唱曲)で「アヴェ・ヴェルム・コルプス」という曲があり、家にあったミサ曲のCDに附録のような形で入っていた3分の曲を聴き、すっかり魅せられてしまった。
これも弦楽合奏用にアレンジしようと思い、ピアノ譜を購入し、そこから弦楽4部に分けてFinaleを使って作成。
本物の歌の素晴らしさには敵わないが、充分これも使えるのではないかと思った。
| ■2006/06/22
(木) 「夜の女王のアリア」打ち込み |
今日もFinaleで弦楽雑誌サラサーテの巻末に載っていたモーツァルトの「魔笛」のなかの有名な「夜の女王のアリア」が弦楽四重奏要にアレンジされていたのでシコシコと打ち込んでみた。
巻きピアノのMIDI入力を使いたいのだが、また設定にいろいろ読まなければならないのでステップ入力をした。
これも完成してMIDIで鳴らすとカッコいい。
難しそうに聴こえるが、弾いてみるとそれほどではない。
早速アンサンブルのHPにアップし、メンバーに伝えた。
| ■2006/06/21 (水) オーボエとのデュオ用譜面の作成 |
FInaleという楽譜作成ソフトを使って、9月にオーボエとのデュオでやる予定の2曲、モーツァルトの「カノン・インバース」とバッハの無伴奏パルティータ3番の「ガヴォット」の譜面を作成してみた。
オーボエの音域があるので、少々ヴァイオリン部分への移動と、和音の構成を考えてMIDIで鳴らしたところ、何とかいけそうなのでこれで完成とした。
こういうソフトはどこにどういう機能があるのかを覚えるのが大変だが、覚えてからはこんなに面白いものはない。
明日は弦楽アンサンブルのアンコール曲の譜面を作ってみよう。
| ■2006/02/19
(日) 自宅練習録音のまとめ |
今朝は6時頃起きて、今まで録音した自分の演奏をCD-Rに焼く。
1月の頃はボロボロ、2月に入ってだんだんと安定してくる。
収録曲はバッハの無伴奏ソナタ第1番のアダージョとプレストが10テイクくらい、モーツァルトの「アダージョ」が7-8テイク、バッハの「ドッペル」全楽章も同じくらい、「望郷のバラード」は始めたばかりなので2テイクといったところ。
はやく自分の演奏を聴くのがイヤじゃないようになりたいと思うが、これは永遠の課題だな。
やっと休みだ。
睡眠をとってだいぶ回復したので、今日のレッスンのためのモーツァルトの28番ソナタの練習を中心に行う。
まだ譜読みの段階だが、第1楽章は大体理解できた。
これをレッスンでどのように指摘してもらえるかちょっと楽しみである。
あと今日の分の無伴奏のアダージョとプレストを録音してみる。
すこーしずつ精度が上がっているかな?
本日は朝起きれず、夜も疲労のためヴァイオリン練習はなし。
結構腰に来ているので、無理はせず早めに寝ることにする。
今日はまた3時に起きてしまった。
5時まで種々雑多な処理をしてからヴァイオリンの練習1時間半。
モーツァルトの28番ソナタは大体フィンガリング、ボーイングを決めた。
それほど難しくはないが、それから先が大変なのだ。
無伴奏はアダージョとプレストはだいぶ弾きこなせるようになってきた。
シシリアーノはまだまだ音楽全体が見えていない。
少しずつ積み上げていくか。
望郷のバラードは速いパッセージの2回目の音程がまだ怪しい。
あとはだいぶ慣れてきた。
問題はハンガリー舞曲第5番で、和音、重音、ダブル・ストップ、高域パッセージがたくさんでてくるのでまずはパターン分析をして、フィンガリングを固めたところ。
これからおいおい精度を高めていこう。
今日も朝連。1時間半。我ながらよく続くなぁ。
今日も朝連を1時間半朝連。
弓も馴染んできてだいぶ弾きやすくなってきた。
肩当はビバムジカとマッハワンをとっかえひっかえ使っているが、その日の調子によってこっちがいい、いややっぱりこっちだ、ということでなかなか難しい。
朝連を1時間半行う。
やはり毎日弾いていると、各曲の演奏レベルがあがっていくのが実感できる。
タフだが幸せな時間である。
| ■2006/02/12
(日) レッスンとドッペル練習 |
日曜なのにまた7時前には起きだし、ヴァイオリンの練習。
毛替えをした弓に松脂を塗る。
弾き始めると、カスカスだった音が、キュッキュッという感じで太い音が戻ってきた。
まだ引っ掛かりがあるがそのうちピタリと馴染んでくるであろう。
今回は半年振りの毛替え。
やっぱり3ヶ月にいっぺんは変えないとだめだなぁ。
今日はレッスンとドッペルの練習があるのでその辺りを中心に練習。
ドッペルは曖昧だった細かいフレーズもほぼ高い精度で弾けるようになった。
やはり毎日の練習にかなうものはない。
モーツァルトのアダージョは今日のレッスンで終わりにしたいので、入念に細部のチェック。
なんとかなるかな?
今日は夜カルテットの新年会+ミーティングで久々に飲み会があるので、朝連を行う。
断酒の効果は大きく、結構時間が有効に使えて、やるべきことをやり、やりたいこともできる。
このところ録音をしているのでそのうち聞きながら、CD-Rに落としておこうと思う。
聞いていく過程で少しでも進歩が見られれば嬉しいではないか。
寒暖の差が激しいこの頃だが、今日は昨日に比べ5度以上気温が高く通勤時の寒さ時からは解放されたが、オフィスはやや暑かった。
今朝は4時半起床で2時間弱の練習。
アダージョとドッペルを録音してみた。
前回よりはうまく弾けたと思うが、まだプレイバックしていない。
帰宅後は2時間ヴァイオリンの練習。
いつものメニューと、アルジェンティーノで「望郷のバラード」と並行して「ハンガリー舞曲第5番」をやることになったので、昔習っていた簡単な編曲ではない和音重音の多い版のものを採りあげようと思い初練習。
といってもほとんどフィンガリングの書き込みに時間を費やす。
最初はとても弾けそうにないかなと思われていた譜面も丹念に分析していくとなんとか光が見えてきた。あとは実践あるのみ。
今朝はやはり7時起きで、午前中にヴァイオリンの練習をする。
このところのメニューをこなし、録音をしてみる。
「アダージョ」「ドッペル」はCDに合わせオケ伴がついているのでまあまあ聞けるが、「望郷のバラード」、無伴奏はソロで弾いたところ穴だらけ。
録音は恐ろしいが、欠点が良くわかるのでまたやってみよう。
今朝は7時に次男が「起きろ!起きろ!」とうるさいので起き上がる。
当人は妻と野球の練習に出かけ、長男は2/1-3までの入試のための特別自宅学習期間も終え、学校に行った。
さて、どうするか?
10時半からヴァイオリンのレッスンに行くので、それまでまた2時間ほど練習。
モーツァルトの「アダージョ」はいい感じに仕上がってきた。
出来はレッスンのページで → レッスン 2006年2月4日
朝は起きれず。
しかし薬が効いたのか体は比較的楽。
今週も今日で終了。
依然として今年に入ってからは休まずに出社できている。
自分にとっては不本意な体調が2年ほど続いていたので自信につながる。
帰宅してから夕食後ヴァイオリンの練習をする。
1時間くらいのつもりだったが、結局2時間になってしまった。
明日のレッスンのための練習、来週のドッペルのユニット練習のための練習、デュオでの「望郷のバラード」の練習、独学でのバッハの無伴奏の練習、とだいたいメニューが固定してきたので、どうしても2時間かかってしまう。
今月末からはオケのための練習も加わるので今にも増して時間の確保が必要になってくる。
でも、それが今自分にとって大きな支えであり、楽しみであり、表現することの素晴らしさを体感できることであるので、苦にはならない。
週末も大事に時間をすごしたい。
今朝はなんと夜中3時に起きてしまい、結局寝られず4時に起き上がりヴァイオリンの練習をする。
最近のメニューをこなし、約2時間半休みなし。
でもなんか風邪っぽい・・・
今朝も5時に起き、昨日同様の練習を行う。
多分こういうことができるようになったのは、昨年末以来晩酌をやめ、飲み会以外では飲まないということを実践しているので疲れがリフレッシュされ、残らないからではないかと思っている。
絶対にやめられないと思っていたお酒だが、今は断酒によって一番やりたいことの時間が取れるほうがはるかに今の自分にとっては重要だ。
今朝は5時に起きれたので朝連を行う。
昨夜の感触を忘れないように、まず各曲の不安箇所をさらい、アダージョとドッペルはCDに合わせて弾いてみる。
昨夜よりさらに楽に弾ける気がする。
無伴奏のほうは第4楽章がまだ目覚めていないのかミス多発。
時間がないのであきらめ、第3楽章を中心に練習する。
だいぶ曲の構成がわかってきたので、スムースに流れるように最後まで弾くのが次の課題。
最後に朝弾くとすがすがしい気分になるパルティータ3番のプレリュードを弾いて朝連を終える。
今朝は起きれずあわてて会社に向かう。
開発期間に入ったので、もう一度作業項目とスケジューリングの見直し。
相変わらず4つ同時に開発するので、あっという間に1日が終わる。
帰宅後2時間ヴァイオリンの練習を行う。
ボーイング-スケールで音の調整をして、まずモーツァルトのアダージョ。
これはだいぶ慣れてきたので前回のレッスンの細かい指摘に対してもほぼ対応ができるようになってきた。
まずソロで細かい点を注意しながら全部弾き、納得の行かなかった箇所を何回か弾いて仕上げる。
それからCDに合わせて弾いてみる。
藤川真弓盤のテンポが一番しっくりいく。
そのあとスターン盤に合わせてみたが、基本的に遅すぎ、テンポの伸び縮みもあるので弾きにくい。
藤川盤をマイ・スタンダードとしてもう少し研究してみたい。
その次はバッハのドッペル。
前回録音して気になった箇所を各楽章ピックアップして弾いてから、楽章ごとに一人で通し、シェリング盤に合わせるという形で全3楽章を練習する。
第1楽章は危ない部分は伸ばす音のところだが、かすれずに弾ける精度が高くなった。
第2楽章はSul
G(G線上のみで弾く)指定の4thポジションの音程がよくないので、1stから4thにとぶ箇所を位置を確かめながら練習。これも良くなってきた。
第3楽章は難関がたくさんあるが、とりあえず弾きやすいボーイングをもう一度考え直したところ、だいぶ楽になった。
しかし、16分音符の速いパッセージはしつこく何度も弾いて指に覚えさせないといけないので、これに時間がかかった。
その甲斐あり、先回りして心の中で準備をする余裕ができてきた。
さすがに疲れ、ここで休憩。
休憩後はバッハの無伴奏ソナタ1番に取り組む。
第1楽章アダージョの音値は細かく正確に弾くのはとても難しいが、基本的に拍をとりながらその中に納まるようにするのを心がける。
このあたりからヴァイオリンの周辺になにか違った世界が感じられる。
時々そういう瞬間があるのだが、なんか次のレヴェルに入って音を出しているという感じで、楽器がふっと軽くなる。
こういうときは得てして難しい和音も簡単に取れたりする。
第4楽章プレストはまだ音符を覚えきっていない段階なので、テンポを落として曲が落ちないで最後まで続くことが今の目標だ。
今回も似ているがちょっとずつ違う音の反復に惑わされ今一歩のところで1つ音を取りそこなった。
これも毎日の練習で体で覚えていくしかない。
第2楽章シシリアーノはやっと最後まで通るようになったが、和音が続く箇所はまだまだ音程が悪い。
しかし、本当に崇高な気持ちにさせられる曲で、最後の和音が鳴るとき、とても昇華する。
今日は夜連となったが、自分の中ではとても納得した練習だった。
前日10時に寝たら4時に目が覚め、そのまま起きてCD聴いたり、整理したりで8時頃になった。
妻と次男は野球の集まり?に出かけ、長男は起きてこないので、朝食抜きでそのままヴァイオリンの練習。
また3時間ほど弾く。
これくらい時間かけると、前日のレッスン内容の復習、ドッペル・コンチェルトの分析と練習、「望郷のバラード」の分析と練習、バッハの無伴奏の分析と練習・・・といろいろなことに時間をかけられる。
そして久しぶりに「タイスの瞑想曲」を弾いてみると、1年前とは全然違う世界が見えてくる。
音楽的に成長するというのはこの年でも十分可能で、それには日々の積み重ねが重要なんだということが、目からウロコ状態で実感できた。
逆に反省はちゃんと弾けていると思ったドッペルを録音してみると、いろいろな点で甘い!
16分音符の不明瞭な部分、音量の過度な増減、リズムのかすかな乱れ・・・よくわかる。
これを糧にさらに精進したい。
はやめに事業所を出ることができたのでとなりのS楽器に久々に立ち寄る。
ヴィオラの弾き比べをさせてもらった。
自分の持っている5万円の中国製楽器はやはり重い、音が出にくい。
16万のドイツ製楽器は軽い、弾きやすいが音量が出ない。
25万のドイツ製楽器は軽い、弾きやすく、音量も出る。音色もいい。
ということで相応の値段がついているのだな、と思った。
S楽器のI氏といろいろ喋るが、アンサンブル倶楽部も100名を越える大きな組織になってきたので、いろいろな制約が出てくることを聞く。
具体例を出して申し訳ないが、演奏会のDVD配布に関する著作権、今年の演奏会の人数制限(3名以上でないとダメ)など。
もちろん会社として行っているのだから利潤追求、コスト削減というのはわかる。
担当の方の苦渋といったものもわかる。
結局ある程度までいけば、それ以上の自分のやりたいことは自分でやっていくしかないのである。
そしてさらに上を目指すなら実績を作って、またそうした会社という組織と歩み寄って大きなものにしていくというのが進むべきやり方なのであろう。
会社のオーケストラにしても、組織というものを熟知したオーケストラ企業家の人たちが運営しているのでまさにプロのワザである。
そこまでは無理にしても小さいものから大きくしていきたいという願望はあるので、自身で運営できる団体をクラッシックでも作ってみたいものだ。
ジャズに、オケに、室内楽に、ソロに・・・ととにかく今は欲張りたい。
帰ってから夜またヴァイオリンを2時間ほど練習。
1週間の疲れが取れる。
今日は午後会社のキックオフ・ミーティングがあり、修了式で歌う「贈る言葉」をレクチャー・ホールという教室で披露。
ピアノは手配できなかったので、PCでのMIDI再生。
仕方がないので歌う側で参加。
ぶっつけ本番は怖いのでロール・ピアノでも買って会社での練習で使おうかな、なんて思っている。
夜はヴァイオリンの練習を行う。
毎日弾いていると段々と楽器が鳴ってくるのがわかる。
難しい無伴奏も少しずつではあるが、音符は覚え、流れの方に意識を向けることができるようになってきた。
こうした積み重ねが肝要である。
| ■2006/01/25 (水) ヴァイオリンの練習 |
今日は朝は起きれなかったが、仕事が定時で上がれたので、帰宅・食事後にまた2時間ほど練習をした。
最初はモーツァルトのアダージョだが、大分曲想が理解できてきたので弾いていて楽しくなってきた。
もう少し細かい部分を仕上げて体の一部分のようになるように弾きたい。
会社の行き帰りの電車でドッペル・コンチェルトを聴きながらスコアにいろいろと書き込み、全体像というものを恥ずかしながらようやく捉えられてきたようだ。
それに基づき、自分の2ndソロのみならず1stソロの楽譜も弾いてみて、いろいろと2台のヴァイオリンの織り成す彩のようなものを実感する。
あと未消化だったボーイング数箇所を確定し、何度も練習をしてなんとか身体で覚えることができた。
次回の練習が楽しみである。
最後はバッハの無伴奏だが、第1楽章は弾きこんできたのでだいぶこなれてきた。
ただ和音の音程に不安な箇所があるので、きちんと整理していきたい。
第4楽章はまだまだ音符を指に覚えこませている段階で表現までは至っていないが、今後はどうアクセントをつけて表情を持たせていくかが鍵である気がする。
第3楽章は運指の分析は終ったが、最初の2段を繰り返し練習している。
これも和音が難しく、少しずつ覚えていくしかない。
しかし、なんか生活にリズムが出てきていい感じだ。
| ■2006/01/24 (火) 贈る言葉-Vn練習 |
午前中は朝一番で定例ミーティング。
そのあと新入社員修了式でのイベントの練習。
インストラクター陣で合唱をやることになり、なぜかピアノ伴奏者に指名されてしまった。
オケもその式典には出るのでオケ伴に変えようよ、と言っているが・・・
曲は「贈る言葉」なのでまあ何とかなるとは思うが、多分ピアノ伴奏は当日直前の1回だけになるのでやや不安。
食事後たっぷり時間があるので、久しぶりに8時から10時までヴァイオリンの練習。
ただ弾くのではなく、譜面を読む、ということを中心に行い、かなりいろいろなことを書き入れる。
・モーツァルトのアダージョ(今週末のレッスンに向けて)
・バッハのドッペル(2月のコレギウムドッペルの練習に向けて)
・バッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番〜第1・3・4楽章(今年の独学課題曲)
弾くことの前の読むことの大切さを再確認した。
またまた4時起き練習。
4日続いた。
今多少悩んでいるのは肩当のことで、今までのものが軋みを感じるので、MachONEという使わないで取ってあったものに変えてみたが、音はいいのだが胴体を固定するゴムの部分が滑りやすく、弾いているうちに自分のちょうどいい位置からずれていまう。
今度調整の時に解決策を聞いてみようと思う。
仕事帰りに買ったレコード芸術2月号は「リーダーズ・チョイス」の特集。
昨年末に送ったコメントが2つ採用されていた。
でも「飯守」先生が「飯森」になっていたのは私のせいではありません。
ちゃんと「飯守」と打って送った内容をプリントしてあるので、クレームは音友社へ。
| ■2006/01/19 (木) 英語プレゼンテーション |
今朝も4時起きができた。
例によって練習メニューを消化。
今日もまた、4時起で出社前に2時間弱練習した。
明日もレビュー資料のまとめ、ミーティング、海の向こうのコースへの参画(Web)とフルフル。
今度の日曜は寝ていよう。
今朝4時起きで朝練をした。
今週は以下のメニューでやっていきたい。
・スケール(E-Dur;1-3
Octaves)
・モーツァルトのアダージョ(レッスン課題)
・コレルリのクリスマス協奏曲(今週末のコンサート用)
・バッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ(3&4楽章の分析)
大体以上で1時間半かな。
昨年末のS高校管弦楽団創始者の池辺晋一郎先生の会で30年ぶりに再会した先輩と年が明けたら飲もう、と約した「巨匠の会」、と言っても自分たちが巨匠なのではなく、クラシックの巨匠たちの話で盛り上がるという主旨。
恒例の7878おじさんも加わり、K大出身のS先輩の行き着けのTホテル地下のM倶楽部へ連れて行ってもらう。
入り口の分厚い木製の扉に「会員制」の文字がある。
なんかエグゼクティブな気分になり、飲み始める。
先輩は昔と変わっておらず、次々にマニアックなクラシックの主に指揮者の話で盛り上がっていく。
またオケでもやりましょうよ、という話も出たが、状況が許せば出来るうちにやっておきたいなと思った。
先輩ご推薦のフリッツ・ブッシュ、エーリッヒ・クライバーでも聴いてみるか。
定例会にしようということで再会を約して別れた。
とても溜飲を下げた一夜だった。
■2005/12/25 (日) クリスマス・レッスン
世はクリスマス。
昨日休養のおかげで大分楽になる。
ちょこちょことしか触っていなかったヴァイオリンを久々に3時間ほど練習。
E
Durのスケールをやり、今度レッスンでやろうかどうか迷っているモーツァルトの「アダージョ」の譜面を丹念に眺め、少しずつ弾いてみる。
最初はつかみ所のない曲だと思っていたが、だんだんと面白くなってくる。
これは2ヶ月ほどかければ表現を含めて完成できるかもしれない。
次に「ラ・フォリア」を先月のコンサート以来初めて弾いてみる。
重音、対旋律がやはり劣化している。
毎日弾かないとダメだなぁと思う。
あと、前に自己流で弾いていた、フィオッコの「アレグロ」、ヴィヴァルディのA-mollコンチェルトなどを久々に弾く。
前のような余裕のなさがなくなったと思えるのはそれだけ進歩した?からだと思いたいところだ。
| ■2005/12/04
(日) 池辺さんを囲む会@グランド・パレス |
今日は午後から新宿高校の管弦学部創設者「池辺晋一郎さんを囲む会」があり、まず中目黒で氏の作曲した78年のNHK大河ドラマ「黄金の日日」をOBOGが集まり一日限りのイケベ・キネン・オーケストラとして数回通し練習。
2-30年ぶりに会う顔が懐かしい。
コンマスは12代上のN響の方。
予定の時間より早くまとまり、会場のお茶の水に7878氏の車で移動。
彼は今回シンセサイザー担当でマリンバなどの打楽器系を弾く。
機材が多くて大変だ。
 (開演直前)
(開演直前)
高校在学当時お世話になった3年上の先輩たちも同乗し、いろいろと昔話に花が咲く。
会場のグランド・パレスでは170名ほど新宿高校の管弦学部・音楽部が集まり盛況。
イベントの最初がゲネプロ入り池辺さん指揮による「黄金の日日」。
即席にしては結構まとまっていて、池辺さん曰く「黄金の日日ではなく黄金の時間だ!」とおっしゃってくださった。
歓談では当時の音楽の先生で管弦学部の顧問をやっておられた野村光男先生(チェンバロ製作の第一人者として有名)や、諸先輩・後輩といろいろ話が出来、2次会もそのままなだれ込み、池辺さんともツーショットで写真をとってもらった。
若き頃の仲間に会うと活力が湧いてくる。
何人かと再会を約して散会となった。
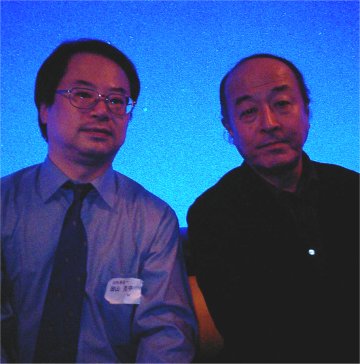 池辺さんと(2次会で)
池辺さんと(2次会で)
| ■2005/10/20
(木) ポジティブ・モード |
自分の練習はエックレス、バッハ、そして第九の第1楽章。
第九はやはり各所に出てくる6連符の数え方が難しい。
もう一度スコアを確認する必要がある。
その前に何とかやり遂げようモードの維持がまず大切。
お疲れ→ネガティブを省力→ポジティブにしたい。
デジタル・ビデオに撮ってあった去年のテープをDVDに保存しようと思い、少し観てみた。
数十年ぶりのK先生とのレッスンや、今の先生との初レッスン、次男の前の先生の頃の自宅練習の風景など。
自分も子供も弾き方が雑。
音符を弾いてますよ、というだけで音楽になっていない。
右手の細心の注意、いやその前の弾く前の心構え、準備が全然なっていない。
一年でいろいろなことがわかり、変わり、前に進んでいることが認識できた。
夜はエックレス、ラフォリアの練習でをする。
電車の中でエックレスを暗譜しようと思って譜面を見てイメージをつかんだつもりでいたが、いざ弾いてみるとまだ全然できていない。
具体的に段階をひとつ上がるというのは簡単にはいかないものだ。
久々の集中的にヴァイオリン練習。
エックレス、ラフォリア、バッハのコンチェルト、そして今晩練習のある弦楽四重奏2曲。
個々までノン・ストップで2時間。
ただ弾き流すのではなく、出来ない箇所、自信のない箇所を取り上げ細部の練習。
最後に全体の中でそれがうまく自然に流れるかどうか練習をしてみた。
エックレスは全楽章共ようやく曲がつかめてきて意に沿った表現がかなりできるようになった。
ラフォリアは重音部分、カデンツァが難所で、まだまだ改善の要あり、ただし音自体は幅広さが出てきたような気がする。ガット弦の効力だろうか?
バッハは明日ユニット練習だが、まだ16分音符の細々としたところを完全に覚えていないので、音符の確実な把握を行う。
表現に関しては明日の練習の中で決めていこうと思う。
弦楽四重奏はハイドンのセレナーデは置いておいて、モーツァルトのディヴェルティメントに集中する。
CDも聴きなおし、スコアを見ながら本日の練習のポイントになりそうな部分をチェック。
このユニットでは2nd担当だが、1st同様細かく動くフレーズがたくさん出てくるので、音取りを確実にする。
小休憩のあと、オケの曲の練習。
CDに合わせ、第九の第1楽章、マイスタージンガー前奏曲を弾く。
大体のところ把握できてきた。
どこにいるか迷うことはなくなった.
第2楽章、第4楽章は弾ききれていないパッセージを取り出して練習。
現段階では第4楽章の後半部分の細かい動きをあとどのレベルまで克服できるか、だな。
こちらは1時間ほどで終了。
体力的に限界になり昼食後はゴロゴロして過ごす。
今日で週末。
でもなんか長い一週間だった。
月曜の祝日出勤と、恩師のお通夜で気が抜けたのかもしれない。
寝る前に30分ほど楽器を触る。
でも明日久々に練習時間が取れそうなので、まあいいや、ということで就寝。
| ■2005/10/13
(木) 疲労度ピークの木曜日 |
今日は一日仕事の日。
さすがに帰りの電車ではぐったり。
帰宅後食事してちょっとピアノを弾いてから就寝。
今日はヴァイオリンには触らず。
寝ることがやはり体力回復には一番。
今日は調子が今ひとつ。
夕食後に少しエックレスとラフォリアを練習するが、疲れていて音程がよくなく断念。
やはり時間を作るのは難しい。
さすがに週末、疲れがどっときている感じ。
それでも朝練1時間ほど行う。
スケールで指慣らしのあと、エックレスとバッハ、ラ・フォリアを抜粋してみておく。
出社し、CD-ROMの研修資料第2版のチェックを行い、エラー項目を洗い出す。
結局一日仕事となったが定時に帰宅。
夜は再度ヴァイオリンの練習で、数ヶ月弾いていなかった弦楽四重奏の曲をおさらい。
明日明後日で4ユニットの練習があるが、一番不安なのが明日の弦楽四重奏である。
ヴィオラ交代後の初練習でどんな感じになるのだろうか。
明日からの3連休、最終日の午前は出社だし、またあっという間に終りそう。
オケ練がないのがちょっと救い。
本日は朝練できず。
帰宅後エックレスとラ・フォリアのダメな部分をピックアップして練習。
肉体的に疲れているのか、ガット弦に慣れていないのか、はたまた難しい部分ばかり集中的にやっているからなのか、左手の疲労が激しい。
土曜の練習時に楽器店でもう一度調整してもらおう。
今朝は起きれたので朝練をする。
Oliveの弦はまだまだ安定しない。
チューニングをこまめにしつつ、バッハの「ObとVnのための協奏曲」、エックレスのソナタを弾く。
バッハはまだ曲を覚えきれておらずポカをしてしまう。
バロック系は似たような指使いが多いので、覚えてしまった方が速いのだがすぐに忘れてしまうのは歳のせい?それとも朝練で目が覚めていない?
それはさておきエックレスは第2楽章の出だしの和音が少しきれいに鳴るようになった。これは弦を変えたからかもしれない。
しかし全4楽章を集中するとそれだけで結構疲れる。
そのあとラ・フォリアの重音部分を繰り返し練習。
前回の合わせの録音を聴いてみて音程の悪さに愕然!
弓の使い方とあいまってこれはきちんと確かめながらやり直さねばと思った次第。
これも左手にかなり負荷がかかる。
室内楽系のあとはオケの練習。
第九の第4楽章を弾いてみる。
聞こえないから弾けなくてもいいということにはならないので、やはりちゃんと弾きたい。
四苦八苦しながら永遠と続くフーガの練習。
リズム・パターンが変わるところの理解がまだまだ。
毎日弾いて体で覚えこもう。
とやっているうちにタイムアップ。
会社から帰宅後はもう弾く元気はなく明日またがんばろう!ということで一日終わり。
| ■2005/10/04 (火)仕事に行って音楽して |
練習はオケの曲と、室内楽の曲とたくさんあるが、第九は第4楽章以外は大体のところ弾けるようになった。
ワーグナーも同様。
ただし細かいところはまだまだこれから。
室内楽はエックレスのソナタは譜面は何とか弾けるようになったが、表現の点がまだ追いつかない。
ラ・フォリアは仕上がりとしては一番進んでいるが、なにせ難曲なので日々の精進が必要。
バッハのコンチェルトはまだ大雑把にしか捉えていない。
細かいところはこれからである。
| ■2005/05/07 (土) 子供達と音楽の一日 |
GWもあと2日だが、今日は昼前に次男をヴァイオリンの先生のところにレッスンに連れて行く。
前の先生が諸事情で続けられそうになくなったため、楽器も変わり、小学生にもなったということでおけいこからレッスンへの転換をさせようと思った。
本人を説得するのが一番困難だと思ったが、言ってみると「いいよ。ボクあの先生も好きだから」とあっけなくOK。
先生に確認したところ「喜んでお引き受けします」とのことなので早速自分のレッスンの日に次男を連れて行く。
前回は体験レッスンみたいな感じだったが、今回は立ち方、構え方、弓の持ち方、1stポジションの押さえ方、基本からやり直してくれる。
次男も緊張の面持ちで、得意のおふざけも出ず少々疲れた表情で終了。
来月から本格的に週1回での練習をお願いすることにした。
昼過ぎに帰って、今度は学校から帰ってきった長男を連れてリラクシンの練習へ向かう。
長男はバンドを作ってドラム担当になったので、リラクシンのドラマーTくんに聞いてみたいことがあるのだという。
スタジオに着くと「ここ何かみたことある」。
10年位前今の次男より小さい頃練習につれてきたことがあり、それを覚えていたわけだ。
ともあれ練習は5/15用の「アルマンドのルンバ」を徹底練習。
今回はヴァイオリン用のマイクも持っていったのでバランスが良くなる。
5−6テイクやってなんとかテンポ、進行が定着する。
休憩中ドラム講座が始まり、長男は8ビートの基本を熱心に教わる。
休憩後せっかくだから叩いてみたら、ということで尻込みする長男をドラムの椅子に座らせ初ドラム演奏。
曲はハンコックの「カンタロープ・アイランド」。
ともあれ最後まで持ちめでたく初演奏終了!
そのあとカルテットで通常レパートリーを演奏し、最後にもう1回「アルマンド」で締める。
長男に感想を聞くと「緊張で死にそうになった」とのこと。
そうやってだんだんうまくなっていくのだよ。
今日は図らずも子供たちの音楽同行デーになった。
でも音楽のある家は楽しいはず。
どちらもこれからに期待。
朝起きると9時。
今日は家にこもってヴァイオリンの練習。
まずは5/15シンデレラステップでの「アルマンドのルンバ」のコピーをする。
最近入手したFinaleという譜面ソフトで入力し音を確かめながら作成。
コピーよりもソフト操作で時間を食い、完成に3時間もかかってしまった!
CDに併せて弾いてみるがテンポが速すぎて歯が立たない。
メトロノームでテンポを落として音をひとつずつ確認する。
段々とテンポを上げていき、なんとかCDに合わせられるようになった。
この時点で午後2時を回っている。
朝から何も食べていないことに気づき、パンとバナナと紅茶を軽く腹に入れる。
それからオケの曲の練習。
タンホイザー序曲を音符を確認しながらやってみる。
これは難しい。
中盤以降の16分音符の羅列は指揮者がいないと頭がずれていってしまう。
とりあえずオケ連のときにがんばろう。
| ■2005/04/24
(日) 次男の新しいヴァイオリン購入 |
久々に家族でお出かけ。
川崎のつばめグリルでランチ。
休日はウィークデイのランチはないが、自慢のハンバーグ料理、トマトのサラダなどなかなかおいしい。
そのあとシマムラ楽器で次男のヴァイオリンをみる。
1/4と1/2を数本ずつ用意していてくれた。
本人はやはり1/8から1/2はかなり大きくなった感じで「弾きにくい」とのこと。
1/4はあまり見た目も変わらず「弾きやすい」。
しかし、明らかに1/4は子供のヴァイオリンの音で、1/2は大人のヴァイオリンの音で、音量もかなりちがう。
弾きやすい1/4を頑として譲らないので、いったん後日またということで店を出る。
駅に向かう途中「でもあの1/2のレッド・ヴァイオリンはいい音だよね。次に行ったときはなくなってるかも」というと態度を急変し、「あのレッド・ヴァイオリンにする!」。
急遽引き返し1/2を購入。
家に帰り弾き始めると、やはり全然音の鳴りが違い、本人も「ぜんぜん弾きにくくないや」と調子がいい。
ひとまず買い替えは終了。
ま、よかったかな。
| ■2005/04/10 (日) 久々にヴァイオリン・レッスン |
今日は久々にヴァイオリンのレッスンに行った。
今までの課題曲は置いておいて、オケに入ったことを言ってあったのでブラ4のパートをみてくれた。
先生も学生時代オケでこの曲は弾いたことがあるそうで、熱のこもった指導で気がついたら1時間のレッスンが2時間近くなってしまった。
おまけに最近聴きに行ったN響のブラ4がとてもよく、放送されたのを録画したから参考に、とビデオまで貸してくれた。
レッスンが終る時に、でもこの定演の2週間前にバッハのドッペルを人前で演奏する、と言ったら「えー!じゃあそっちの方が先じゃないの」ということで、次の土曜もレッスンに行くことになった。
熱心にみてくれるのはありがたいことだ。
たしかにこの先生についてから単に音を弾くから、いかに音楽にするかということをいろいろと学んだ。
今後ともいろいろな音楽的な面を教わっていこう。
帰ってから次男のレッスンを見る。
9月の発表会の曲はバッハのガヴォットに決まったそうだが、ニ長調の音階練習は一度もやったことがない。
なんと脈絡のない、と思いながら教本のスケールのページを見つけて指のポジションを説明する。
最初はクセでハ長調やイ長調の指使いになるが、#の位置を楽譜上で確認し、こことここが#だから2と3の指がくっつく、という説明をしたら「なるほど!」と理解し弾けるようになった。
そろそろなんとなくではなく論理的に教えても理解できるようになってきたようだ。
とりあえず音階とガヴォットの最初の繰り返しまでを把握して今日は終了。
そのあと最近弾けなかった曲を2時間くらい練習。
最後にメンデルスゾーンのコンチェルトの第1&3楽章を弾いてみる。
すごく久々なのにさすがに前より音程は取れるようになったし、指も回るようになった、と自画自賛しこちらも終了。
| ■2005/04/06 (水) 休暇でひさびさ弾いた気がした |
夕方スプリング・ソナタ、ロマンス、カンタービレを練習。
少し細かく見ていくといろいろなことが書いてある。
ベートーヴェンらしさのスフォルツァンドを意識して弾く。
パガニーニは音色の美しさを意識する。
久しぶりに練習した気がした。
今日はヴァイオリンの練習も出来なかったが、行き帰りの電車でCDを聴きながらパート譜を読んでみた。
ヴァイオリンの先生が言っていたように譜面を読むというのも大事な練習なんだなぁ、と感じた。
それに指揮者によってどの部分をどこまで譜面の指示どおりにやっているかなどの解釈もよくわかる。
例えばタンホイザー序曲では、カラヤンの演奏はとても各パートが明瞭に聞こえるので非常に参考になる。
マタチッチのものは音は塊で聞こえる部分が多いが、ダイナミックスなど譜面に書いてある強弱のつけ方がよくわかる。
といった具合。
そうこうして聞いているうちに今日の全体の構成がつかめてきた。
イメージ・トレーニングの効用というべきかな。
| ■2005/03/29
(火) 誕生日・・・でした |
早朝4時に起き上がり練習をする。
さすがにボーッとした感じだが、時間がないので仕方がない。
ブラームスの3楽章、タンホイザーに取り組むもまだスコアの理解が出来ていないので場所を見失うことがある。
週末は今回の指揮者、円光寺氏の初練習なのでまがりなりにもパート譜の中身の理解はしておきたい。
考えてみれば今日は自分の誕生日だった。
それでも朝練と夜練を行う。
ロマンス、スプリング・ソナタ、ラ・フォリア、プレリュードなどをこなす。
ところがE線の響きが悪いので巻きなおそうと思って外したら、なんと切れてしまった!
変えたばかりの
TITANIUM
が!
ストックのあったOliveのゴールドに張り替える。
このほうが全然鳴るなァ。
この方がいいやと無理に納得。しかしなんか悔しい。
なんかツイてない日だ。
会社のオケに参加することになったので、ブラ4のCDをかけて終楽章をスコアと見比べると思っていた譜割りと全く違う。
これはたいへんな曲だなぁ、と思ってしまった。
タンホイザー序曲も難しい。
とりあえず土曜に2ndで参加してみることになった。
| ■2005/03/02
(水) 会社のオーケストラ |
昨晩は早寝したため今朝は早起きでき、リフレッシュした感覚で朝練をする。
ロマンスとスプリング・ソナタはだいぶわかってきた気がする。
バッハのプレリュードも昨晩のガタガタぶりから比べるとひとつひとつの音がよく聞き分けられる。
やはり疲れたときやっても意味ないのだな。
会社のオーケストラに興味を持ち、取りまとめている人にメールで聞いてみる。
年2回定演があり、プロの指揮者に振ってもらうというスタイルで運営している。
ちゃんとしたシンフォニー・ホールでフル・オーケストラでやるので参加したくなってきた。
次回は好きなブラームスの4番交響曲とタンホイザー序曲とのことなので少なくとも聴きに行ってみよう。
今日はヴァイオリンのレッスンの日だったが、先生が風邪でダウンして中止。
このところどちらかが体調が悪くなり、結局2月は1度もレッスンしないまま終りそうだ。
寒いので午前中、車で図書館に行く以外は家から出ないことにする。
後は次男のレッスンを見る。
ト長調の音程も安定し、課題曲の「メヌエット」もほぼ覚えた。
今日はフォルテに向かうクレッシェンドの表現を教える。
弓をこうして大きく使っていくんだ、と弾いてみると
「なんか、とてもうれしい!って言っているみたいだね」
と次男が言う。
やらせてみるとまだ自然にはいかないが、意味は理解したみたいだ。
次回でこの曲もパスするだろう。
そのあとは自分の練習をする。
いつものと久々にメンデルスゾーンのコンチェルトを弾く。
テンポを大分落としてやってみるとどこが弾けて、どこがあやふやかがわかる。
この曲も毎日弾きたいが時間がないなぁ。
今日は朝練時に弦を張り替える。
tomastik vision TITANIUM
というDominantで有名なtomastik社の最新の弦。
今までは去年の10月に張り替えたtomastik vision
を使っていたが、これも悪くなかった。
セットで定価\5,000(イシバシ楽器のセールで\3,500で購入)くらいなのでリーズナブル。
今回のtomastik
vision TITANIUM
はセット定価\9,000をネット価格\6,000で購入。
E線がTITANIUMという感じの?渋い色をしており、どんな音が出るのかと期待に胸が膨らむ。
結果として、非常に鳴りのいい弦である。
特にE、A線がデッドな部屋でも残響感が出ており、ホールで鳴らしたらどうなるのだろうかと思えるほど。
これで弾き込むうちにとろけるような艶が出てくればかなりのもの。
帰宅後は張り替えた弦が気になり、また楽器を鳴らす。
また弦が安定せず、1曲ごとにチューニングが必要だが、バッハも明確に音が出るので嬉しい。
もうしばらく様子を見てみたい。
練習は朝練のみ。
ベートーヴェン、バッハ。
新しい弦(tomastik
vision TITANIUM)が通販で届いたので明日張り替えてみよう。
評判の弦だけに楽しみである。
朝練でベトーヴェン、バッハ、夜練でコレルリ、バッハと今日も2度練習。
夜練習すると子供たちと接する時間がほとんどなくなってしまう。
しかし、なんか今右手のボーイングの妙味が体得できそうな感じがしてつい弾いてしまう。
時間が欲しいなぁ。
午後は昼寝をし、夕方次男のレッスンを見る。
課題曲は譜面づらは覚えたので、クレッシェンド、ピアノ、フォルテなど表情記号を中心に行う。
できないとフテくされるが、ともかく最後までやらせる。
曲想全体がつかめてきたようなので終了。
そのあと自分の練習をする。
昨日やらなかった分含め2時間くらい弾いてしまった。
前半はスケール、練習曲、ザイツのコンチェルト、アヴェ・マリアと来週のレッスン用の練習。
ザイツのコンチェルトは3楽章の構成で部分部分は課題があるが全体的なバランスはわかってきた。
アヴェ・マリアは音符そのものは簡単だがなかなか納得のいく表現にはいかない。
さらに練習要。
後半はラフォリア、ロマンス、スプリング・ソナタ。
ラフォリアは重音部分とカデンツァがまだ十分に弾きこなせていない。
テーマ部分の表情はだいぶついてきたように思う。
ロマンスは半音階などの細かい部分があいまい。
スプリング・ソナタはまだまだ音符の把握が不十分で、16部音符の速いパッセージの臨時記号を見落としがち。
ということで課題を分析し、さらに弾き込むしかない。
最後はバッハの無伴奏で、プレリュードは5箇所の難関を少しずつ改善中、アダージョは音符の長さの妥当性を見直し中、プレストは延々と続く八分音符の連なりを落ちないように覚えること、などが課題。
これに今日弾けなかったものとして、アンサンブルでやっているバッハのドッペル・コンチェルト、カルテットのモーツァルト、ハイドンもあるのでやはりちょっと欲張りすぎかな?
夜は少しピアノを弾く。
バッハのインヴェンションと明日のリラクシンの練習のためのおさらい。
そんなことでまたあっという間の休日であった。
| ■2005/02/17
(木) 朝も夜も A Morning &
Night |
今朝は起きれた。
今日もスケール練習、カイザー練習曲のあとラフォリア、バッハ無伴奏アダージョ、プレリュード。
プレリュードは再開後は全く歯が立たなかったが、やっとこの4ページに渡る曲のツボがわかりかけてきた。
ただしホ長調で基本的に開放弦が2弦使えないので音程がかなり難しい。
それと3弦に渡るアルペジオの連続がなかなかきびしい。
しかしこの曲は何ともいえぬ爽快感があり、1日の始まりのプレリュード(前奏曲)としては活力が湧いてくる。
難易度の高い練習曲としての役割も果たしてくれるので毎日の練習で欠かせない曲である。
夜はまたヴァイオリンの練習をする。
昨日から始めたベートーヴェンの「ロマンス ヘ長調」と「スプリング・ソナタ」を中心に弾く。
新しいピアノのTさんとはまだメールでのやり取りしかしていないが、「聴くのとやるのでは大違いでスプリング・ソナタむつかしい」とのこと。
たしかに細かいところをきちんと弾き、楽譜の表情記号を表現しようとするととても難しい。
しかし高校時代の懐かしさも蘇ってくる。
ぜひとも再演したいものである。
おまけに寝る前にピアノでインヴェンションの2声の1-4番を弾いてみる。
とてもよくできている曲だなぁ。
自分には難しいがやりがいはある。
今朝は起きれず、朝練なしで会社へ行く。
帰ってから夜練習をする。
無理せず、譜読み程度にする。
年末の高校の同窓会以来懇意にしていただいているAさんから偶然近所に住むピアニストの方を紹介していただいた。
最初の合わせの候補曲であるベートーヴェンの「ロマンス ヘ長調」と「スプリング・ソナタ」をちょっと弾いてみる。
ロマンスは再開後も何回か弾いているのでなんとかなりそうだが、スプリングは高校時代以来なので、少し練習が必要である。
また新しい励みができバランスよく生活のリズムに乗れていきそうなのがうれしい。
夜寝る前にピアノでバッハのインヴェンションを弾く。
弾くというよりポロンポロンと鳴らす程度だが、一日の疲れが取れるようだ。
ピアノは座ってキーを叩けば鳴る。
ヴァイオリンのような表現力うんぬんまでいかないけどやはり慣れた楽器なので変な気負いがなく接することができる。
気が向いた時に2声の15曲の方だけ少しずつやってみようかな。
このところ早起きが快調である。
今日も朝練ができた。
例によってスケール練習、カイザー練習曲のあとラフォリア、バッハ無伴奏アダージョ、プレリュード、プレスト。右手の難しさを改めて感じる。
力を抜くというのはできそうでできない。
無意識にできている場合もある。
気負ってはいけない。
純真に音楽を創り上げなければどこかに余分な力が加わる。
解脱した境地がどこかに必要なのかもしれない。
今日は久々に朝も早く起きることができた。
出社までの時間を気にしつつ6-7時までヴァイオリンの朝練をした。
スケール練習、カイザー練習曲でウォーミングアップして、ラフォリア、バッハ無伴奏アダージョ、プレリュードをやって1時間弱。
やはり朝はバロック音楽が身が引き締まる感じで好きだ。
夕方になり次男のヴァイオリンのレッスンをみる。
モーツァルトの「5月のうた」というのが新課題曲で、なかなか難しい。
最初にト長調のスケールと分散和音で調整の確認。
久々に一緒にヴァイオリンで合奏してみるが、思ったより音程がしっかりしてきている。
そのあとピアノで音を取りながら少しずつ曲を覚えていく。
最後はピアノ伴奏でとにかく全曲弾けるようになった。(といっても32小節)
ヴァイオリン終了後、最近始めた調音(ピアノで叩いた音を楽譜に書く)は、2和音(ドとラとか)はほとんど聞いた瞬間にわかるようだ。
即答で「ドとラだな」とか言う。
ただ書く方がまだダメで、ドは五線紙の下に一本線を引いてその上に書くということなどがたどたどしい。
でも絶対音感がありそうなのは頼もしい。
| ■2005/02/03
(木) ヴァイオリンの練習 |
夕食後は30分ほどヴァイオリンの練習。
最近は朝が起きられず、1日弾かなかっただけでとても久しぶりの気がする。
スケール、カイザー(最近練習曲の重要性を再認識しまた練習し始めた)、ザイツのコンチェルト、アヴェ・マリア、バッハ無伴奏アダージョで終わり。
楽器を弾くことの喜びを噛み締める。
あとピアノも少し練習したいなぁ。
| ■2005/02/01
(火) ヴァイオリンの練習 |
体調もなんとなく戻ってきたようだ。
今日はヴァイオリンの練習を夜行う。
このところまったく禁酒状態なので、多分冴え渡った?頭で練習に臨めているかな?
バッハの無伴奏パルティータのプレリュードとソナタのアダージョの力の抜き方が急に解りかけた気がした。
日曜にFMで生中継でアダージョの演奏を聴いて、ああ、こんなに楽に弾くんだ、と思ったのがヒントになった。
解ると、なぜこんなことが解らなかったのだろう、ということになるが何事もそうやって少しずつなのだな、と感じた次第。
夕方ヴァイオリンの弦を替えてみる。
トマステイックス社の”Vision”という新しいナイロン弦だが、さすがに買った当初からのインフィールド・レッドはくたびれていたのが、鳴りが全然よくなり、腕が悪いからかと思っていた音のかすれも大幅に軽減した。
あとは弓の毛の張替えをどのタイミングで行うかだな。
安い弓より弾きにくいと感じたらその時なのかもしれない。
でも弦替えで音がよくなり少し気分が晴れた。
| ■2004/07/11 (日) 新盆でのヴァイオリン演奏 |
今日は新盆であった。
はやいもので父が亡くなってあとひと月ちょっとで1年が経つ。
新盆の儀は葬儀以来お願いしている八王子のお寺さんの副住職の方が読経をされ、親戚も10名ほど集まり滞りなく終了した。
昼時だったので会食をして一応解散。
兄弟夫婦2組、おばがひとり残り、兄嫁のリクエストでヴァイオリンの演奏をソロで行った。
前から聴きたいといっていた「タイスの瞑想曲」のほか「美しきロスマリン」「愛の悲しみ」「トロイメライ」の4曲を演奏。
技術的にはまだまだだが、いいカッコをみせるのではなく音楽を聴いていただくという自分の中での心理が多少は伝わったのではないかと思う。
人前で弾くというのは難しいことだが、少しずつコミュニケーションが取れるようにこれからもいろいろな人に聴いてもらいたいと思っている。
| ■2004/07/03 (土) 友人のピアノとの合奏 |
30年近くぶりに高校時代のクラスメートを家に呼び、ヴァイオリンとピアノの二重奏の練習。
彼は営業で忙しく、なかなか練習時間が取れなかったようだが初見に近い状態でもさすが幼少の頃より続けているピアノの腕は確かである。
今日は昨夜と違う難しさ、人とあわせることの難しさを十分に味わった。
ジャズでの呼吸とは全く違うクラッシック、自由なようでありながら厳格なビート感覚に支配されるジャズとは違い、譜面というものが前提となりその中でどのような自由を獲得していくのかというのが正反対なように違う。
とはいえまずは呼吸合わせから入る。
杓子定規に1拍ずつを意識しながら弾いていくので音程や音色が時としておろそかになる。
すべてをバランスよくやっていくことはまだまだ時間がかかる。
今回意外と難しかったのがクライスラーの「愛の悲しみ」で、3拍子のウィーンのワルツのなかで2拍4拍のひっかけフレーズは数えないと惑わされる。
やってみるといろいろなことがわかるものである。
とりあえず予定6曲中5曲をなんとかこなし、次回につなげることにする。
終了後は家の近くの昔からあるやきとり屋へ行く。
10数年ぶりだが全くなかは変わっていなくてやきとりもおいしい。
旬な鮎の塩焼きとかも食べられたし、久々に日本酒もたくさん飲んでしまった。
結局彼の終電の時間までいろいろとしゃべっていたわけである。
音楽でつながっている友人というのは会話以外でも楽器を通じてのコミュニケーションができるので楽しい。
いつかはホテルの会場でも借りて身内での音楽発表会ができればいいななどど話は広がっていった。
| ■2004/06/27 (日) 人前での演奏の難しさ |
午後は昼寝のあと母と長男に新しいヴァイオリンで数曲弾くのを聴いてもらう。
やはり人前で弾くときはひとりで練習しているのとは全然違う。
たとえ家族の前であっても緊張するのだろう、できないところが多すぎる。
それにあたらしい楽器がまだじゃじゃ馬娘のようにコントロールできていない。
慣れてくると次第に調子が出てきたが、それでも焦ってるし力が入っているのがわかった。
しかしこれは予想がついたところなのでこうして慣らしていくしかない。
場数を踏んだジャズのピアノならもっと最初からリラックスして弾けるはずである。
ま、いい経験だった。
| ■2004/02/13 (金) ミニ・コンサートその2 |
今日は朝から義母がやや遠方よりやってきて妻と自由ヶ丘でお買い物。誰もいない家でまたヴァイオリンを弾いてた。昼ごろ昼食を買って帰ってきたので一緒に食べて、+自由ヶ丘のロールケーキ屋が評判だというので9種類も買ってきた。どれもおいしく結局子供たちも帰ってきてからあっという間に全種類を少しずつ味見しながら食べてしまった。
妻が義母に「ヴァイオリン弾いて聴かせたら?」というのでまた厚かましくも1曲披露。義母は最初はあっけにとられていたが、知っているボッケリーニのメヌエットを弾いたらホントに涙を流して喜んでくれた。こんなに力強く弾けるのだからもう大丈夫!」と励ましてくれたのがうれしかった。いろいろな人に心配をかけているんいるなぁ、と反省。しかし、やはり練習の積み重ねか今日は力が抜けて弾いていていろいろな表情をつけられたのが進歩。30年間黙って待っていてくれた愛器にも感謝。
| ■2004/02/12 (木) ミニ・コンサート? |
昨日は兄夫婦がやってきてうちで昼食を共にした。いろいろ話をしているうちに兄の奥方が「ヴァイオリンをぜひ聴きたい」というので、未熟ながらカラ・ピアノのCDに併せて2曲ほど弾いた。ヴァイオリンを複数の人の前で弾くのはホントに20数年ぶりなので緊張した。右手のボーイングの重要性がよくわかり勉強になった。しかし、とても自分の中では自信になったと思う。
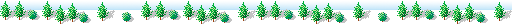
 (開演直前)
(開演直前)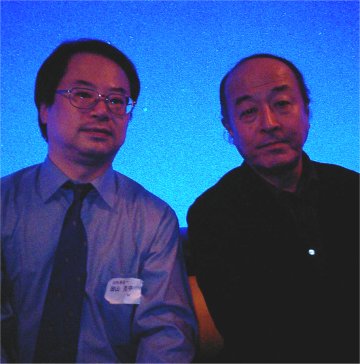 池辺さんと(2次会で)
池辺さんと(2次会で)