(2006.02〜)
@Violin Lesson
![]() モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第28番 ホ短調 K.306
モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第28番 ホ短調 K.306
(2006.02〜)
@Violin Lesson
今年はモーツァルト・イヤーなのでレッスンではモーツァルトの曲を中心に教えていただこうかと思っている。
これは「アダージョ」に続く第2弾で、まだ譜読みの段階である。
いい演奏がたくさんあり、それらを参考にしながら自分の考える音楽というものを出していきたい。
(2006.2.3 記)
| アルバム | 演奏者 (レーベル・録音年) |
演奏 | 録音 | 寸評 | |
| 01 |  |
ヒラリー・ハーン(Vn) ナタリー・シュー(Pf) DG 2004 |
4.5 | 4.5 | 昨年の来日リサイタルで生ハーンを聴いたが、現在のヴァイオリニストの中ではクレーメル、ヴェンゲーロフとならんで最高峰といっていい充実した演奏だった。 このCDでも根の張った深い音色でいささかの意味のない音も存在しない。 ヴァイオリンに関して言えばこの曲のベストの演奏かもしれない。 ただ、0.5ポイントの減点はピアニストのシューのやや平坦な部分に対してである。 (2006.2.3 記) |
| 02 | 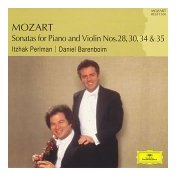 |
イツァーク・パールマン(Vn) ダニエル・バレンボイム(Pf) DG 1980 |
2.5 | 2.0 | やや表情過多でロマンティックに寄りかかりすぎた印象である。 モーツァルトのダイナミズムとはもっと軽やかなものではないのか?というのがこの演奏を聴いての疑問。 パールマンは細かいところを繊細に表現しているのだが、バレンボイムがあまりグランド・マナーで、はかなさや哀しさに欠け、豪快すぎるところに原因がありそうだ。 第2楽章にこれが顕著に現れる。 録音もキンキンした印象で期待の割には肩透かしを食った気がした。 (2006.2.6 記) |
| 03 | 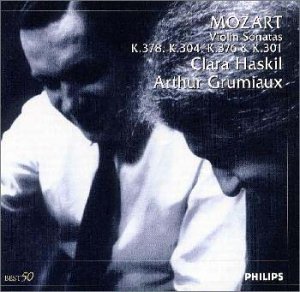 |
アルチュール・グリュミオー(Vn) クララ・ハスキル(Pf) PH 1950 |
5.0 | 3.5 | 録音は古くなったが、さすがに往年の名コンビといわれるだけあって説得力がある。 ハスキルのピアノはいい録音がなく、今まで名の割りには実態がつかみにくかったが、この演奏を聴いて有名な20番協奏曲の演奏に続き、ハスキルのよさというものが実感できた。 第2楽章の出だしなど泣き出したくなるほど素晴らしい。 モーツァルトの詩情にとてもマッチするのだ。 グリュミオーは再録盤に比べると控えめな感じだが、初々しさが出ていて好ましい演奏である。 両者の絶妙なテンポ感がこの演奏を際立たせている。 (2006.2.6 記) |
| 04 | 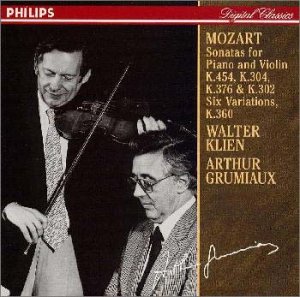 |
アルチュール・グリュミオー(Vn) ワルター・クリーン(Pf) PH 1970 |
4.5 | 4.5 | まずグリュミオーの音色のすばらしさに耳を奪われる。 録音もシャープで非常にすばらしい出来である。 ピアノのクリーンも名前のとおり澄み切った音色とニュアンスでヴァイオリンと一体となりすばらしい。 モーツァルトのmoll曲の厳しさ、透明度が味わえる。 第2楽章でのあふれんばかりの詩情、中間部の暖かさは無類である。 ハーン盤でのヴァイオリニストとピアニストの格の違いを感じさせないバランスのいい演奏だ。 ただ、一点だけだが、両者とも中年の押しの強さのようなものもチラリと見えるところがいかにも惜しい。 (2006.2.6 記) |
| 05 | 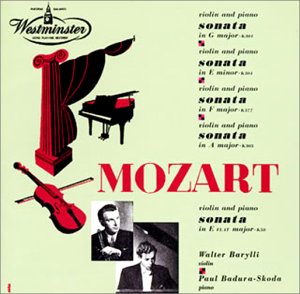 |
ワルター・バリリ(Vn) パウル・パドゥラ=スコダ(Pf) WM 1950 |
3.0 | 2.5 | 比較して聴いてくるとまずピッチの低さが時代を感じさせる。 おそらく440Hzくらいなのかな? 両者の音楽的なバランスはよい。 ただ、演奏も切れ味はなく、いい意味でのウィーン情緒、悪く言うと細かい表現のあいまいさを感じる演奏だ。 ただし、バリリにはボスコフスキーにはない音色の芯がある。 グリュミオー&ハスキルが録音は古くとも説得力があるのとは対照的で、やや焦点のぼけてしまった感は否めない。 (2006.2.6 記) |
| 06 | 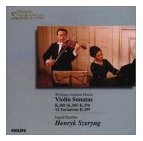 |
ヘンリック・シェリング(Vn) イングリッド・ヘブラー(Pf) PHILIPS 1960 |
3.0 | 3.0 | 定評のあるシェリング&ヘブラー盤であるが、一聴したところ温和だが平板な印象を受ける。 また、堅実すぎて時として流れがせき止められる感がある。 たとえば第2楽章の入りをハスキル盤の繊細かつ流麗さに比べ、ヘブラーはあまりに普通だ。 それなりの環境で聴けば、もっと細かいニュアンスが伝わってくるかと思うが、いい演奏はたとえば電車の中でウォークマンで聴いても伝わってくるものがある。 そういう意味では中庸の美学を求めた演奏で、他と比べて突出したものを求めるべきではないのかもしれない。 (2006.2.6 記) |
| 07 |  NO IMAGE |
ウィリー・ボスコフスキー(Vn) リリー・クラウス(Pf) EMI 1960 |
2.0 | 1.5 | テンポ感はなかなかよい。 しかしヴァイオリンの録音が浅く、古いこともあるが、ヴァイオリンがピアノに完全に負けてしまっている。 やはりソリストとオケ・プレイヤーの違いはこうしたソロ曲を比べると顕著になるのかもしれない。 音程・表現があいまいでクラウスの確固たる音楽に追いついていない。 (2006.2.6 記) |
| 08 | 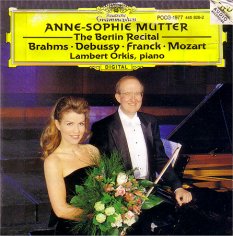 |
アンネ=ゾフィー・ムター(Vn) ランバート・オーキス(Pf) DG 1990 |
3.5 | 3.5 | 第1楽章でのヴァイオリン、第2楽章でのピアノ、それぞれなにか忍び込むような出だしである。 ムターは変幻自在の音色でまさに名人芸!しかもそこにはあざとさは感じない。 ピアノは押さえ気味の表現が好ましいが、多少作為を感じる。 好き嫌いから言うと、多少ロマン派に偏った表現で古典からの逸脱を感じ、やや嫌い。 でも、面白いアプローチであることは確かである。 (2006.2.7 記) |
| 09 | 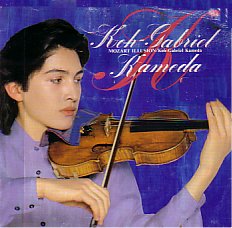 |
コー・カブリエル・カメダ(Vn) | 1.0 | 2.5 | まず、全般に基本テクニックが欠如しているのと、ヴァイオリンとピアノのテンポ感に相違があり、いたる箇所でズレが生じるのはいただけない。 細かい音符がいい加減に弾かれており若さを割り引いたとしても、プロとしてはまだまだ研鑽が必要のようだ。 ピアノも同じくうるさい感じがしてモーツァルトとは別種の音楽である。 (2006.2.7 記) |
| 10 | 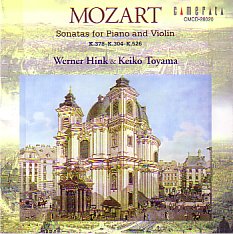 |
ウェルナー・ヒンク(Vn) 遠山慶子(Pf) カメラータ東京 |
4.0 | 3.5 | とても滑らかな滑り出しで、ウィーン風味という感じがする。 全般を通じ作為のなさが自然さをかもし出す。 反面、速いパッセージにかかると軽さが目立つところが惜しい。 やや残響の多い録音は曲の輪郭を多少ボケさせる。 でもいい演奏。 (2006.2.7 記) |
| 11 | 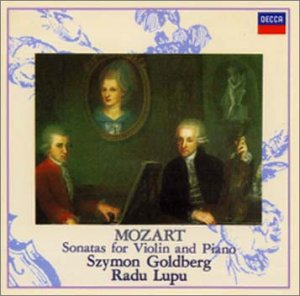 |
シモン・ゴールドベルク(Vn) ラドゥ・ルプー(Pf) KING |
|||
| 12 | 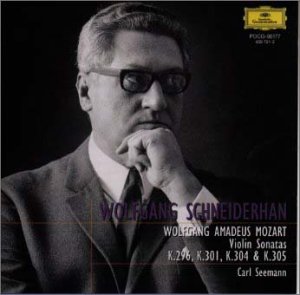 |
ヴォルフガング・シュナイダーハン(Vn) カール・ゼーマン(Pf) 1954年12月17日 ハノーファー、〈モノラル録音〉 DG |
|||
| 13 | 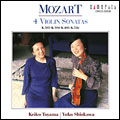 |
塩川悠子(VN) 遠山慶子(Pf) カメラータ 1983年5月 埼玉 ほか |
|||
| 14 | 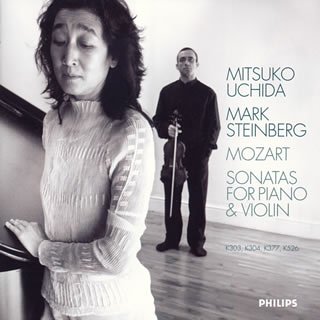 |
マーク・スタインバーグ(Vn) 内田光子(Pf) Philips 2004年6月28日〜7月1日、スネイプ・モルティングス |
|||
| 15 | 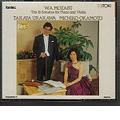 |
浦川宜也(Vn) 岡本美智子(Pf) フォンテック |
|||
| 16 | 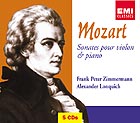 |
ツィンマーマン(Vn) ロンクィッヒ(Pf) EMI Classics |
|||
| 17 | 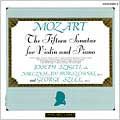 |
ヨーゼフ・シゲティ(Vn) ミエチスラフ・ホルショフスキー(Pf) ヴァンガード・クラシックス CBS 30丁目スタジオ,ニューヨーク |
|||
| 18 |  NO IMAGE |
オーギュスタン・デュメイ(vn) マリア=ジョアオ・ピリス(p) DG |
![]()