ヴァイオリニスト私的考察
このページでは、いわゆるプロフェッショナルなヴァイオリニストに関して、筆者が個人的な見解を述べたものです。
生演奏を実際に聴いたヴァイオリニスト、映像を見たことのあるヴァイオリニスト、録音でしか聴いたことのないヴァイオリニストなど様々ですが、先入観に左右されないできるだけニュートラルな状態での記述を目指したいと思います。
![]()
| 名 前 | Name | 生没年 | 音 | 映像 | 実演 |
| ミッシャ・エルマン | Mischa Elman | 1891-1967 | ○ | ○ | × |
| ジノ・フランチェスカッティ | Zino Francescatti | 1905-1991 | ○ | ○ | × |
| ヤッシャ・ハイフェッツ | Jascha Heifetz | 1901-1987 | ○ | ○ | × |
| ブロニスラフ・フーベルマン | Bronislaw Huberman | 1882-1947 | ○ | × | |
| アルチュール・グリュミオー | Arthur Grumiaux | 1921-1986 | ○ | ○ | × |
| フリッツ・クライスラー | Fritz Kreisler | 1875-1962 | ○ | ○ | × |
| レオニード・コーガン | Leonid Kogan | 1924-1980 | ○ | ○ | × |
| ギドン・クレーメル | Gidon Kremer | 1947- | ○ | ○ | ○(2004) |
| チョン・キョンファ | Kyung-Wha Chung | 1948- | ○ | ○ | |
| ユーディ・メニューイン | Yehudi Menuhin | 1916-1999 | ○ | ○ | × |
| アンネ・ゾフィー・ムター | Anne-Sophie Mutter | 1963- | ○ | ○ | |
| ダヴィド・オイストラフ | David Oistrakh | 1908-1974 | ○ | ○ | × |
| イツァーク・パールマン | Izark Perlman | 1945- | ○ | ○ | |
| アイザック・スターン | Isaac Stern | 1920-2001 | ○ | ○ | ○(1975) |
| ヨゼフ・スーク | Josef Suk | 1929- | ○ | × | |
| ヘンリック・シェリング | Henryk Szeryng | 1921-1988 | ○ | ○ | × |
| ヨゼフ・シゲティ | Joseph Szigeti | 1892-1973 | ○ | ○ | × |
| ジャック・ティボー | Jacques Thibaud | 1880-1953 | ○ | ○ | × |
| ピンカス・ズーカーマン | Pinchas Zukerman | 1948- | ○ | ○ |
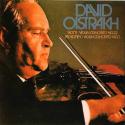 ダヴィド・オイストラフ
ダヴィド・オイストラフ
この大ヴァイオリニストは1974年に急死してしまい、年代的には聴くチャンスはあったのだが叶わなかった。
安定感のある包容力豊かなその音色は、凡百のヴァイオリニストとは比較できないほど群を抜いたものであり、あとあまり言われないことだが、テンポ感・スピード感も曲によって最適な選択をしている。
ベートーヴェンのコンチェルト(クリュイタンス指揮)は、この曲の持つスケールの大きさを見事に描ききっている。
オーマンディとのメンデルスゾーンとチャイコフスキーのコンチェルトは一転してそれぞれの曲の持つ軽やかさや、トリッキーさなどを縦横無尽に表現しており、いまだに自分の中でのこの3曲のベストは上記盤である。
ブラームスのコンチェルトに関しては、セルとの晩年のものが好きだが多少全体構成に押しの強さが目立ちすぎる感がないでもない。クレンペラーとのものは録音のせいか音の薄さが全体に感じられ、採らない。
他にはロジェストヴェンスキーとのシベリウス&チャイコフスキーのカップリングが切迫感のあるギリギリさが緊張感を誘う。
ロストロ、リヒテル、カラヤンとのベートーヴェンのトリプル・コンチェルト、ロストロ、セルとのブラームスのダブル・コンチェルトはクラッシックを聴き始めた頃の話題の新譜でいまだに愛聴している。
室内楽ではリヒテルとのもの、特にフランク&ブラームスの3番ソナタが巨匠同士のいい意味でのぶつかり合いが聴ける。
定評のあるオボーリンとのベートーヴェンのソナタ全集は聴き込みが足りないのかインパクトが感じられない。
最近出た50年代の来日時の録音集というのを聴いてみたい。
(2005.10.6)
 アイザック・スターン
アイザック・スターン
中学・高校生の頃オイストラフとスターンは現存する最高のヴァイオリニストという存在であった。
特にスターンは高校2年生の時、東京文化会館の前から2列目で見たので、とりわけ印象が強い。
その時の演目はベートーヴェンのロマンス2曲と、メンデルスゾーン&ブラームスのコンチェルトだった。
特にブラームスでステージから落ちてしまうのではないかと思うほど舞台の最前まで上体を乗り出して弾く様は今でも強烈に覚えている。
バックは森正指揮のN響だったかと思うが、とにかくスターンの一挙一動に目が釘付けだった。
スターンはやはりレコードでもオーマンディがバックを務めたブラームスのコンチェルトが自分にとってぴったりとくる演奏である。
同じくオーマンディとのメン&チャイも定評があるが、いわゆるバタっこさを感じてしまい、オイストラフ&オーマンディ盤に軍配を上げたい。
バーンスタインとのベートーヴェンもややバタっこいがエネルギッシュな演奏で割りと好きである。
オーマンディとのシベリウスはベスト。
ブラームスのソナタも60年代のものは素晴らしい。
70年代後半以降はあまり聴いていなかったが、後年録音されたベートーヴェン、チャイコフスキー、メンデルスゾーンなどのコンチェルトを聞く限りでは黄金期は50-60年代だったように思う。
ただ、75年頃放送されたノイマン/チェコ・フィルとの来日公演でのベートーヴェンのコンチェルトは出来としてはムラがあるが思い出に残る演奏である。今でもFMから録音したものをCD-Rにおとしてたまに聴いている。
(2005.10.6)
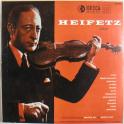 ヤッシャ・ハイフェッツ
ヤッシャ・ハイフェッツ
ハイフェッツという存在を知ったのは中学生の頃NHKで放送された「ハイフェッツ・オンTV」という番組であったと思う。
正確無比な機械のようなヴァイオリニストというイメージがあって、放送の中でもあまり笑顔は見せず、なんか怖い感じだなぁと思ったのを覚えている。
そのなかではプロコフィエフの「3つのオレンジへの恋」行進曲というのが摩訶不思議な感じで好きになった。
ハイフェッツのクールなイメージにも合っていたのだろう。
その後ヴァイオリンの先生に薦められて「チゴイネルワイゼン」や「序奏とロンドカプリチオーソ」などが入った17cmLPレコードを買う。
確かにすごいが、細かいピッチカートなどは弾き飛ばしている感じで丁寧さに欠ける気がした。
同じ頃サラサーテの自作自演盤を聴いたが、こちらの方が第3部の音の粒は揃っている。
これはいまだに疑問に感じていることであるが、世評の通りハイフェッツはヴァイオリンの特性を本当に生かした最高のヴァイオリニストなのだろうか?ということである。
自分においてはハイフェッツはバッハの無伴奏、ベートーヴェンを始めとする4大コンチェルト、ベートーヴェンのソナタ全集などどれをとってもそっけなさ過ぎて感動できない。
トスカニーニとのベートーヴェンのコンチェルトなど切羽詰りすぎていてあの曲の豊かなイメージが皆無。カミソリのようなヴァイオリンとオーケストラの響きは全く持ってミスマッチとしか言いようがない。
ハイフェッツを買うとすれば、ガーシュインや先のプロコフィエフといった近現代の作曲家の彼自身のアレンジものが自身の美徳を最も表しているものだと思う。
あまりいいと思えないのは聴き方が足りないのであろうか?と悩んでしまう大ヴァイオリニストである。
(2005.10.6)
 ヨゼフ・シゲティ
ヨゼフ・シゲティ
この人も人気の高い往年の大ヴァイオリニストである。
最初に聴いたのは高校生の時で、バッハの無伴奏だった。
音がかすれ音程も外れがちで、どこがいいのか全くわからなかった。
続いて聴いたステレオ録音のベートーヴェン、ブラームスのコンチェルトでも印象は変わらず。
評論家は(特に日本的な評論をする方々)、その下手なところがいいとかワケのわからない誉め方をするし・・・
なんか精神論だけで語られてかわいそうな感じがした。
それから30年ほど経って聴きなおしたバッハの無伴奏は、当時感じた弱々しさはなく、何をこのヴァイオリニストが訴えたいのかがよくわかる演奏だった。
なるほど音楽を聴くということはある程度経験が必要なのかということを感じた次第。
その後に若き日の映像を見ると、技術も大したものでイメージが大分変わった。
死にそうなおじいちゃんというイメージから、頭の毛は薄いが精悍なヴィヴィッドなヴァイオリニストとしての側面が垣間見れた気がした。
40年代のバルトークとの「クロイツエル・ソナタ」、コンサート録音での一連のバッハの無伴奏作品など気迫溢れる演奏だ。
改めてシゲティは決して下手なヴァイオリニストではない、晩年の演奏は肉体的な衰えがもたらしたものであり、若い頃の演奏を補完した上で傾聴すればそこには伝えたい内容が聴き取れるはずである。
(2005.10.6)
 フリッツ・クライスラー
フリッツ・クライスラー
あんな音でヴァイオリンが弾けたなら・・・クライスラーを聴くたびに思うことである。
多分最初に聴いたのは中学の頃に聞いたSP盤(友人が持っていたのを、まだ78回転演奏が可能なステレオが我が家にあったのでかけた)のパガニーニの1番コンチェルトではなかったかな?
1楽章しかなく最初のオケ部分はチリチリ音に紛れてほとんど聞こえなかったが、突如甘美な音色が立ち上った。
それがクライスラーの独特の美音であった。
それから1927年に録音されたベートーヴェンのコンチェルトの復刻LPを聴く。
レンジが狭くオーケストラの広がりはないが、クライスラーを聴くためのもので、自作の19歳の時に作曲されたという有名で素晴らしいカデンツアを自身の演奏で聴けたのには感激した。
その後ブラームス、メンデルスゾーンのコンチェルトでもその甘美で懐かしい音色を味わう。
そして唯一残されたバッハの無伴奏、ソナタ1番のアダージョに深い感銘を受けた。
ハイフェッツと対極に位置する大ヴァイオリニストとして語られることが多いが、自分にとってはヴァイオリンとはかくあるべしという音を具現化した神様みたいな存在である。
最近は自作の小品集(作曲の才を含め)や、ベートーヴェンのソナタ全集でその妙技を改めて味わっている。
(2005.10.6)
 ジャック・ティボー
ジャック・ティボー
この洒落たフランス人ヴァイオリニストを知ったのも中学生の頃である。
1953年に来日の途中アルプス山中で飛行機事故により亡くなった。
ティボーに関しては実は中学高校の当時はあまり聞いていない。
ストコフスキーが指揮をしたラロのスペイン交響曲と、その裏面に入っていた小品集くらい。
あとはカザルス、コルトーとの「大公トリオ」か。
実はコルトーとのフランクのソナタを聴いたのもつい2年程前が最初である。
昔の演奏なのでよくわからない、というのが実際のところだった。
しかし、シゲティ同様「アート・オブ・ヴァイオリン」というDVDのなかでの映像を見て、独特の構えと、しっかりとした、しかし洒落たフレージングを見て初めてティボーという人の粋が理解できたような気がする。
最近オーパス蔵で復刻された小品集を手に入れて聴いているが、その粋さが表れているものもあり、ノイズに埋もれてしまっているものもあり、もう少しいろいろ聴いてみたいところである。
(2005.10.6)
 ブロニスラフ・フーベルマン
ブロニスラフ・フーベルマン
中学生の頃FMで放送されたチャイコフスキーのコンチェルトを聴いて、その快刀乱麻ぶりに唖然とし、何度も聞き返したのがこのヴァイオリニストとの出会いである。
この勇壮果敢なヴァイオリニストはユダヤ人であることに誇りを持ち、戦時中も決してファシズムに屈することなく、戦後はイスラエル・フィルの創設にまで貢献したということである。
人間的には愛用のストラディバリウスを2度盗まれたとか、なんか抜けた面もあったみたいだが、ことヴァイオリンを弾かせると別人のごとくとはこのことで、火を噴くような演奏は先のチャイコフスキー以外では「クロイツェル・ソナタ」で、この2曲だけでもこの人の存在感は圧倒的である。
セルとのベートーヴェンのコンチェルトは意外とおとなしい感じだが、独特のクセはやはり彼ならではのものかもしれない。
(2005.10.6)
 ヘンリック・シェリング
ヘンリック・シェリング
自分の中での位置付けの難しいのがこのシェリングである。
高校生くらいの時にパガニーニの3番コンチェルトを発掘したとかで、TVでその演奏が紹介され、レコードも買った覚えがある。
さらにバッハのスペシャリストとして、彼の弾く無伴奏ソナタ&パルティータは定番となっていた。
ベートーヴェンのコンチェルトも定評があったし、とにかくムラがなく水準を越えた演奏をするというイメージだった。
とはいいながら当時は無伴奏もベートーヴェンも聴いたことはなく、知識としての名ヴァイオリニストであった。
ここ数年いろいろなものを聴くようになり、新旧バッハ無伴奏、来日公演の抜粋などを聴くと、なるほど堅固だが融通性もある立派な構築物をイメージできる。
時を越えてリヒターのバッハのように指針となる演奏だな、と感じた。
コンチェルトもベートーヴェン、ブラームス、メン&チャイなど聴いたが、こちらは無難。
破綻がなく予定調和の世界であり、今ひとつパッションが欲しいというのが共通の感想。
ルービンシュタインとのベートーヴェン、ブラームスのソナタも同様。
逆に魅力的だったのが、クライスラー作品集で、ここでは真面目さ一辺倒ではない遊び心に通じるリラックスした側面がうかがえシェリングという人の多面性が認識される。
あとヘブラーとのモーツァルトも中庸の極をいく演奏だが、割りと好きである。
(2005.10.6)
 アルチュール・グリュミオー
アルチュール・グリュミオー
中学の頃はその柔和な風貌からきっと弱々しい音に違いないと全く聴いたことがなかった。
数年前に初めて聴いてその美音に惹きつけられる。
サン・サーンスの3番コンチェルトでの自在さと抜けるような音の洒脱さ!
小品集でのひとつひとつの独立した作品の音楽性の高さ!(タイスの瞑想曲は参考になりました)
全体に柔和であることは風貌どおりだが、その音色の美しい透明性と曲解釈のセンスのよさがこのヴァイオリニストの持ち味である。
バロック作品にも相性がいい。
ヴィルトゥオーゾ的なものは趣味の良さが生き、メン&チャイとかスペイン交響曲、ブルッフなどで爽快な演奏を披露する。
大曲となるとベートーヴェン、ブラームスでは軽さが目立ち、バッハの無伴奏では底の深さという点でやや不利である。
ハスキルと組んだベートーヴェンのソナタ全集はやはり名盤で、ふたりのギリギリのところでの哀切がにじみ出ていて感動的。
後年のアラウとの選集もさらに奥深くなったグリュミオーを聴くことができる。
(2005.10.6)
 ヨゼフ・スーク
ヨゼフ・スーク
スークはチェコの名ヴァイオリニストだが、真面目な風貌と堅実な技巧というイメージが付きまとい、これも若き日の自分にとってはあまり関心の向かないヴァイオリニストであった。
最近になってこの人は私自身がヴァイオリンの曲をこう弾きたいなと思うと、そのとおりに弾いてくれる一番近い解釈を持っているのではないかと思うようになってきた。
もちろん自分がそんな巧く弾けるわけではないが、このフレーズのこの間、といったところがすごくピタリと合うのである。
妙なフィルターをかけず、本当に自然な音でヴァイオリンを鳴らす。
聴いていて何にも煩わされることなくスーっと心に入ってくる音である。
天然ものといった感じのバッハの無伴奏、独特のスラブの風味が自然とかもし出されるドヴォルザークの作品集、そして最近気に入っているのが全くの自然体でのベートーヴェンのソナタ全集である。
コンチェルトでもオーケストラに対して主張するのではなく、調和を求めていくのが特徴的である。
十分に生で聴けるチャンスがあった人だけに残念だ。
(2005.10.6)
 ユーディ・メニューイン
ユーディ・メニューイン
10代のときに天才ヴァイオリニストとして、今聴いても十分な芸術性を持った録音を残しながら、成人していくとともに輝きが失われていったある意味で悲劇のヴァイオリニスト。
フルトヴェングラーと共演した30歳前後に一時的に立ち直ったといわれるが、10代の頃の演奏に比べると音のコク、意味合いの深さを取り戻したとは思えない。
オイストラフのベートーヴェンのコンチェルトを聞いてから、フルトヴェングラーとの同曲の共演盤を聴けば、その言わんとするところがわかると思う。
3つのバッハの無伴奏を10代、40代、60代(位だと思う)で残しているが、あとにいくに従い10代の輝きばかりが目立ってしまう。
たしかに成人してからはヴァイオリニストというよりも音楽大使としての人生であったというのが正しいのかもしれない。
(2005.10.6)
 ジノ・フランチェスカッティ
ジノ・フランチェスカッティ
中学時代、この人の演奏するスペイン交響曲とパガニーニの1番コンチェルトがカップリングされているアルバムをよく聴いた。
そのまぶしいばかりの音色に魅了されたものだ。
よくラテン系の明るい音色と言われるが、たしかに音色の輝かしさとラテンのリズムの爽快感を併せ持っていたヴァイオリニストだったのかもしれない。
ワルターとのベートーヴェンも柔和なワルターの表現の上で趣味よくソロを展開しているし、カサドゥシュとのスプリング&クロイツェル・ソナタもその特質が生かされている。
軽やか過ぎるというのが今ひとつ大ヴァイオリニストのランクから外される理由かもしれないが、これだけ自在にハッピーにヴァイオリンという楽器を操れるだけで大した才能だ。
もっといろいろな演奏を聴いてみたい。
(2005.10.6)
 レオニード・コーガン
レオニード・コーガン
この人は顔が怖い。
ゆえに音楽も怖そうだと敬遠して、やはり最近まで聴かなかったひとりである。
聴いてみるとすごい。
なんとも音楽的で、抜群の表現力である。
ブラームスのソナタ全曲、コンチェルトなど聴いてみると、なるほどオイストラフと並び称されるだけの実力の持ち主であった。
まだ自分の中では断片的にしか聴いていないのでもう少し体系的に聴いてから再度コメントをしてみたい。
(2005.10.6)
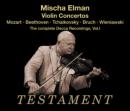 ミッシャ・エルマン
ミッシャ・エルマン
恰幅のいいおじいちゃんという印象で、エルマン・トーンという名で呼ばれる独特の音色は知っていたが、聴いたのはヴィニアフスキーの2番コンチェルトくらいだった。
これまた「アート・オブ・ヴァイオリン」のDVDで演奏姿を初めて観て、「ユーモレスク」を難しい重音で歌い切る職人芸にとても驚かされた。
その他どこかの音楽祭でチャイコンを弾いている場面もあり、やはり一種の名人芸的な歌い回しに興味を持った。
アルバムとしてはクライスラー曲集を聴いたが、独特のフレージングはやはり一世を風靡したのだろうなぁ、と推測させる。
エルマン節を味わえるかなと思い購入したメンコンは晩年のものらしく、技術的にも大分衰えちょっと哀しかった。
(2005.10.6)
 イツァーク・パールマン
イツァーク・パールマン
今や世界の巨匠というかコマーシャライズされたクラシック界の巨匠という存在のパールマンだが、中学生だった頃世界の楽壇に登場したパールマンはとても鮮烈な印象だった。
初めて聴いたのはヴィニアフスキーの2番コンチェルトだったが、無類の安定感とフレッシュな音色、決して冷たくない包容力を感じさせるその表現はヴァイオリンの次の世代を代表する存在のように思えた。
それからは順風満帆で王道を歩みつづける。
ただ難点があるとすると巧すぎて、曲を通じて何かを心に訴えるという訴求力にかけるところではないか。
なんでもいとも簡単に最上の音色で弾いてしまうため、その音楽は常に楽天的に鳴っている。
デビューの頃のメンデルスゾーンとブルッフの1番では若さがその開放感を助長し、素晴らしい出来になっているが、ベートーヴェン、ブラームスあたりになるとその明るさが裏目に出てしまう。
バッハの無伴奏も技術的には素晴らしいが、求心性というか心を解放してくれる音楽としては感じられないのである。
その何かが生み出された時、パールマンは真の意味での大ヴァイオリニストになるのではないかと思う。
(2005.10.6)
 ピンカス・ズーカーマン
ピンカス・ズーカーマン
パールマンと同じ頃のデビューだったと記憶している。
モーツァルトの4&5番コンチェルトのデビュー・アルバムを買った。
パールマンより重太い音色で、ヴァイオリンとしては地味な音色だな、と思った。
その後はヴィオリストとしても活躍し、表現の幅も広げていくが、やはりパールマンの次の人という印象がいつもついてまわる。
最近小品集を2枚聴いたが、決して悪くない。
ただ圧倒的な存在感を出すにはいつも至らないというのがこの人らしい点である。
パールマンはたいていの曲をバレンボイムの指揮またはピアノでやっており、ズーカーマンも後追いのようにバレンボイムと共演する。
ひとつの違いはブラームスのクラリネット・ソナタのヴィオラ版はズーカーマンしかやっていないところで、そこでの枯淡の境地を聴く時、同時代にパールマンが常に半歩前にいるズーカーマンの内心を慮ってしまう。
(2005.10.6)
 アンネ・ゾフィー・ムター
アンネ・ゾフィー・ムター
10歳そこそこの少女がカラヤン/ベルリン・フィルをバックにデビューしてから30年が過ぎようとしている。
今聴いても当時の演奏は天才少女というよりもうすっかり成熟したヴァイオリニストの表現である。
特にベートーヴェンやブラームスのコンチェルトを10代で、細かい技術はもとよりあれだけの構成力で弾けるのは奇跡に近い。
最近はすっかりムターの世界を築きつつあり、この辺が好みの分かれてくるところではあるが、王道から超個性への変貌を続けていく様が録音を通じても聴いて取れる。
小品においてカラヤンばりの音の磨き方には正直閉口するが、2004年録音のチャイコンはやはり圧倒的な表現力である。
CD店で視聴してぶっ飛んだ。
そのあと並んで置いてあったコンクール優勝の日本人女性ヴァイオリニストのデビュー盤を聴いて、大人と子供くらいの違いを感じた。
常に安全運転を求めるより自分の信念の元に演奏をしていくムターは立派だと思う。
(2005.10.6)
 チョン・キョンファ
チョン・キョンファ
この人も若くから天才ヴァイオリニストの名をほしいままにした人である。
1989年の来日リサイタルはチケットを買ったが、都合でどうしてもいけず、以後も実演には接していない。
ベートーヴェン、メンコン、ブルッフ1番などは映像でも観ることが出来、確かにトラが獲物に挑んでいくような演奏姿は緊迫感がある。
この人は女性であるがゆえにムター同様人生もドラマティックで、それに対応して演奏にも波があると言われる。
若き頃のコンチェルト録音は一様に素晴らしく、どれをとっても水準を大きくクリアしているように思う。
最近は身振りが大きくなったというか、音楽にある種の空白を感じてしまう演奏がなくもない。
しかし、まだまだこれからを期待できる存在であると思う。
(2005.10.6)
 ギドン・クレーメル
ギドン・クレーメル
この人ほど先入観と聴いてからの印象が変わった人もいない。
まず、若い頃は陶酔しきった表情で口を半開きにして弾く姿を見ただけで生理的に受け付けなかった。
たしかに美音だが弱々しい音色に聞こえたのも事実だ。
そうしてほとんど聴かないまま昨年のクレメラータ・バルティカを率いた来日公演を最前列で聴いた。
ブランデンブルグの3番だったが、最初の音が鳴った瞬間、ぞくっとした。
シルクのように柔らかで、ビロードのように絢爛たる響き。
これだけでクレーメルおたくになりましたねぇ。
バッハとシュニトケを交互に配置するプログラムで、少しも弛緩なく最上の音楽を聴くことが出来たように感じた。
帰ってからは数だけは持っていたクレーメルのCDをとっかえひっかえ聴いてみたり、録画した映像を見たりした。
弱点だと思っていた部分が実は最大の美点で、これだけのユニークな世界を描ききれるヴァイオリニストは世界でも一握りしかいないと、今は思っている。
(2005.10.7)