
http://www12.plala.or.jp/ibmorch/
オーケストラ

http://www12.plala.or.jp/ibmorch/
![]() 練習日記(上に行くほど新しい内容です)
練習日記(上に行くほど新しい内容です)
![]() 演奏会レポート
演奏会レポート
・第10回定期演奏会 2007年11月26日@すみだトリフォニーホール
・会社の新入社員修了式記念演奏 2007年3月23日@OVTAホール
・第4回 室内楽演奏会 2007年2月11日@大田区民センターアプリコ小ホール
・第9回定期演奏会 2006年11月26日@すみだトリフォニーホール
・会社の新入社員修了式記念演奏 2006年3月17日@OVTAホール
・第3回 室内楽演奏会 2006年1月21日@目黒区民ホール
・第7回定期演奏会 2005年11月26日@ミューザ川崎シンフォニーホール
・第6回定期演奏会 2005年5月29日@大田区民センターアプリコ大ホール
| ■2007/05/27 (日) IBMオケ 第10回定演@すみだトリフォニーホール |
今日は快晴。
演奏会日和?である。
9時半頃会場につき楽屋入り。
10時半からステリハが始める。
客席が空いた状態の響きは思ったよりデッド。
音符が切れるところは上空に舞い上がるように響くが、ステージ上での細かい動きはそのまま聴こえる感じ。
ステリハでは、フンパーディンク、チャイ5、弦セレ、シベコンの順に行う。
昼食、着替えなどしているうちに予ベルがなる。
ステージ裏に集合し、チューニングのあと三々五々ステージへ出て行く。
このあたりもう少しまとまっていったほうがいいような気がした。
ステージ上で手持ち無沙汰な感じがする。
と思っているうちに照明が落ち、コンミス登場。
いつもながら艶やかないでたち。
そのあと一正先生が登場し、フンパーディンクが始まる。
やはりホルン、惜しいなぁ。
練習の最高のときのものを出すというのがいかに難しいかをまたまた実感。
弦のピチカートはお客さんが1200以上入っていただいたおかげで、ころよい響きとなって舞い上がる。
全体的には並の出来か。
シベコンはやはりまろ先生人気で、客席の前の方は女性が多い。
あれほどバラバラだったバックもここ数回の練習でかなりまとまってきた。
とりあえず破綻なく先生の入魂のソロにつけることが出来たと思う。
大喝采で3回ほどのカーテンコールがあり、前半終了。
後半もしばしの休憩ののち、チャイ5となる。
冒頭の足取りは、冬の寒さ、厳しさが表現されていたように思う。
次第に先生の棒からのエネルギーがオケ全体に伝播し、あっという間に終った気がする。
第2楽章に入ってもテンションは落ちず、むしろ切なさがより表出されてきて、心から音楽を!という気持ちが先に立っていった。
第3楽章、ドンくさく。やや洗練さているかな?
れいの中間部はやはり走ってる、走ってる。
他のパートにも伝播し、やや苦しかったが後半持ち直し、終楽章へ。
冒頭から中身のある音が出ていた。
めまぐるしく表情が変わる部分も決して荒っぽくはしないで、激変するテンポも頭の中に入っており、ある方向性は出せたのではないか。
惜しむらくは今一歩の鋭角性というか、えぐりがあるとさらに印象に残るのではないかと思った。
しかし、ブラヴォー!が続き、苦しんでやってきた甲斐があったというものだ。
アンコールはやはりハマらないところはダメだったが、全体の流れは流麗で出来としては悪くはなかった。
セットダウンのあと、いただいたプレゼント10いくつか、スーツ、ヴァイオリンを抱えて楽屋口へ。
次男がすぐに寄ってきて、妻に「ここ、ここ」と教える。
毎度申し訳ないが、プレゼントと楽器を持って帰ってもらう。
高校の同窓生7,8名、VPO幹事連、アンサンブル倶楽部の知り合いなど、待っていてくれたので、それぞれ会話をしてお礼を言う。
一番ほっとする週間だ。
こういう仲間がいるから自分も頑張れるんだと思うし、本当にありがとう、って言いたい。
それから打ち上げ会場へ。
ヴァイオリンのセクションで固まっていたが、徐々にいろいろなところへ遠征し、トラで出ていただいた高校の後輩の女性とも話ができた。
事務局長にも次回の曲の意見を求められたり、めまぐるしくいろいろな人たちと会話しているうちに1次会お開き。
体調を考えて帰ろうと思ったが、皆が「行くべし!」と言うので2次会にも参加。
高校の後輩のファゴットM君と隣になり、いろいろと歓談。
逆となりには今まで会話したことがなかったコントラバスの今回の実行委員長の女性とも、音楽についていろいろ語れた。
最後は2ndトップのSさんとお互いをねぎらい、VPOでも一緒ののだめことHちゃんともお話しし、2時会終了。
一正先生もずっと付き合って、「もう振らない」が最後には「また、いつか」に変わり、一同より大拍手。
いろいろあったが、いい雰囲気で収まった。
次回は11月。
さらにクォリティーをあげた演奏を目指したいと思った。
| ■2007/05/26 (土) ゲネプロ@クラッシック・スペース |
今日は9時半集合でゲネプロ。
9時過ぎにいくともう何人か来ていて、会場の人も15分早くあけてくれた。
9時半前にはセッティングが終り、リハOKの状態。
弦楽器で、アンコールの弦セレの通しと難所の練習を数回行う。
1ヶ所どうしてもはまらない部分があるので、なんとかしたい。
チャイ5は3楽章の中間部の練習。
これも落ち着いてやればいいのだが、せきたてられるようになって、1stから突っ走り始める。
抑制を効かせることが大切。
そうこうしているうちに一正先生が登場し、フンパーディンクから開始。
ホルンの主席がお休みという、またこの期に及んで、という感じだが、先生も事前に承知していたということで無事終了。
この曲は簡単なようでいろいろな要素を含み結構難しい。
チャイ5は、明らかに2週間前とは違うが、1週間前のさらなる緊迫感には及ばない感じ。
本番はもう少しテンションアップが欲しいところである。
まろ先生のシベコンは前回とは違い随所に独特の見得を切るような箇所が織り交ぜられ、聴きどころは満点。
ようやくどこでどうつけたらいいのかがわかった気がした。
2時過ぎに終了に、予定されていたパート練も中止となり、解散。
あとは明日の本番、気持ちをいいところに持っていきたい。
| ■2007/05/20 (日) オケ練@HZ 田野倉&一正先生 |
胃のムカムカ感はまだあるが、食事を最小限にして昼前に会社に出かける。
午後は広島交響楽団コンマスの田野倉先生の高弦練習。
実に細やかで具体的な指導で、楽器の扱い方により微妙なニュアンスがよくわかる。
3時間にわたるご指導で、難所のいくつかがだいぶ改善された。
プロのトレーナーの指導はやはりとても効果があり、大切な練習だと感じた。
2時間のインターバルがあり、また軽くおにぎりを食べて過ごす。
18時になり、前回かなりきつい調子でリハーサルをされた渡邊一正先生が登場。
ほんとにキャンセルされるかもしれないと思っていたが、そこはプロ、そのままフンパーディンクにいきなり入っていく。
この先生は言うことはきついが、それだけ音楽に真剣であり、その表情と手と指揮棒の動きを見れば、いかにそこに音楽が流れているかがわかる。
それが伝わったのであろう、今日になってやっとほぼ全員参加したメンバーが皆とても真剣である。
次のチャイコフスキーもほぼ全曲を通すことで「いいんじゃないですか。この調子を維持、いやさらに来週までレベルアップをはかれば、神様が降りてくるかも・・・」
確かに演奏していてもこれまでとは全く違い、熱く燃えた演奏で、驚くことには弾きながらも感動したことである。
そのあとN響コンマス、篠崎史紀先生が登場。
貫禄があり、オーラを発している。
シベコンは各楽章通しと部分練習で約1時間ちょっと。
今回はオーソドックスなソロを取られ、オケの状態を観察していたご様子。
来週のゲネプロではだいぶいろいろなことをされるようなので、それまでにオケはそれに確実につけて音楽を支えるように各人のさらなる練習が必要と感じた。
計6時間にわたる練習を乗り切れ、胃の違和感も収まってきた。
ひとつひとつクリアーしていこう。
| ■2007/05/19 (土) やはり無理だった |
午後はパート練習があるので、支度をして軽く食事をしたところ、吐き気に襲われ、練習を断念。
電話を入れて、横になって過ごす。
体力の限界値だったようだ。
明日は出られますように。
| ■2007/05/12 (土) オケ練@HZ 一正先生 |
今日は一正先生激怒の日で、最初から「2週間前と何も変わっていない」と厳しいお言葉。
チャイコフスキーも、シベコンもまったくダメで、「2週間前でこんな状態は信じられない!」とのこと。
確かにある種の慢心があるのかもしれない。
過去の演奏会でも直前までメタメタで、本番になるとシャキっとするという悪い意味での泥縄方式が、ついにこの時期まで引きずられてしまっているということだろう。
先生のおっしゃることはまったくそのとおりで、真摯に音楽に向かわない限り、音楽の神様は降りてこない。
といって悩んでいても仕方がない。
あと2週間、できる限りのことをやってみよう。
皆にもパート・リーダーとして伝達できることは全部前倒しで伝えて、心構えを微力ながら変えていこう。
そんなことを思いながら帰路に着いた。
| ■2007/04/28 (土) オケ練@HZ 一正先生 |
今日はフンパーティングとチャイコフスキー5番全曲のリハだったが、予定の40分前に終了。
先生は練習を長くやることを好まず、集中してやるのが効果的と考えているとのこと。
フンパーティングはまとまりをみせてきたが、細かい移り変わりの部分がスパっと場面転換できていない気がする。
8分の細かい動き、2拍3連のスムーズさ、最後の管の裏で動く細かい合わせなどまだまだ課題が多い。
チャイコフスキーは、音づらは弾けていても、音楽としての芯を常に持つことが大切で、これにはすごくエネルギーを要する。
さすがに先生はちょっとでも気が入っていないところ、音楽をしていないところを鋭く指摘し、音楽として磨いていこうとする。
相当心してかからないと、まったく空虚な張りぼてになってしまうと実感した。
少しでも楽器を弾く、スコアを読む、パート譜を読む、といったことを時間を見つけてやっていきたい。
| ■2007/04/21 (土) オケ練 渡辺秦先生 |
トレーナーの渡辺秦先生が大阪からシベリウスのヴァイオリン協奏曲の代奏の女性を連れてくる。
しかも、本番指揮者の渡邊一正先生も見学と称して来ている。
秦先生は「やりにくい」を連発しながら熱心に指導してくださった。
一正先生の「もっと本気でやる気がなければ、やっていても意味がない」とときおり渇を入れる。
シベリウスは何が悪いのかがソロが入ることにより明確になり、収穫の多い練習だった。
フレンチ・ボウで弾いてみたが、チャイコフスキーの細かい音符や、フンパーディングの滑らかさがよく弾けて、かなりこの弓に気持ちは傾いている。
| ■2007/04/14 (土) オケ練 相葉先生 |
本日は午後がオケの弦分奏の日。
トレーナーのA氏の指導で行う。
ヴァイオリンは1st,2ndとも10名以上の参加で多いが、中低域ヴィオラ以下が少ない。
しかし、ヴァイオリンは多くてまとまりがない感じ。
もっと個人練習が必要と感じた。
| ■2007/04/07 (土) オケ練;渡邊マエストロが登場 |
午後は会社でのオケ練。
今日は本番の指揮者、渡邊マエストロが登場。
厳しいの前評判からか、団員も緊張気味。
いきなりチャイコフスキー交響曲第5番全楽章を通す。
そこから、細かいところをひとつひとつ解きほぐし、音楽の表情、意味を考えさせる、という練習が続く。
結局細部の練習は1楽章だけで時間切れ。
次は「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲。
これも1回通してから細部を調整。
指摘されることは理にかなっており、音楽がぶよぶよしたものから身の引き締まったものに変貌していくのが弾きながらも感じる。
最後のシベリウスのヴァイオリン協奏曲はソリストがいないので、タイミングが難しいが、いくつかのソリストの弾き方の可能性をお話しされ、注意箇所を教えていただく。
練習後マエストロを囲んでの飲み会があり、行きたかったが体力温存のため帰宅。
| ■2007/03/31 (土) オケ練;渡辺泰先生の指導 |
午後は4時間会社でオケの練習。
この日は新日本フィルのフルート/ピッコロ奏者である渡辺泰先生の指導で、一応全曲の練習予定だったが、最後のチャイコフスキーの交響曲第5番は第1楽章で時間切れとなってしまった。
少しずつ曲が曲らしくなっていくのは体感できるが、まだまだ全体的にはおっかなびっくりの感は否めない。
これからどう積み上げていくが問題だ。
| ■2007/03/24 (土) オケ・パート練 |
午後は次回の定演のパート練習で、セカンド11名参加。
少しずつパート内で苦手な部分を一緒にやっていくので、効率がいい。
音程やリズムの違いのみならず、ニュアンスの違いも同じベクトルに合わせていけるのがこの練習の強みである。
| ■2007/03/23 (金) 新入社員修了式 |
本日は幕張OVTAで昨年度の新入社員の修了式が催された。
今回はコーディネートを任され、社長室はじめエグゼクティブの方々とのスピーチ内容の確認、開催場所との細かい折衝、会社のオーケストラの手配と自らも出演のため練習参加、合唱のピアノ伴奏と上長いわく「八面六臂」の活動で、なんとかつつがなく終えることができた。
会社の皆が役割分担を確実に行ってくれたチームワークの勝利であろう。
さすがに疲れがどっと出た。
・・・が明日も明後日も練習。
| ■2007/03/10 (土) MAHとIBMオケ弦練 |
午前中は修了式のためのヴィヴァルディその他の練習。
午後は次の定演のオケ練習、弦楽のみ。
| ■2007/02/11 (日) 室内楽演奏会@アプリコ小ホール |
朝9時半からアプリコ小ホールでステリハがあり、出かける。
ホールは音がよく響き、なかなかいい。
そのあとの最終練習まで時間があるのでいったん帰宅。
またバッハの練習をする。
午後1時から演奏会が開始。
我々の出番は最後の4時なので、オケ仲間の室内楽を楽しむ。
改めて感じるのは、室内楽のハーモニーの難しさ、音量バランス、リズム感。
オーケストラだと補完されあって素晴らしい響きになるが、室内楽は個人の力量がむき出しになるので、怖くもあり挑戦しがいもある。
普段聞けないみんなの演奏を聴くことができ、楽しかった。
と言っているうちに我々大所帯13人のムジカ・アンティカ・ハコザキの演奏。
ソリスト二人もそれまでの力を遺憾なく発揮し、アンサンブルもいい響きで支えることができた。
達成感のある演奏だった。
終了後は打ち上げ。
打ち上げに店が開いていないのでその隣にあるさくら水産で6人でさっそく乾杯。
結局その店には15分しかいないで移動。
予約の店での打ち上げはいろいろな人と話をし、修了式の演奏も我々の団体が演奏できるようネゴし、成果はあった。
2次会でホルンのジャズ好きでベースの人、チェロのトップの美しい女性で「ぜひ今年はジャズをやりたいので一緒にいれて欲しい」という方たちと盛上がり、来年はチェロ・カルテットで出演することが決定。
いろいろと収穫のある一日でした。
| ■2007/02/10 (土) 室内楽前日練習 |
午前中は会社で明日の室内楽演奏会の最後の練習。
ソリスト2人もかなり練習を積んだらしく、最初の頃とは段違いによくなっている。
バックもこのヴィヴァルディの曲にだいぶ馴染んできて、多分明日は大丈夫だろうという気がする。
| ■2007/02/04 (日) MAHリハーサル(3回目) |
午前中はレッスン課題のバッハ、ベートーヴェン、VPOの「四季」を練習し、午後は会社に室内アンサンブルの練習に行く。
もう本番は来週なのだが、Tuttiなので気楽に構えて家では練習せず、合奏練習だけで本番に臨むことになりそうだ。
アンサンブルはやるたびによくなっているが、まだまだテンポの揺れや、合わせの不揃いなどいくつか難点がある。
皆で、気が付いたところを言い合って直していったので、最後には大分まとまってきた。
練習が終ったら、昨日の疲れもあり、電車で熟睡して帰宅。
| ■2007/01/21 (日) MAHリハーサル(2回目) |
昼前からは会社の室内楽コンサートの練習があり、またヴァイオリンを担いでお出かけ。
少し前に着くと、ソリスト2人が、本日お願いした弦楽器トレーナーのプロの先生に指導を受けているところだった。
ヴィヴァルディ「調和の霊感」Op.3-8で、2つのヴァイオリンのための協奏曲だが、自分はTuttiなので、とても気が楽。
ソリストに、参考用に、とこの曲の演奏映像のDVDを渡すと感謝される。
練習が始まるが、最初の通しは非常に不揃い。
先生がチェック・ポイントを指摘しながら、少しずつ手直しをしていく。
やはりプロの方は的確なアドヴァイスがすぐに出てきて、効果もすぐに現れる。
合奏とは相手の音、全体のバランスを考えながら、その中で自分のベストの音を出していく、ということがここ3年クラシックをやってきて少しずつ実感としてわかってきた。
2時間後には最初とは別物のようにいい演奏になった。
本番に向けてもこうした創造性を常に持ちながらやっていきたい。
| ■2007/01/13 (土) 会社の室内楽練習など |
そのあと10時から2時間会社で室内楽演奏会の練習があり、出かける。
曲はヴィヴァルディの「調和の霊感」から8番コンチェルト。
1stのTuttiなので、これはある意味で楽だ。
予定より15分ほど伸びて練習終了。
メンバーで昼食に行く。
ヴィオラ主席のMさんが高校が同じ学区域で、私の高校の後輩と知り合いだと聞き、偶然にびっくり。
いろいろ皆と話しができてよかった。
| ■2007/01/12 (金) キックオフ・ミーティングでオケ鑑賞 |
肉体的なダメージは今日は出ず、一安心。
午前中は幕張の会社のホールで、五反田ゆうぽうとからのキックオフ・ミーティングの生中継に参加。
開始は我がオーケストラの「フィガロの結婚」序曲。
快調な滑り出しだ。
事務局長Sさんの指揮ぶりも板についている。
社長の方針スピーチなど式次第が続き、最後に「威風堂々」を合唱入りで演奏。
一昨年の定演の第九で社内応募で集まった方たちで社内合唱団もできてしまった。
素晴らしいことである。
今年は練習に参加できなかったので、本番参加を見送ったが、たまには外から自分の所属しているオーケストラを聴くのもいいものだな、と思った。
| ■2006/11/26 (日) IBMオケ 第9回定演@すみだトリフォニーホール |
いよいよ定演当日。
ステージ設営・受付設営のスタッフに任命されたので、集合時間より1時間はやい9時に、すみだトリフォニー・ホールに着く。
主に受付周りの設営を行う。
三々五々団員が集まり、10時過ぎからステリハ。
ステージから眺めるホールはいつみても気持ちがいい。
3階席などはるか彼方という感じである。
ステリハはピックアップしながら全体を通し、12時半に終了。
漆原さんがステージに残り、カデンツァを通すところを袖口で眺める。
いよいよ会場の時間となり、お客さんが続々と入場。
みるみる席が埋まっていく。
今回も盛況なコンサートとなりそうである。
楽員の入場、コンマスの入場、チューニングに続いて手塚先生の入場。
大きな拍手のあと、一呼吸おいて「オベロン序曲」。
練習時はなかなか決まらなかった最初のホルンの一発が見事に出て、それからはスムーズに曲は流れる。
オケのサウンドがホールに響いているのがステージ上からもわかる。
いい演奏ではなかったかと思う。
セッティング・チェンジのあと漆原さんのチャイコン。
全体的に柔らかいサウンドのオケに乗り、漆原さんの美音が響く。
ところどころのアコーギグもリハで承知なのでオケも手塚先生の変幻自在な棒についていく。
確かに全体的に抑えた音量で、爆発的な演奏を期待された向きには肩透かし気味だったかもしれないが、典雅な演奏が出来たのではないかと思う。
休憩後はブラームスの交響曲第2番。
やはり出だしの速い感じは練習時と同じでいささか落ち着くのに時間がかかる。
途中からは演奏も安定し、第1楽章の終結部ののどかな寂しい感じは出せていた。
第2楽章はやはり最初なりすぎかなと思いつつ、ブラームスの切ない旋律が搾り出されていくうちにオケもひとつとなり寂寥感をたたえつつ終える。
第3楽章は冒頭のオーボエのOさんの妙技に酔う。
なんと豊かで歌のある演奏なのだろう。
細かい弦の刻みは個人的には本番が一番うまくイメージどおりに弾けた。
後ろ髪を引かれつつ第3楽章が終り、第4楽章へ。
は・や・い!
これまでのどの練習よりも速いテンポで突き進む。
途中からはほとんど爆演という感じ。
弾いていて、多少雑になるのはわかるが、これはもう疾走するしかないという感じでとにかく輝かしい終結部を大きな乱れもなく迎えることが出来た。
終って「ブラボー!」と大きな拍手。
ライブならではのスリル感があったのかもしれない。
演奏を終って立ち上がって客席を向いているとき、肩で息をしたのは初めてだった。
アンコールは一転してシューベルトのロザムンデ間奏曲第3番。
クールダウンする感じでコンサートは終了した。
終演後は楽屋口で、家族に楽器、衣装、プレゼント(全部で9つも頂いてしまった)を手渡して、身軽になり、アンサンブル倶楽部の人たち、新宿高校の1年のときの同級生の女子6名などと話すことが出来た。
わざわざお越しいただきありがたいことである。
つい話が弾んでしまい、気が付いたら打ち上げ開始の時間が迫っているので急いで会場へ向かう。
座敷形式の会場で、演奏後のハイ・テンションを引きずりつつ宴会となる。
今回はエキストラでいろいろと連絡を取り合ったお世話になった方たち、コンミスのAさんといろいろ会話が出来、また漆原さんとのツーショット写真などが取れてとても満足。
今回も練習開始から前半は体調が安定せず、また欠場かな、と思うときもあったが、後半は持ち直しほとんど出席でき、本番も出演できてよかった。
段々と団員の知り合いも出来てきて、室内楽とか他の活動でも一緒に演奏が出来そうで楽しみである。
とりあえず今年のコンサート出演は一段落。
| ■2006/11/25 (土) 9th定演 ゲネプロ@HZ |
午前中に次男のレッスンを見てから、11時過ぎに箱崎でのゲネプロに出かける。
泣いても笑っても今日が最後の練習。
最初にチャイコン、漆原さんが再び登場し、全体を合わせる。
ソロを引き立たせるようオケの音量を一段階落とすように、トップから指示があったがちょっと落としすぎかなという感じ。
とりあえず、ソロとオケが噛み合わない部分も多少解消され、何とか形となる。
明日は本番の魔法でさらにいい演奏になればいいなと思う。
オベロンはかなりダイナミックスが出てきて、旋律の受け渡し、和声の移行などもスムーズになってきた気がする。
あとは熱くなり過ぎず、勇壮かつテンポ感を損なわない演奏が出来ればいい出来になると思う。
ブラ2は、個人的には第1楽章の出だしのはやめのテンポが、速いな、と感じてしまうところ、第2楽章の出だしの低弦のメロディーと管楽器群の音が分厚すぎて明瞭感に欠ける所、第4楽章の出だしの不安定さなどが気にかかる。
ブラ2は難しい。
第4楽章の輝かしさはとても好きなので、明日はなんとかそれをステージから客席に伝えられればと思う。
| ■2006/11/23 (木) 9th定演 オケ練@豊洲 |
本日から明日は休暇を取って4連休。
だが、3日間は会社のオケ(最後の休みの日が定演)で、休養というわけにはいかない。
今日は朝からブラ2、オベロン、チャイコンの復習。
ここまで来てもやはり弾きにくい部分は残っているし、ニュアンス的に余裕を持って弾けない部分も残っている。
あとは残る2日間で本番までにどう持っていくかが問題。
今日の練習は夕方6時から豊洲の文化センターで10時まで行った。
漆原さんはいらっしゃらないので、オベロンとブラ2の練習。
音楽ホールではないので、音響的に残響が乏しく、ダメな部分はよくわかるが、いい部分を出すのが難しいという感じだった。
手塚先生の棒は見ているとやはり音楽が見えてくる。
逆に難しい部分で譜面にかかりっきりになると音楽自体の質が低下するのもよくわかる。
できるだけ指揮を見るようにしてしっかりと音楽を作っていきたいと思った。
楽器の方は低音のG線が薄い感じがして、やはりオブリガートあたりにしようかなと思うが、今回は間に合わないのでオリーブのEと残りはドミナントで乗り切りたい。
| ■2006/11/18 (土) オケ練 with 漆原朝子さんSolo合わせ |
今日は通常の2時間遅れ、15時より練習。
前半は手塚先生の指揮でブラ2の1,3,4楽章とオベロン序曲。
さすがに本番も迫ってきて、ほとんどのメンバーが出席。
ブラ2の第3楽章に不安が残るが、次回の練習で仕上げましょうということで、後半はチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲。
ソリストの漆原朝子さんが初めてお見えになり、第1楽章から合わせていく。
やはりプロはすごいなぁ。
どこから入ってもピタリと決まるし、自然とオケを引っ張っていくようなソロを奏でる。
プロとアマの違いは造形の違いだな、と感じた。
ピタリとした自分のテンポがあって、それが揺らがない。
2時間の予定が1時間で終り、はやめに終了。
ゲネプロにも来てくださるそうなので、また楽しみである。
| ■2006/11/11 (土) オケ練@HZ 初の手塚先生のリハ |
今日は午前中セカンド・ヴァイオリンのパート練習、午後は手塚先生のTutti練習だった。
午前中のパート練習はほぼ全員が集まり、しゃかりきにやるのではなくトップが確認の意味でピックアップしながら行い、午後の練習のウォーミングアップとしてはちょうどいい内容だった。
午後は自分は初めて手塚先生のリハーサルに参加した。
喉がご不自由で、指示はコンマスが補足しながら伝えて進められていくが、棒を見ていると何を求められているのかがよくわかる。
だから、とてもいい呼吸で、音楽を感じながら演奏できる。
これが、指揮者というものなのだな、と改めて感じた。
オベロン序曲もなかなか突っかかって弾けなかったところも流れるように弾けるようになったし、チャイコンもダイナミックスの付け方、配分などがよく理解できた。
最後にブラ2の第2楽章のみ練習したが、ブラームスの寂寥感がにじみ出てくるのを感じた。
とても充実した気持ちで練習を終えた。
| ■2006/10/28 (土) オケ練@HZ |
先週はダウンして出席できなかったので、今週は体調を整え参加。
今日のトレーナーの先生は厳しいと評判のO先生。
9月の合宿ではだいぶしごかれたらしい。
今日も、ヴァイオリンは一人弾きさせられるかものうわさに恐れたのか、2名が直前キャンセル。
実際に指導を受けてみると、たしかに細かくいろいろなところを指摘して、何度もやり直しをさせられるが、それは出来ていないから当然で、厳しいのではなくどうやったら本当に音楽になるかを真剣に指導してくれるいい先生だと思った。
おかげで、考えなければいけないところ、考えないでも弾けるように覚えてしまうところ、ブロック化して覚えれば非常に弾きやすくなるところ、こういった方法を4時間の中で数多く学べたのは大収穫。
次回の演奏会に関しては、あとは自己の細かいテクニックを必要とする部分練習と、常に周りとのアンサンブルを成立させるための回りを聴く意識、深い呼吸で音楽を捉える全体感覚、これを無意識にできるようになれば大丈夫なのではないかと思える自信がついた。
とにかく体調を崩さず次回は出演したい。
| ■2006/10/14 (土) 2ヵ月半ぶりのオケ練 |
午後は2ヵ月半ぶりに会社のオケ練に出席。
今日は弦楽器の分奏で、ブラ2の1曲のみ。
ほとんどVPOに時間がとられていたので、細かいところがまだまだ個人的にはダメ。
しかし、曲はよく知っているので、テンポのゆっくりなベーム盤のCDに合わせ事前予習をしていく。
トレーナーの先生は前回のときも的確な指導をしていただいた方で、曲の部分の背景、例えば
「ここはハンガリアンだから勇壮に!」とか「ホルンのブレスに合わせた息継ぎのような弾き方で」とか、「ここは最終的なフォルテに向かうためのフォルテであることを意識してもう少し凝縮したフォルテで」など、曲全体の中での連関をよく把握した練習でとても納得させられた。
次回からは本格的に全体練習に入っていくので、他の曲も予習怠りなく臨みたい。
| ■2006/07/29 (土) 久々のオケ連とヴァイオリン会 |
今日は第9回定演の第1回目の合わせの日だ。
3ヶ月ぶりに会社のカフェテリアでの練習。
チャイコのVn協奏曲、オベロン序曲、ブラームスの交響曲第2番の順で合わせる。
指揮は団員持ち回りで、3人のリーダーが行う。
チャイコは伴奏は当然だが、ソロに比べてなんと楽なんだろう、という印象。
しかし、ソロがいないと逆に数えていなければならないので気を抜くと次のところに行っている。
オベロンは細かいパッセージは練習すればなんとかなりそう。
ブラ2もよく知っている曲なので、細かいところをちゃんとさらって、はやく曲の表現の細かいところに目を行き届かせたい。
4時間の練習後はヴァイオリンセクションで14名ほどが参加した食事会・飲み会(ヴァイオリン会と称している)に参加。
侵入団員姪の歓迎会もかねる。
セカンドのトップサイドを弾いている女性と席が隣になりいろいろと話が弾む。
こうした交流で皆の士気が高まりそうである。
次回こそはアクシデントなく出演したい。
| ■2006/06/20 (火) 譜面係 |
会社のオケから連絡が来て、来年はヴァイオリンのパート・リーダー(トップではなく幹事みたいなもの)を引き受けてくれないかという打診が着たので了解する。
手始めに今年後半の定演のヴァイオリンのパート譜の管理、配布などの仕事をやることになり、セカンド・ヴァイオリンのパート譜が送られてきた。
ファースト・ヴァイオリンの楽譜係は同じ部門の女性で、いろいろコミュニケーションがとりやすい。
次回の定演は11/26@すみだトリフォニーホールで曲はウェーバーの「オベロン」序曲、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(ソリストは国際的に活躍されている漆原朝子さん)、そしてブラームスの交響曲第2番がメインだ。
これまた好きな曲ばかりで嬉しくなってしまう。
今度は体調を整えて絶対に乗るぞ、と誓う。
さっそくスキャナーでパート譜をPDF化し、セカンドのメンバーに配布。
最初の練習が待ち遠しい。
| ■2006/05/21 (日) 定演の日 |
ああ、今日は定演の日だ。
しかし入院。
無念だ。
| ■2006/05/13 (土) 不調 |
GW後半から胸の不調で病院に行くと気管支喘息との診断。
安静を命じられる。
明日のオケ練出席は断念せざるを得ない。
なんとか本番までには回復したい。
| ■2006/05/07 (日) オケ練 |
今日は11時から18時まで会社でのオケ練。
幻想交響曲、クラコンを主にやる。
さすがにくたびれたが練習もあと1回。
がんばりたい。
| ■2006/04/22 (土) 第8回定演 弦分奏 |
本日は午後から弦の分奏があった。
相葉さんという方がトレーナーで、実に細かく具体的な指導をしていただき、どこをどのように自己練習したらいいかというポイントをつかむことができた。
特に普段はあまり指摘されることのないセカンド・ヴァイオリンのニュアンスや弾き方にまで細かく指示をいただき、なんとなく表面的に感じていた今回の一連の練習の中で一番ためになった気がする。
プロフェッショナルである。
練習後はヴァイオリン、ヴィオラの女性陣と一緒に電車で帰る。
やはり、今日のトレーナーの人はよかった、という話になった。
みんな思うところは同じなんだな、とやや安心。
| ■2006/04/15 (土) 第8回定演 オケ練 |
今日は午後から横川先生の練習があった。
内容は幻想交響曲第1、4,5楽章とアンコールの「ラコッツィ行進曲」。
アンコールは初見演奏だった。
幻想交響曲は難しい箇所が各楽章にちりばめられており、安心できる楽章がない。
今回はパート練習がないままに終わりそうだが、こうした難所をアンサンブルする機会が少なかったのは残念である。
しかしあと1ヶ月あまり、なんとか練習時間を見つけて自分なりに納得のいく演奏がしたいものだ。
| ■2006/04/08 (土) 第8回定期演奏会練習 弦分奏 |
午前中は次男のレッスンをみたあと、会社のオケ練に出かける。
今日は弦の分奏で、モーツァルトとベルリオーズのみの練習。
モーツァルトはだいぶ感触が掴めてきていて何とか形になってきた。
ベルリオーズはなかなか難しく、第1楽章、第5楽章に超難関箇所があり、ここを克服するには指で覚えこんでしまうしかないかなというところである。
しかし段々全体像がわかってきたので、練習が楽しくなってきた。
| ■2006/04/02 (日) オケ練@お台場 |
11-18時まで会社でオケ練の予定だったが、カフェテリアが使えないことが判明し、練習会場が台場区民会館に変更。
時間も13-17時に短縮。
しかしあっという間に代替会場を見つける組織力には驚かされる。
今日の練習はセカンド・トップがお休みなので、仕方ないのでトップ横に座らされる。
トップ代理の人は途中で「胃が痛くなってきた」と青ざめる。
しかし、指揮者の近くはいろいろなことが伝わってきて勉強になる。
横川先生も根気よく指導してくださる。
今日の収穫はドビュッシーの曲がだいぶ見えてきたことで、これはいい方向に行くかもという感触をつかめたことだった。
帰りは雨が降り、会場に直結しているゆりかもめで帰宅。
| ■2006/03/25 (土) オケ練;高弦(ヴァイオリン、ヴィオラ)分奏 |
午後からオケ練。
今日は高弦(ヴァイオリン、ヴィオラ)の分奏でトレーナーの尾花さんの指導の下4時間練習する。
モーツァルトのしっかり弾かなければならない部分。
その弾き方、ニュアンスの出し方などを教わる。
ドビュッシーはソロがいないとあまり効果がないのですぐ終り。
幻想交響曲は難しい部分を20回も弾かされ、否応なく弾けるようになる。
地道だが確実な方法だ。
入団して1年、知り合いも増え毎回練習が楽しみである。
| ■2006/03/18 (土) 第8回定期演奏会練習 厄日? |
オケの練習に出かける。
時間的に余裕で30分前に着くな。
今日は横川先生の初めてのリハだし楽しみだな、なんて呑気に構えて大手町で乗り換えようと思ったら、「財布がない!」
バッグもポケットも全部探したがどこにもない。
さっそく駅の忘れ物センターに飛び込み事情を説明。
すぐに各所に対応してくれるがそう簡単には出てこない。
「あと1時間くらいしたらセンターに情報が集まってくると思いますのでそれまで待ってください」と言われ、とりあえずオケのリーダーと家に連絡し自宅に戻ることにする。
その途中乗換駅で念のためセンターに連絡すると、なんと王子の駅に届けられているとのこと!
急いで引き返し王子駅へ行き無事財布が戻ってきた。
お金もカードもすべて紛失していないでほっとする。
届けた方に御礼をしたいがとくに名乗らなかったとのことなので仕方がない。
まだ運には見放されていないな、と思いオケの練習に向かう。
後半の幻想交響曲に間に合った。
リーダーの人は「それは本当によかったですね」と言うので「ご迷惑をおかけしました」ということで一件落着。
横川先生は前に一度代替指揮でリハを振っていただいたことがあるが、まだまだオケの各パートが譜面を読みこなしておらず少しずつ進めていく。
2時間のうち1時間以上第1楽章に費やし、休憩なしで4,5楽章、最後に3楽章の冒頭でこの日は終り。
しかし、いろいろなことがわかり参加できてよかった。
次回が楽しみである。
オケ連が終りセットダウンしているとクラリネットの人が話しかけてきて、この日記を見つけました、と言う。
そして「昨年の暮れ池辺晋一郎さんの会に出席しましたか?」と聞くので、「ええ」と答えると、「リハ会場から会の会場に移動したとき先輩クラリネットのTさんも同乗していませんでしたか?」そういえば7878おじさんの車に先輩二人とも一人面識のない女性と5人で移動したことを思い出した。
「その女性はウチのかみさんなんです」「エーッ!」というまたしても狭い世間。
奥さんは自分と同じS高校の4代下のクラリネットだそうだ。
いやぁ、そうと知っていればもっと話できたのにとちょっと残念。
なんか厄日かと思っていた日が最後に奇遇な話で報われたという感じ。
晴れてぐっすりと眠ることが出来た。
| ■2006/03/17 (金)修了式 |
朝少しはやく起きてピアノとヴァイオリンの練習をする。
今日は両方の楽器を弾かなければならないので最後まで気が抜けない。
仕事で楽器が弾けるというのはこの上なく幸せなことではあるが。
最初オフィスによってからと思ったが、強風のため京葉線が遅れに遅れ、直接OVTAの会場に行く。
まだ控え室にはオケ・メンバーは来ていない。
最初にステージで合唱「贈る言葉」の練習。
大ホールにも思ったより声は響き、何とかいけそう。
そのあとオケのリハ、ピアノからヴァイオリンに楽器を変える。
まずBGM用の「カノン」「主よ人の望みの喜びよ」「水上の音楽」「ユダス・マカベウス」を練習。
結局3回の練習のうち1回しか出られなかったが、まあ、曲は知っているのでなんとかこなす。
記念演奏の「クリスマス協奏曲」は1月の室内楽演奏会に続く2回目の演奏。
メンバーもだいぶ曲に慣れてきていい出来になりそうだ。
昼は数人のメンバーで外にパスタを食べに行き、いろいろ喋りながらランチを楽しむ。
午後になり修了式開始。
まずは緞帳の裏にスタンバイし、表彰式などでのBGMを進行係りのキューに従い演奏。
無事終えて帰ってくると、「定演より緊張した!」というメンバーの発言に皆大爆笑!
次の出番は緞帳が上がり修了式の記念演奏コレルリの「クリスマス協奏曲」。
2度目ということ余裕があるかと思ったが、やはり人前というのは緊張する。
第2楽章で1箇所自信無げに入ってしまったのが悔やまれるがそれ以外は全体的にいい演奏だったのではないかと思う。

第二部は、日本IBM管弦楽団による記念演奏で始まりました。曲目はコレルリ作曲「クリスマス協奏曲 ト短調 作品 6-8」です。御子の誕生を祝うこの曲が、研修を終え真の社会人として新しく生まれたばかりの出席者に贈られました。(会社HPより)

最後にインストラクター合唱団による「贈る言葉」の三部合唱が基礎研修を修了した皆さんへの餞として披露されました。(会社HPより)
| ■2006/03/11 (土) 第8回定期演奏会練習 午後弦練 |
今日は午後からオケ連なので午前中練習をする。
「幻想」はフィンガリングは大体入れてみたが、まだまだインテンポでは弾けない。
ドビュッシーはスコアを追うのが精一杯。
クラコンはまあまあ弾けそう。
ということで午後は会社の練習所に出かけていく。
今日は弦だけでの譜読み兼合奏なので、人数もそんなにいない。
オケを紹介してあげた新入社員の女性も今日が初参加で、緊張の面持ち。
でも10年前に市民オケで「幻想」は弾いたことがあるそうなので、大丈夫のようだ。
最初のモーツァルトは大体通るが、細かい引っかかりそうなリズムのところはやはりひっかかる。
ドビュッシーはトップの人が指揮をしてくれたので数えていれば入れるが、まだまだ音楽以前の問題。
「幻想」は全楽章を通すが、管がいないのでなかなかむつかしい。
| ■2006/01/21 (土) 室内楽演奏会@目黒区民センター |
 雪の中会場入り
雪の中会場入り
ああ、雪だ・・・
朝起きたら天気予報どおり夜中のうちに雪が降り積もっている。
今日は会社のオケの室内楽演奏会。
25年位前に高校のOBオケで出演したことのある目黒区民センターホールで行われる。
9:30から練習開始なので、8時半過ぎに出る。
目黒からはタクシーに乗る。
会場につくともう数名自己練習を始めていた。
こんな天気でお客さんが入るのだろうか?と思いながら自分のユニットの練習に備える。
その時、コンマスの人が体調不良なのでリハは来れない旨連絡が入る。
仕方がないのでコンマス抜きで控え室で練習。
それからステリハ。
雪はこんこんと降りつづけるが、お客様もぼちぼちこの雪の中を入り始める。
ありがたいことだ。
 個人練習
個人練習
1時半になり本番が始まる。
我々は第2部の出演なので、ようやく到着したコンマスを中心に控え室で最後の確認。
そしてステージへ上がる。
全体にあまり合わせの練習をしていないので多少の不安感はあったが、コレルリ「クリスマス協奏曲」最初の音がきれいに鳴り響いた。
あとは流れるように進む。
このオケの人たちは本番に強いようで、今回の曲も本番が一番良かった。

自分の出番が終ってからはステージで他の人の演奏を聞く。
体調不良のコンマスは全部で4つ掛け持ち、特にバッハの無伴奏ソナタ1番からの第1・2楽章はよくあの難しい曲をあそこまで弾けるなぁ、と関心。
また全日本管楽器コンクールでここ数年第1位のオーボエ奏者Oさんのドラティ作曲の無伴奏の「5つの小品」は思わず引き付けられた。
他にカルテットやトリオなど様々なユニットでそこそこの水準。
次回は自分もユニットを結成して出てみたいなぁ、と思った。
打ち上げではそのオーボエの人と席がとなりになり、実は高校のクラスメートで今はプロのオーボエ奏者兼指揮者のMさんとオーボエの先生が同じ同門であったことを聞き、お互いびっくりする。
あとこれまで話したことのなかったチェロの女性陣ともいろいろ音楽の話で盛り上がった。
女性でもクラシックにすごく詳しい人もいるのだなぁ、と感心。
なかなか楽しい一日だった。
帰宅して何かビデオでもみて寝ようとしたら・・・そこから記憶がない。
翌日妻に聞いたら、ベッドの上でリモコンをTVの方に向けながら布団の上で眠り込んでいたそうだ。
体の向きを逆転させて布団をかけてくれた妻に感謝。
| ■2006/01/14 (土) 室内楽&ドッペルのダブル練習 |
今日は夕方から会社の室内楽コンサートのための最後の合奏練習とS楽器のコレギウム・ドッペルのユニットの練習が続けてあり、箱崎→川崎への移動を含め5時に出て10時終了とハードなスケジュールだった。
室内楽のコレルリの「クリスマス協奏曲」は前回の練習が出られなかったが、ボーイングを決めておいてくれたので一安心。
しかし、伴奏部分は数えてないと落ちるので気が抜けない。
川崎へ移動のため1時間ほどで退席。
移動は雨・強風の中を楽器を抱えているのでなかなかきびしい。
なんとかたどり着くがへとへとになる。
すでにNさんと7878おじさんは先行してデュオの練習が終了していた。
チェロのKさんが遅れて到着し、練習開始。
第1楽章は通るので、中身を議論しながら進める。
Nさんの1stと私の2ndで各々の表現が食い違うので難航する。
部分と全体にわけイメージを言葉として伝えるが、なかなかぴったりとはいかない。
音符を弾くことと音楽を造っていくことの違いを痛感する。
第2楽章も同様で、私は決して一昔前の重厚なスタイルを否定するものではないが、この楽章は澄んだイメージを持っているのでガリガリとやるのには同意できない。
・・・とまあ、こんな議論をしているうちに時間はあっという間になくなり、3楽章を少しだけあわせるが、途中で合わなくなり終了。
曲へのコンセンサスというものを取らないといけないな。
次回はそれを踏まえてやっていきたい。
そういえば、ドッペル練習の時、松脂を落っことしてバラバラになり使えなくなった。
なんとなくツイてない一日。
| ■2006/01/06 (金) ニュー・イヤー・キックオフでの演奏 |
 オーケストラ・ピットでの演奏風景
オーケストラ・ピットでの演奏風景
結局4時間半ほどの睡眠で起きて、軽く朝食を取って出かける。
妻も付き合ってくれて食事も作ってくれご苦労様である。
まだ真っ暗なうちに国際フォーラムに着くが、入り口がわからず迷っているとオーボエのN氏と会い、彼も同じく迷っていたらしく二人で探してなんとか見つける。
メンバーも三々五々集まり、定刻どおり最終リハーサルの開始。
サウンド・チェックの人がホールの各所で聞いていてくれてバランス調整を行う。
曲はワーグナーの「マイスタージンガー」第1幕への前奏曲(短縮版)、BGMとしてモーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」(弦楽のみ)、最後はシュトラウスの「ラデッキー行進曲」である。
途中O社長も現れ、「よろしく!」と壇上より激励。
リハは概ねうまくいき、控え室で待機。
9時半から開始されるので5分前にピットに再度入る。
ミーティング会場は4000人のキャパシティーだが、2階席までだいたい埋まったようだ。
冒頭のワーグナーは定演でやったのでメンバーも余裕を持って演奏。
大きな拍手を受けた。
そのあと米本社のP会長が登場、これが予定以上に延びる。
しかし、生で間近で会長の姿を見れたのはなかなか興味深かった。
もっと太っている方かと思っていたが、非常にひきしまった感じで、熱意を持って語り、来場者の質問に答えているのが印象的だった。
そのあとの表彰タイムでアイネクを演奏。
時間が押していたので第2楽章途中で終了。
最後のラデッキーは2回半の繰り返しでピタリと終了。
まずまず成功した。
こうした会社の行事で演奏できることは、段取りを考える人の苦労は大変だと思うが、自分にとっては少しでも貢献できてよかったなと思った次第。
終了後上司からメールがじゃ入り、「オーケストラは会社の誇りです。次は仕事でがんばってください」と嬉しいようなプレッシャーのような内容だった。
期待に沿うようがんばりましょう。
| ■2006/01/05 (木) ニュー・イヤー・キックオフのリハ |
今日も一日仕事のあと、夕方いったん家に戻り楽器を持って、有楽町の国際フォーラムへ行く。
明日の午前中に全社のキックオフ・ミーティングの演奏のためなんと夜9時から11時までリハーサルである。
8時過ぎに行くとかなりのメンバーが集まっており各自の音だしチェックに余念がない。
結局ステージの準備が遅れ、30分押しでスタート。
通しのみの練習となったが、オーケストラ・ピットに入って演奏するのは初めてなので、なかなか目新しく面白かった。
しかし、すごく寒い夜だったので、帰りはぶるぶると震えながら帰った。
家に帰ると12時近くになる。
明朝は6時半集合。
起きれるか心配だ。
| ■2005/12/23 (金) ニュー・イヤー・キックオフのオケ連 |
世はクリスマス・イヴ・イヴ。
体調はあまりよくないが、午後会社のニュー・イヤー・キックオフのオケ連に2時間行って来る。
マイスタージンガー、アイネク、ラデッキーということで、やはりアイネクの2楽章が難しい。
しかし、前の方に座っていると音楽に参加している気が高まり、周りの音もよく聴くようになる気がする。
あとは年明けの1回で本番だが、できる限りちゃんと準備して臨もうと思う。
| ■2005/12/17 (土) ニュー・イヤー・キックオフの練習 |
今日は午後からニュー・イヤー・キックオフの練習が会社であり、参加した。
曲は「マイスタージンガー」前奏曲、「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」、「ラデッキー行進曲」の3曲。
国際フォーラムのオケピットに入って演奏するそうなのでいつもとは違う横長の配置。
今回は2ndのトップ・サイドを弾くことになった。
参加人数は半数ちょっとだったが、さすがに「マイスタージンガー」は定演の余韻が残っており、皆いい音を出していた。
「ラデッキー」も初見だが大して難しくなく自分のパートに関して言えば問題なし。
「アイネク」は2・3楽章を練習したが、第2楽章が難しい。
音符的にではなく、合奏表現が千差万別で散漫なのである。
コンミスとトップが相談をして方向性を確認。
少しよくなるが、次回の練習でどこまで向上するか。
全体で2時間の練習だったので身体は楽。
帰りは1月の室内楽演奏会で同じユニットで演奏するヴィオラの女性と電車でいろいろ話しながら帰ってきた。
来年の定演は「幻想交響曲」かもしれないという噂だそうだ。
| ■2005/12/11 (日) クリスマス協奏曲 |
午前中は10時に会社のカフェテリア集合で、来年の1/21の室内楽演奏会の初練習。
曲はコレルリの「クリスマス協奏曲」で、2ndのTuttiパートの入れさせてもらった。
2ndのソリストがこないのでコンマスのU氏が代弾きしたが、やはりうまい。
曲のアーティクレーションとかが初見でもすぐに浮かんでくるようで、となりで弾いていて感心した。
バロックは気を抜くとどこを弾いているか解らなくなるので緊張が強いられる。
しかしきちんと合ったときはとても気持ちがいい。
このユニットはあと2回で本番だが、みんなうまいので大丈夫でしょう。
| ■2005/11/26 (土) 第7回定期演奏会 第九@ミューザ川崎 |
| 2005年11月26日 第7回定期演奏会 (ミューザ川崎シンフォニーホール) |
| 指揮:飯守泰次郎 独唱 ソプラノ:吉田恭子 アルト:池田香織 テノール:小貫岩夫 バリトン:成田博之 ベートーベン 交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱」 ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 第1幕への前奏曲 |

いよいよ本番の日である。
舞台設営係なので13時前にミューザ川崎の楽屋入り口に行く。
三々五々団員がやってくる。
舞台設営は初めて手伝ったが、合唱団の立ち位置を円形に段組していき、座るためのイスを設置。
これだけで結構時間がかかり、管楽器・打楽器の雛壇もやらなきゃならないのかぁ、と思っていると、それは自動で上昇してくるのでほっとする。
リハーサルが14時から始まり、前夜の残響のないホールとは違い、たっぷりの残響音に上手くなったように感じる。
飯守先生は最後まで改善できるところは念を入れて練習し、言葉で伝える。
上手くいきそうな予感がする。
会場となり、楽屋裏手の大モニターで先生のプレトーク(ピアノを弾きながら第九を解説)をみる。
客席が次第に埋まっていくのも確認できる。
前回のような緊張感はあまりなく、ここまでこれたのだからなんとか最後まで上手くいって欲しいと思う。
開演時間となりステージに出て行く。
家族は予め教えておいた席に陣取っているのが見える。
最初の「マイスタージンガー前奏曲」は飯守先生の呼吸に皆が合わせ最初の音が鳴る。
ヴァイオリン・パート鬼門の飛びつく高音の部分も決まり全体に細かい描写が表現できていたように思う。
幕開けにふさわしく華々しく最後の音が響き渡る。
これで聴衆のハートを掴めたのではないかな、と思う。
休憩後いよいよ本番の第九。
壮大な第1楽章の滑り出しの6連符の霧の中から1stヴァイオリンのメロディーが浮かび上がってくる。
葛藤・暗黒の中からかすかに射してくる一瞬のなごみ、厳しく恐ろしさを感じる音楽だ。
とにかく巨大な音楽はこれからの展開を暗示させる響きで終結。
第2楽章は映画「時計じかけのオレンジ」のなかで「自殺のスケルツォ」と呼ばれていた無機質で人を不安に陥れるような音の並びが延々と続く。
懸念していた2ndヴァイオリンから順に始まるpの刻みはコントラストがきちんと描けていたように思う。
中間部の場違いだが懐かしいトリオ部分も牧歌的に響く。
また無機質なスケルツォが戻ってきて唐突に終る。
第3楽章は天上の音楽で、これも長い楽章なのだがあまりに美しいので聴いていても弾いていてもあっという間に終ってしまう。
木管も1stも好調で、メロディーが流れるように受け渡されていく。
最終楽章への誘いをみせる最後の刻みで音楽は盛り上がり、名残惜しそうに終る。
そのまま間を置かずアタッカで第4楽章に突入。
リハより速いテンポで疾風怒濤といった感じ。
チェロ・バスによる前3楽章の否定のあと「歓喜の歌」のメロディーがでてくる。
リハよりいい音程で心がひとつになっている。いいぞ!チェロ・バス。
ヴィオラがメロディーに乗り、ヴァイオリンがさらに重なっていく。
管が入り最高潮に達し、突如急雲風を告げ冒頭の不協和音がなだれ落ちる。
いよいよ歌の登場。
独唱・コーラスが入ってからは音量バランスを取りながら弾き過ぎないようにする。
マーチもフーガもいい出来で、終結部に入る。
全員が一丸となり急速調で音は天に舞い上がっていった。
すぐに「ブラボー!」の嵐。
自画自賛になるが、よくこんな難しい曲をできたものだと感心する。
終演後打ち上げ参加のため家族に楽器・衣装一式持ち帰りをお願いする。
シマムラアンサンブルの方々にお会いできたのでお礼を言う。
みんな「良かった!」と言っていただけた。
また、花束や指し入れもあり、高校同窓生のAさん・Mさんからはチョコを、Sちゃんからはワインをいただき感謝!
その他の来て頂いた方にも感謝!
打ち上げは川崎のホテルの宴会場での立食パーティー。
今回は合唱団の方々も混じるのでいつもの倍以上の人数。
先生方のスピーチも面白かった。
入場者人数当てトトカルチョ発表は1506名。
自分は強気に第九の初演の年1842と書いたのであえなく撃沈。
しかし、打ち上げで収穫だったのは飯守先生と直接お話が出来たことで、先生の出しているベートーヴェン交響曲全集のCDで使っているベーレンライター版のことや、オケの規模によりどういう楽譜を使うのかといったことをお聞きすることができた。
なかでもフルトヴェングラーの名前が再三出てきて、「自分はこういう巨匠の演奏を聴いて指揮者を志してきたので原点はそういうところにある」と言われたのにはちょっと感激した。
自分も今回たくさんの第九のCDを参考にしたがフルトヴェングラーのを聴くと自分が戻っていく場所みたいに感じたからである。
最後に先生がスピーチで「いま自分が考えている第九の理想の形で演奏できた」と言ってくださったことはオケ・合唱団にとってこの上ない言葉であった。
あっという間に打ち上げも終了し、同じ部署のヴァイオリンの女性と「終ってしまうとなんか寂しいね。また来年もやりましょう」と話しながら帰途に着いた。
| ■2005/11/25 (金) ゲネプロ(第7回定演) |
昼は品川での外部セミナーに参加し、そのまま船橋で行われるゲネプロ会場に向かう。
船橋文化センターというところだが、反響板を下ろすと合唱団が乗り切らないのでむきだしのままリハーサルを行う。
最初低弦サイドの音が遠くに聞こえていつもと違うバランスにとまどう。
飯守先生も「こういう悪環境でも皆さんよくなっているのがわかる」と激励してくれるので、段々とオケも鳴ってくる。
合唱と今日初めて合わせるソリストの方々が加わり、初めて第4楽章の全員での演奏が実現した。
通し練習のあと細かいところを調整して本番に臨むこととなった。
しかし、船橋は遠かった。
家に帰ると11時半。
疲れたのでビールと焼酎お湯割りを飲んでダウン。
| ■2005/11/23 (水) 最後の?自主連(第7回定演) |
今日しかないと、午前中第九の第1&2楽章を練習。
大体のところはOKだが、第1楽章の6連符から32部音符に移行するあたりと第2楽章の出だし後のpの始まりが難しい。
なんども練習してみるが、第2楽章の弓の飛ばしは不安なままである。
妻と次男は野球の練習で不在なので、やっと昼頃起きてきた長男と昼食を食べに行く。
有名な「餃子の王将」が近くにできたので行ってみると結構繁盛している。
安い割りに量が多いので満腹となる。
家に戻りしばし休憩のあと第3楽章&第4楽章を練習。
第3楽章はまずまずで、最後の3連のところをしっかりとできれば大丈夫そうだ。
第4楽章は難所が最も多く、物理的に弾けない(とトレーナーの先生が言っていた)部分はさておき、もう一度楽譜をよく読み直し、もっと弾きやすいポジション・フィンガリングはないか検討する。
いずれにしても難しいのだが、気休めのために半端なポジションは極力排除して肝心なところは押さえるようにする。
マイスタージンガーは高音に跳ね上がる部分の音取りと32部音符の連なり数箇所が決まれば大丈夫そうである。
ということであとは明後日のゲネプロで成果を試してみたい。
| ■2005/11/20 (日) 一夜明け・・・第九練習(第7回定演) |
昨日はヴァイオリン教室の発表会のためオケの練習には出席できなかった。
今日は久々の予定のない日曜日だが、その分オケの定演の練習をしなければ。
午前中に第1,2楽章とマイスタージンガーをCDに併せて弾いてみる。
前夜に張り替えたインフェルドのレッドの弦はさすがに高性能でピッチがもう安定してきている。
十分本番に間に合いそうだ。
午後は第3,4楽章を練習。
特に第4楽章はまだ指が覚えていない箇所があるのでそこを集中的に練習する。
でも難しい。
あと23日の祭日の自主練習にかかっているといったところか。
| ■2005/11/12 (土) オケ全体練習(第7回定演) |
週末になったが予定はパンパンである。
今日は飯守先生のアシスタント指揮者の方のリハーサルで、全曲の通しと細部のさらなる磨き上げという形で行われた。
第1楽章は自分的には刻みからの転換部分、楽章を通じてのダイナミクスなどだいぶ身についてきた。
第2楽章は出だしのピアノでのリズミックで細かいフレーズが不満、練習要である。
第3楽章はほぼ自分のパートの役割はわかってきたが、最後の3連の刻みが確実でないのでこの部分をしっかり把握したい。
第4楽章はマーチの難しい部分は大分制覇してきたが、リズムが動くところが甘い。
これも身体に叩き込まねばと思った。
終結部はまともに弾くことはとても難しいので、ポイントを外さないようにしていきたい。
来週の合唱との練習は参加できないので、あとはゲネプロ、本番を残すのみ。
できるところまでベストを尽くそう。
| ■2005/11/06 (日) トップサイドでのオケ練(第7回定演) |
11時半に家を出て途中ドトールで昼食をとって会社の練習場へ向かう。
この日はセカンド・トップがお休みでトップサイドの女性がトップに座り、トップサイドを弾いてくれるよう頼まれる。
飯守先生の目の前なので緊張したが、後ろに座っているのとは違い、とてもいい意味で勉強になった。
マイスタージンガー、第九第1&2楽章は大体仕上がってきましたね、という先生のお言葉で全員励まされる。
第3楽章は譜面を弾くことはもう十分出来ているのでその先の最上の音楽、天上の音楽というものを表して欲しいというのが先生の要求だが、そこまでまだ行かない。
次回の課題となった。
第4楽章は3日前とは違い、皆さんとても集中力があって素晴らしい!とお褒めの言葉が多かった。
ただとにかくもっと聞き合えばもっとよくなる、というのが何度も言われたことだった。
そして演奏のための技術であって、技術だけしか見えない演奏は音楽からは遠い、とも。
肝に銘じて取り組んでいきたい。
| ■2005/11/03 (木) 合唱入りオケ練習(第7回定演) |
今日はいつのも会社のカフェテリアではなく、古石場文化センターというところで朝から夕方まで第九の合唱入り練習。
とにかく200人近い人数での練習だっただけに、飯守先生も舞台の壇上から大きな声で指導する。
午前中、マイスタージンガー、第2楽章。
なんとなく落ち着かない感じでざわつく。
全体に集中力の欠落が感じられるが、先生の指導のもと次第に締まってくる。
昼食後、合唱団が加わり第4楽章。
しかし、合唱までのオケ部分でかなり時間がかかる。
飯守先生は妥協することなく求める音が出てくるまで、いろいろと指示を変えてなんとかその域に持っていこうとする。
合唱団が入ってからは、やはり第九の音楽の偉大さの真髄が初めて現れた感じがした。
第4楽章が終ると、オケが残り第1&3楽章。
全体に疲労の色が出てくるが、飯守先生は精力的で最後まで最上の音楽を求める姿には頭が下がる思いだった。
とりあえず課題点は残しながらも、次回3日後のオケのみの練習につなげていく形となった。
| ■2005/10/29 (土) オケ弦練習(第7回定演) |
午前中バタバタしているうちに時間になってしまい、第九の第4楽章を少しだけ弾いてからオケの練習に向かう。
今日は前半が高弦(ヴァイオリン&ヴィオラ)とチェロ・バスに分かれての弦楽器練習、反対側のカフェテリアでは管楽器の分連をやっている。
高弦の練習トレーナーは先週と同じ尾花さんで、みんなが嫌がるところを中心に繰り返し練習する。
ある箇所などは「20回やります」と言って、本当に20回やった。
するとやはりできるようになる。
繰り返し練習の重要さは当たり前、と頭で思うのではなく実際やってみて本当に実感できる。
後半は尾花氏が仕事のため帰られ、パート毎の練習となる。
2ndは会議室にこもり10名で練習。
トップのSさんの指導のもと、やはりいやな部分(音程が大変とか持続力が必要なところとか)をゆっくりしたテンポで音を確認しながら何回もやってみる。
これも効果があり、最初バラバラだったものが回を追うごとによくなっていく。
あとは個人的に苦手な部分を各自個人練習すれば本番までにはさらに良くなるのではないかと思う。
帰りに今月号の「モーストリー・クラシック」誌にオケの紹介がカラー2ページで掲載されており、無料で団員に配布された。
http://mostly.sankei.co.jp/0512/topic/index.htm
残念なことに8月の入院中の取材だったために自分は参加していない。
そう言えば11/26のミューザ川崎の定演の2000枚のチケットはほぼ完売で、当日券の発売もしないかもしれないとのこと。
さすが第九人気といったところだが、立ち見が出ては消防法に抵触するらしく、座席誘導係りの人員を増やすなどいろいろと大変らしい。
出演する側はたくさん入ればその分嬉しいが、裏方の方たちに感謝しなければ。
| ■2005/10/22 (土) 10/22 午後 オケ練(第7回定演) |
午後はそのまま会社のカフェテラスに移動し、オケの弦楽合奏練習に4時間参加。
トレーナーの尾花さんが全体を指導した。
最近家での練習を少しサボり気味だったので、マイスタージンガーの高音の音程が上手く取れない。
勇壮なテーマ部分も全体的に雑になっていると指摘され、もう一度音符の意味を考える。
収穫は細かい高音部でのスピッカートの鳴らし方。
弓のどの部分が一番効果的か、適正な音量で鳴るかが理解できた。
第九は第1楽章は音程の難しい部分をピックアップ。
鳴って欲しいけど音量は出て欲しくない、ということで具体的には弓を寝せて弓幅は多めに使うということでかなり雰囲気が変わる。
さすがに日本を代表するオケのコンマスを30年務めてきた尾花氏である。
第2楽章は出だしの小さな、しかし明確な音が要求される部分、しかも2ndが先発でヴィオラ、1stと続く。
ここも絞られたが、繰り返すうちにコツがつかめ全体的に安定してきた。
第3楽章は2ndの夢見るようなメロディーはただ弾くのではなく、フレーズの節を考えて、感情を込めるように意識を変えるとまったく別物の音楽になる。
ついつい忘れがちになってしまう「楽器を弾いているのではなく、音楽を演奏しているのだ」というを常にもてるようにしたい。
第4楽章は冒頭はチェロ・バスが全面的に出てくる部分を聴いたが、確かにヴァイオリン族に比べ迫力があり、低弦族の最大の見せ場と言える。
そのあと低い方から有名な歓喜の歌のメロディーが奏され、ヴィオラ、ヴァイオリンと加わっていくが、尾花さんいわく「ここは何事もないように平らに進んでいくこと。なぜならこのあとに出てくる合唱が歓喜の爆発となるのだから」
言われてみれば当然だが、このテーマが出てくると熱くなってしまうのは自然の摂理?
そこを抑えられるかどうかが音楽の分かれ道だともおっしゃていた。
「ベルリン・フィルなんかは微動だにもせずここはやっているよ」と。
フーガの部分の超速6連プは「ピアニストの発想で書かれているので、全部正確に弾く必要はないし、弾けない」とパート練習の時に別の先生が言われたのと同じことをおっしゃられ、またまた安心。
「ただし、小節の頭は確実に押さえること」とのことであった。
| ■2005/10/01 (土) オケのパート練&全体練(第7回定演) |
今日は朝10時から12時まで2ndヴァイオリンのパート練習、13時から17時まで全体での練習となかなかハードな一日だった。
10時からのパート練習は緊張の面持ちで参加したが、円座でプロの女性の先生にアドヴァイスをいただきながら進めるという方法で、アットホームな雰囲気でリラックスしてできたのでよかった。
パート・トップの方も「今までと比べ全然良くなっている。みんな弾けてる。」とのことで安心した。
昼は会社の中にあるコンビニでおにぎりを買ってプロの先生を囲んで昼食をとる。
長老(確か91歳くらい)指揮者ジャン・フルネの話になって、東京都交響楽団でフルネの指揮に何度も接した先生いわく「あの先生は5年前に奥さんを亡くしてから元気になったのよね」みんな???「そのあと若い奥さんと結婚してその奥さんがメネージメントも全部やっている」とのこと。
普通妻に先立たれると男はだめになるというが、そういうケースもあるのかと納得。
午後は東京シティ・フィルのS氏の指揮によるワーグナー「マイスタージンガー」ッ前奏曲、第九第4楽章、第2楽章をみっちりと練習。
マイスタージンガーは場面転換の微妙な部分が数箇所出てくるが、最初はいやな分部だなと思っていたが、スコア上何がどう行われているかが段々わかってきてからは弾くことから表現することにマインドが移ってきたように思う。
第九は、4楽章マーチのあとの中間部の管弦楽の延々と続く部分がやはりターゲットとなり、何回かパートごとにわけて確認。少しずつ合うようになってきた。
あと場面が変わる部分の雰囲気の転移、これは音楽全てに通じることだと思うが、全体を考える場合非常に重要なことで、常に最新の注意を払なればいけないことだと感じる。
第2楽章も速いパッセージの呼吸を各パート内、パート間でいかに同じ意識をもって演奏していくかということを考えさせられる練習だった。
最後は第3楽章、第1楽章の通しで終了。
両楽章共オケ全体で通すのは自分にとっては初めてだったが、CDに合わせるのとはやはり全然違い、指揮者の呼吸、パート・トップの呼吸がわかると今自分が音楽のどこにいるのかがよくわかる。
ということで結構へとへとになったが、非常に自分にとってはまた一山越えて、定演に対して抱いていた高い山が、登頂可能な見通しが立った感触を得ることが出来た。
| ■2005/09/29 (木) 第九の練習(第7回定演) |
夜は第九の練習。
第4楽章のマーチのあとの延々と続く8分音符、そして時々出てくるシンコペーション、速いのでなかなかおっつかない。
そのあとのフーガの6連プの雨嵐もまだまだダメだ。
疲れたので、エックレス、ラ・フォリアで鬱憤?を解消するが、全体に弓が荒くなっている。
時間がまたなくなってきた。
体が良くなってくれば、時間が足りなくなってくる。
なかなかバランスよくはいかないものである。
| ■2005/09/27 (火) 久々の朝練(第7回定演) |
今朝は5時に起きれたので1時間朝練をする。
エックレスと第九の4楽章でいっぱいいっぱい。
シャワーを浴び、朝食を食べて7時過ぎに家を出る。
例によって電車の中でスコアを読むが、ついうつらうつらしてしまう。
今週末から土日はオケ、S楽器店の定演の練習で11月まで埋まっている。
体力的にかなり復活してきたようなので何とか乗り切りたい。
| ■2005/09/17 (土) 久々のオケ練(第7回定演) |
久しぶりに会社のオーケストラの練習に参加した。
弦楽練習であったが、ワーグナーとベートーヴェンの第1、4、2楽章でタイムアップ。
なんとか本番までには体調を整えて、ミューザ川崎の舞台に立ちたいものである。
この夏ずっとひっかかっていた懸案事項がやっとその第一歩を踏み出せた感じである。
精神的にもかなり楽になった。
| ■2005/09/14 (水) 少し練習(第7回定演) |
帰ってから少しオケ曲の練習。
まだまだ問題山積みだが、最初はゆっくり、段々速くの原則で少しずつ壁を乗り越えていくしかない。
しかし第九の第1楽章の6連譜が延々続くところはなんか繰り返しの魔力というか忘我の世界に引き込まれてしまう。
でもそれではいけない。
ちゃんと正確にサポートが出来なければ。
難しいけど少しずつわかり面白くなってきた。
| ■2005/09/12 (月) 電車の中で(第7回定演) |
電車の行き帰りは第九とマイスタージンガーの譜面を音と照らし合わせながら、不明点を少しでも解消しようとするが、やはり難しい。
今回も2ndヴァイオリンなので特に難しい。
1stヴァイオリンも難しいが、メロディー中心なので耳タコの曲はある種フィーリングで弾けるが、2ndはそうはいかない。
底が奥深くて面白いと気づいてはいるのだが・・・第九の4楽章、あの速さでのパッセージはコンチェルト並みのものが随所にある。
週末の練習までせいぜい輪郭だけでもなぞれるようにしましょう。
| ■2005/09/11 (日) 合宿不参加(第7回定演) |
今日は合宿にいけない分オーケストラの曲の練習をした。
第九は第1楽章は大分わかってきた。第2楽章も譜面は追えるが音程がまだダメである。
第3楽章はスコアでよく確かめてからパート譜を弾いてみるとだいぶ感じがつかめてきた。
第4楽章は速い部分などはまだ全然追いつけない。これから。
ワーグナーは前半は大分譜割りはわかってきたが、場面が変わるところが数箇所あり、テンポの伸び縮みを把握するにはもう少しかかりそうだ。あと後半の速いパッセージ(パターンが微妙に違ういやらしさ)も難関である。
来週の初参加までにはなんとか形にしておきたい。
しかし大曲だ。
| ■2005/08/20 (土) オケ練欠席(第7回定演) |
今日はオケ練の後半3時間は飯守先生の初顔合わせなので、楽器が弾けないまでも見学に行こうと思っていたが、シャバの酷暑でスタミナを奪われてしまいこれは無理と断念。
はやく復帰したいなぁ。
| ■2005/07/09 (土) 第7回定演練習始まる・・・が(第7回定演) |
椎間板ヘルニアのブロック治療で入院したが、1泊で退院できた。
朝特に痺れがなければということだったので、午前中に退院。
今日からオケの第7回定演の練習が始まるが、参加できず残念だ。
| ■2005/05/29 (日) 第6回定期演奏会 |
| 2005年05月29日 第6回定期演奏会 (大田区民ホール・アプリコ 大ホール) |
指揮:円光寺雅彦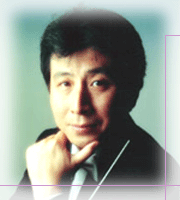 ブラームス 交響曲第4番 ホ短調 作品98 ドビュッシー 小組曲 ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲 |

朝起きて最終チェック(ヴァイオリン、衣装)をし、会場へ向かう。
蒲田にあるアプリコ大ホール。
正面から入り地下の楽屋へ行くとメンバーが揃い始めている。
ヴァイオリンを持ってホールに行く。
観客席は照明が落としてあるが、2階席後方が高く遠くに広がっている。
カッコいいなぁ、と思ってしまった。
10:30になりステリハが始まる。
タンホイザーの冒頭のホルン、天高く昇華していくような響きに聞き惚れる。
低弦の後のヴァイオリンのテーマ提示もたっぷりとした音を感じながら弾くことができる。
ドビュッシーも、ブラームスも今までとは別の次元にいるような感覚である。
これはうまくいくな、と思った。
ステリハ終了後、衣装着替えや昼食を取って舞台裏に待機する。
初めて蝶ネクタイをするので家では面映かったが、皆同じスタイルなので気にならない。
モニターを見るとほぼ満席状態になっている。
体の中を高揚感を伴った緊張感が走る。
開演。
舞台に出ると緊張感が抜け体が軽くなる。
いい演奏をしようという気持ちが前に出てくる。
指揮者の円光寺先生が登場し1曲目「タンホイザー序曲」の棒が振り下ろされる。
順調に曲は進み(細かい乱れはあったが)、最後の大団円を迎える。
最後の音が天井まで舞い上がっていったとき、客席で聴いてみたいなと思った。
ドビュシーの「小組曲」もオケの色彩の変化がうまくつけられたように思う。
前半終わって、あっという間で短く感じた。
休憩後、後半。
ブラームスの交響曲第4番、第1楽章冒頭。
今までで一番ぞくっとする入りだった気がする。
諦観の漂う第2楽章、一瞬の煌きの第3楽章、重厚で厳しい第4楽章・・・自画自賛になるが、よかった。
オーケストラの生き物のような不思議というものを味わった。
アンコールのシベリウス「カレリア行進曲」で華々しく締めくくった。
終演後、アンサンブル倶楽部の方たちと会い会話することができた。
皆さん熱心に聴いてくださったことに感謝。
その後家族に会い楽器と衣装を渡す。
さあ、手ぶらで打ち上げに行こうとすると、「花束とか届いてます」とのこと。
花束とかプレゼントとかいくつか自分宛のものが置いてある。
ありがたいことだ。
結局また大荷物となり打ち上げ会場へ向かう。
90名参加の大打ち上げ。
事務局から来場者数は1090名と過去最高であったことが発表され、大いに盛り上がる。
後援会長の会社の重役、指揮者の円光寺先生などが出席し、これまでの一丸となった成果を改めて感じる。
次回の事務局長が、「次は11月の第九、初の合宿もやります!」と告げ、はや第九への思いを馳せる。
さすがに2次会はパスし帰宅。
帰って妻も、会社であれだけのことができるとはすごい!と今月2度目のお褒めの言葉。
(1回目は5/15のシンデレラッステップ)
クタクタなので風呂に入り、寝る。
また一山越えることができた。
| ■2005/05/28 (土) ゲネプロ(第6回定演) |
午前中オケの各曲の難しいパッセージの練習、次男のレッスンをみる。
次男も1/4にしてからは、疲れたからという理由ですぐに休憩するのを禁止にする。
だいぶ慣れてきたようで1/8のときのような自在感が出てきたようだ。
午後は森下文化ホールというところでゲネプロが行われた。
場所は狭いがホールというだけあって、会社でのカフェテリアでの練習よりちょっと残響などを感じる。
全曲の通しとピックアップで、円光寺先生は「今日の言ったことは必要最小限なのでこれだけは必ず守ってください」ということであった。
自分的にも全体的にもまだ怪しげな箇所があるが、もう明日に迫った公演、持っているものをすべて出す気持ちでやっていきたい。
| ■2005/05/21 (土) 本番1週間前のオケ練(第6回定演) |
いよいよ定演の1週間前になった。
今日の練習ではフルメンバー近くが揃い、結構両隣前後の空間が狭い。
本番は2ndの5プルトなのでフルートがすぐ後ろにいる。
管楽器が間近に聞こえるので面白い。
優雅に聞こえるオーケストラもそれぞれの近くでは人間が音を出しているんだ、というのが実感できる。
これが客席に届く時いいサウンドになるんだなぁ。
全曲練習なのでかなりタイト。
弦トレの尾花先生もやってきて、「もっとアンサンブルを意識して!指揮者の先生に失礼だぞ!」と活を入れる。
全体としては先週の方がまとまっていた気がするが、自分的には弾けない部分を練習していったので改善はできたと思う。
あと1週間なので、細かい部分を毎日少しずつチェックしておこう。
| ■2005/05/14 (土) オケ練 ドビュッシー&ワーグナー(第6回定演) |
午後はオケ練で、今日はタンホイザー、ドビュッシーを集中的に行うとのことで午前中予習してから行く。
前の部署で一緒だった人がオーボエ、コールアングレーで出演するのを知り、挨拶に行くとお互い数年ぶりで懐かしく会話を交わす。
今までも一緒に練習していたのかもしれないが、大所帯なので弦、管、打楽器それぞれで会話をすることが精一杯。
プログラムの原稿が出来上がって初めて知ったという間抜けな話。
今日の練習はなんとなく後回しにされていた感のあるドビュッシーをかなり丹念に練習。
低弦が頑張りすぎると円光寺さんが「そんな、オレはなーにーわー(浪花)のドビュッシー、みたいな感じで弾かないで!」
というのには皆大受け。
例えが的確でわかりやすくたいへん勉強になる。
やはり指揮者は天性のものだとまた感じる。
ワーグナーはヴァイオリンにとって地獄の16分音符が5ページくらい続くが、それ以外にも難所多し。
しかし序曲なのに大曲1曲分の満足感がある。
自分的には両方とも満足のいく練習だった。
終了後、11月の定期で共演する合唱団の方達が挨拶にきてくださった。
ああ、本当に第九プロジェクトが動いているのだなぁ、と実感。
| ■2005/05/08 (日) GW最終日はオケ連(第6回定演) |
GW最終日はオケの練習。
今日は円光寺先生ではなく、N響の管の方。
サヴァリッシュはこの部分はこう言った、などと聞くと何かすごいところにいるなという気になる。
タフな先生で休憩はちょっと取らず、ドビュッシー、ブラ4を全部細かく指導してくださった。
今日隣に座った女性がベテランで上手くていろいろ勉強になった。
社員の家族の方だということで毎回定演には出ているそうだ。
行くたびに少しずつ知り合いが増えていくのも嬉しい。
しかし本腰を入れて譜面を覚えるくらいにしていかないと本番ではフラストしそうだ。
好きな曲なので悔いのない事前練習をして臨みたい。
帰りはパートのトップの人に飲み会に誘われたが体力的にダメだと思ったので丁重にお断りする。
| ■2005/04/23 (土) 週末のオケ練(第6回定演) |
ブラームスの4番交響曲を4時間みっちり行う。
細かく各楽章を見ていき、どこでどういう呼吸で音楽を表現していくかを指示する。
バラバラとなっていた音符が意味のある音楽となっていく様が弾きながらも感じられる。
オーケストラって本当に不思議なものだ。
全体練習のあとは2nd有志でのパート練習。
7名残り、トップの人の指示で各曲各部分で、ピックアップして練習する。
結局こちらも2時間弱。
指揮者の先生を囲んでの飲み会は疲れたのでパス。
またまたたくさん練習の休日だった。
| ■2005/04/09 (土) オケの弦練(第6回定演) |
今日はオケの弦トレの日。
例によって午前中は個人練習に集中。
午後から出かける。
今日はコンマスも2ndトップの人も来ずややヴァイオリンが少ない感じ。
トレーナーの尾花さんはいろいろなオーケストラを経て(コンマスなども務めた)フリーでヴァイオリンの指導やアンサンブルなどを企画している結構有名な人だということがわかった。
しかし、弦トレも最終日で結局個人的には会話ができなかったのは残念だ。
今日の練習内容は、マイスタージンガー、ブラ4、ドビュッシーの順で、やっと曲になれてきた気がする。
尾花氏はこのオーケストラはブラームスの感性がとても合っているとおっしゃっていた。
個人的には細かい部分がまだまだ把握できていないので次回までにはなんとか精度を上げたいと思っている。
| ■2005/04/05 (火) 正式入団(第6回定演) |
今朝は5時に起きれたので朝練ができた。
といってもブラ4の1,2楽章の運指の確認くらいしかできなかったが。
電車のウォークマンでのイメトレしかないな。
会社のオケのヴァイオリン・リーダーの人から正式な入団申請依頼が出て、晴れて正式入団となったようだ。
それはそうだろうな。
試用期間があって技術的な側面、人間的な側面からの判断があるのは共同活動では当然のこと。
一応ほっとした。
| ■2005/04/02 (土) オケ全体練習(第6回定演) |
午後から円光寺氏の初のリハなので午前中はほとんど練習できなかったオケの曲を練習。
タンホイザーはホントに弾けるのかな?というくらいすさまじいヴァイオリン・パートの楽譜だ。
ブラームスは大体わかった。
ドビュッシーは時間切れで練習できず。
午後会社のカフェテリアでの練習。
円光寺氏の指揮でいきなりタンホイザー序曲を通す。
最初の氏の感想が「皆さんの呼吸は浅い。深呼吸して始めるように」
しかし、指揮者がいるとあのいつ果てるともわからない16分音符の羅列が音楽となって弾けるというのが体感できた。
なるほどオケには指揮者が必要なわけだと改めて実感。
休憩後ブラ4をこれまたいきなり全4楽章を通す。
初めて管楽器との合同練習に参加したが、確かに社員だけでこうした曲を演奏してしまえるというのはすごい!
ブラ4も全体の雰囲気、個別箇所での表現の仕方、いろいろなことを指導していただく。
最後はドビュッシー。全然弾けないかと思ったが、隣の女性が結構弾けるのでそれに合わせていくと大体感じはつかめた。
終ってからは緊張からの解放かへとへとになったが、充実感はいっぱいだった。
| ■2005/03/28 (月) 11月定演は第九! |
会社のオケ管理者から11月定演の内容が決まったとのこと。
なんと第九!
指揮:
飯守泰次郎氏
合唱:
東京シティ・フィル・コーア
しかもミューザ川崎のシンフォニーホールとのことなので、これはぜひとも参加したいと思った。
なんとなくうきうきした気分で帰る。
| ■2005/03/27 (日) オケ曲の練習(第6回定演) |
本日は家族全員休養の日。
午後ブラ4の第1&2楽章と「タンホイザー序曲」の譜読みと練習をする。
どちらも難しい。
特にタンホイザーの後半は16分音符が延々と続きCDに合わせようとしてもなかなか合わない。
結局スコアとにらめっこをして金管の主旋律がどう進行しているかを照らし合わせたら少しわかってきた。
しかし、ブラ4の第3&4楽章もあるし、ドビュッシーもあるし、定演まではこちらにかかりきりにならないとイカンかな、と思ってしまった。
とりあえず明日から少しずつ積み上げてやっていこう。
| ■2005/03/12 (土) 会社のオケ初参加(第6回定演) |
今日の午後は会社のオーケストラに初参加、会社のカフェテリアが練習場所だ。
弦合奏の日で総勢30名以上の弦楽合奏はなかなか壮観である。
曲はドビュッシーの小組曲とブラームスの交響曲第4番。
両方とも初見なのでキツい。
みな演奏レヴェルが高く、みな大人ですぐに溶け込めそうだ。
さすがである。
トレーナーはプロの方で、「総じてブラームスは皆さん理解していらっしゃる。だから細かいところを積み上げればいい演奏になりますよ」とポジティブに指導してくれるところもモラルアップにつながる。
30年ぶりのフルオーケストラへの参加だが、自分にとっては非常に刺激になった。
次回までにパート譜を読み下し音楽表現ができるレヴェルまで練習していこう。
| ■2005/03/02 (水) 会社のオーケストラ |
会社のオーケストラに興味を持ち、取りまとめている人にメールで聞いてみる。
年2回定演があり、プロの指揮者に振ってもらうというスタイルで運営している。
ちゃんとしたシンフォニー・ホールでフル・オーケストラでやるので参加したくなってきた。
次回は好きなブラームスの4番交響曲とタンホイザー序曲とのことなので少なくとも聴きに行ってみよう。
![]()